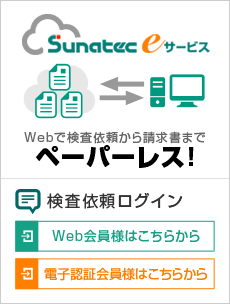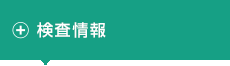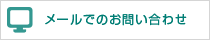腸炎ビブリオ
特徴
この菌は海水や海泥中に潜み、お刺身や生鮮魚貝類からよく検出されます。サルモネラ同様に発生の多い食中毒原因菌で、この菌は夏になると活発に活動するため特に注意が必要です。塩水を好むが真水には弱く、また熱にも弱く100℃数分で死滅し5℃以下ではほとんど増殖しないという性質があります。細菌の増殖速度が他の細菌に比べて早く、調理後の食品の取扱いにも注意が必要です。
腸炎ビブリオによって起こる食中毒は、魚介類に付着した腸炎ビブリオがまな板・包丁・など調理器具を介して他の食品を汚染し(二次汚染)、その食品から食中毒を引き起こすこともあります。
最近では血清型03:K6タイプが主流となっている。(心臓停止作用の有る耐熱性溶血毒を持つ)また、増殖速度が速く、至適温度では1個のビブリオは3時間で食中毒を発症させる菌量に達します。
腸炎ビブリオによって起こる食中毒は、魚介類に付着した腸炎ビブリオがまな板・包丁・など調理器具を介して他の食品を汚染し(二次汚染)、その食品から食中毒を引き起こすこともあります。
最近では血清型03:K6タイプが主流となっている。(心臓停止作用の有る耐熱性溶血毒を持つ)また、増殖速度が速く、至適温度では1個のビブリオは3時間で食中毒を発症させる菌量に達します。
原因食品
お刺身・生鮮魚貝類とその加工品等
食中毒症状
飲食後、数時間から24時間で激しい腹痛と下痢がおこります。下痢はしばらく続くため脱水症状を起こすこともあり注意が必要です。腹痛は刺しこむような激痛で、しばしば発熱も見られ、吐き気・嘔吐もまれにみられるが2~3日で回復します。
潜伏時間は約10時間から24時間(短い場合で2、4時間)で、激しい腹痛、下痢などが主症状です。発熱、はき気、おう吐を起こす人もいます。
潜伏時間は約10時間から24時間(短い場合で2、4時間)で、激しい腹痛、下痢などが主症状です。発熱、はき気、おう吐を起こす人もいます。
予防のポイント
夏場6月~10月は特に注意!
- ・
- 魚介類は真水でよく洗ってから調理する。
- ・
- 調理する直前まで他の食品と接触しない用に、冷蔵庫など低温で保管する。
- ・
- 調理したお刺身等の生ものは出来るだけ早く食する。
- ・
- まな板・包丁・布巾等の調理器具は十分洗い、熱湯や漂白殺菌液等を用いて消毒する。
- ・
- 調理器具は魚介類専用。のものを使用するほうが好ましい。
詳細
最近減少傾向にあった腸炎ビブリオ食中毒は、1994年から増加を示し、1998年には事例、患者とも1位となる、また、発生は7~9月に集中している。
- §1.
- 【血清型】
1995年まではO4:K8であったが、'96からはO3:K6とその類似パターンに激変。
・この血清型はインド亜大陸、韓国、台湾、米国でも発見されており、日本周辺海域に広く分布している。
・但し一般の腸炎ビブリオ検査ではO3:K6は極めて検出しにくいが、菌の耐熱性等は従来菌株と大差ない事から、食中毒は管理の徹底で防御できる。詳細については厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/)をご覧下さい。生食用魚介類とゆでがに、ゆでだこについて規格基準が定まりました。 - §2.
- 【一般的特徴】
(1)発育に食塩を要する。(至適食塩濃度2~4%)
(2)真水や熱に極めて弱い、42℃以上、15℃以下発育抑制(至適発育温度:35~37℃)
(3)分裂速度が極めて速い(8~10分で2倍となる)
(4)夏場の近海もの魚介類は殆どが汚染と考えるべきで、またこれらよりの2次汚染により発生する場合が多い。