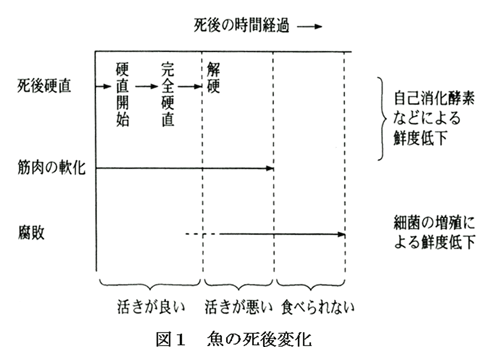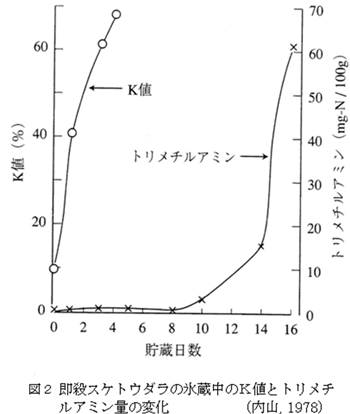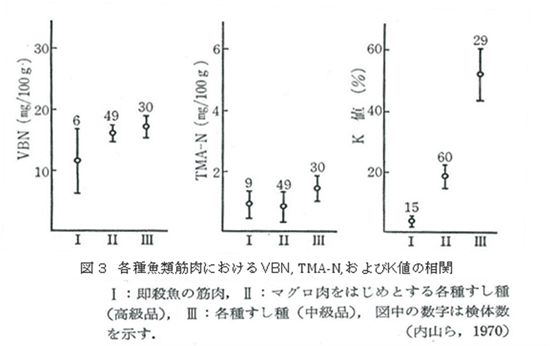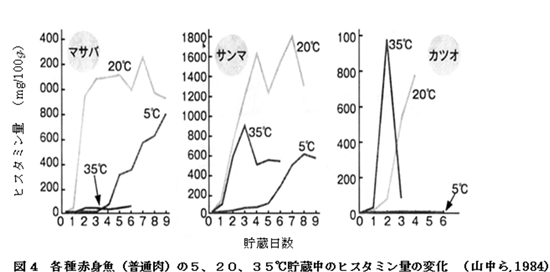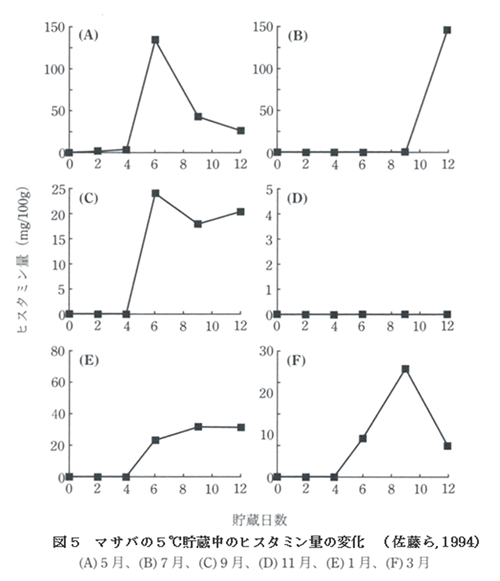|
食品企業の品質管理担当者が誤解しているかもしれない
食品微生物の基礎知識 東京家政大学大学院
客員教授 藤井建夫 1.はじめに私たちが日ごろ正しいと思っている常識にも案外間違っていることがある。教科書に書かれていることは正しいと信じてしまいがちである。確かに高校までの教科書には検定制度があることもあって、大きなミスには出会わなかったかもしれないが、大学生向けの教科書となると、自由度が増す分、必ずしもそうとはいかない。 ① 微生物の作用によってタンパク質が分解される場合を腐敗、炭水化物が分解される場合を発酵という。 ② 腐ったものを食べると食中毒になる。 ③ 生菌数測定は公定法の35℃培養で行うのが正しい。 ④ 魚のK値が60%以上(または60~80%)になると初期腐敗とみなされる。 ⑤ 食品中のヒスタミン含有量は腐敗指標として用いられる。 ⑥ さば味噌煮は十分加熱をするからヒスタミン食中毒にはなりにくい。 ⑦ 120℃4分の加熱をすればすべての微生物が死滅する? ⑧ かつお節は優良カビの増殖によって水分量が減少する(保存性が高まる)。 ⑨ 塩辛の熟成(旨味成分の増加)は魚介肉の自己消化酵素によるが、微生物の酵素作用も大きい。 ⑩ ふぐ卵巣糠漬け工程では、乳酸菌の働きでフグ毒が分解される。 これらを正しいと思っている方が多いのではなかろうか。食品学や栄養学関係の教科書、参考書ではこのように書かれているものが多いのでやむを得ない。国家試験問題の解説書などでも、そのように説明しているものが多いが、実はすべて間違いである。しかも、過去の国家試験(薬剤師、管理栄養士など)やセンター試験などでも、これらの間違いをベースとして出題されたこともあるので、影響は大きいと言わざるを得ない。 2.K値が60%になると初期腐敗?魚は鮮度低下が早いため、品質評価の上でとくに鮮度が重要視される。しかし、一口に鮮度といっても、刺身の鮮度とアジの一夜干しの鮮度ではまったく意味がちがう。刺身で問題となる鮮度はいわゆる活きの良さで、生鮮度ともいわれる。一方、アジの一夜干しの場合には食べられるかどうか(腐敗の程度)という意味での鮮度で、鼻で臭いを嗅いで見分けることができる。 3.ヒスタミンは優れた鮮度指標である?栄養系や薬学系の国家試験受験参考書で、ヒスタミンを鮮度指標として用いることができると書いてあるものを見かけるが、これは間違いである。 ① 魚種(試料)ごとに蓄積量や傾向が異なる。 ② 35℃がもっとも著しい場合と、20℃の方が35℃よりも著しい場合がある。 ③ いったん蓄積したヒスタミンが減少する場合がある。 ④ 35℃でもまったく蓄積しないことがある。 ⑤ 5℃においても5日以内に100mg/100g程度認めうることがある。 このようにヒスタミン蓄積がまちまちな傾向は、図5に示すように、同じ魚種(マサバ)、同じ貯蔵温度(5℃)でもみられる。まずヒスタミン蓄積の傾向が試料によって異なる理由は、魚に付着しているヒスタミン生成菌には増殖温度域の違う菌群(低温菌、中温菌)が存在し、その種類や数が試料によって大きく異なるためである。たとえば中温菌が優勢な試料では5℃でのヒスタミン生成は起こらないが、低温菌が優勢な場合には35℃での蓄積はなく、逆に5℃でも蓄積が見られることになる。
また、魚にはヒスタミン生成菌だけでなく、ヒスタミン分解菌も存在するので、ヒスタミンの蓄積量は分解細菌によっても影響を受ける(さらにヒスタミンの生成、分解活性は魚肉のpHによっても異なる)。その結果、魚の貯蔵中のヒスタミン量変化は試料によって大きく異なることになる。これらのことからヒスタミンは魚の鮮度指標とはならない。
しかし、第87回薬剤師国家試験(平成14年)には次のような問題が出題されたことがある。 問75 食品の腐敗に関する記述のうち,正しいものの組合せはどれか。 a 腐敗により生じるカダベリンは、アルギニンに由来する。 b 腐敗により、トリプトファンから発がん性のTrp-P-1が生じる。 c 魚類に含まれるトリメチルアミンオキシドは、還元されて腐敗臭の原因物質を生成する。 d 食品中のヒスタミン含有量は、腐敗の指標として用いられる。 1(a,b) 2(a,c) 3(a,d) 4(b,c) 5(b,d) 6(c,d) 記述のうちaとbは間違いであるので、出題者はcとdを正しいと考えていることになり、この問題は解答不能である。しかも全く同じ問題が平成20年の第93回国家試験(問65)にも出されている。 略歴藤井建夫(フジイ タテオ) サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |
| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |