| ◆ HOME > ヒスタミン食中毒の現状と対策 |
 |
|
 |
|
| ヒスタミンによる食中毒は戦後まもなく国内各地で多発した。最近は年間数件、患者100名に減少しているが、どういうわけか、平成20年は急増し、発生件数22件、患者数462名であった(図1, 表1)。とくに学校や保育所などでの給食によるものが多い。その後も平成21年1月には札幌市の小学校で患者数259名の大規模な事件が発生している。 |
| この食中毒はヒスタミンを高濃度含む食品を摂取した場合に、ふつう、食後30〜60分位で、顔面、とくに口のまわりや耳たぶが紅潮し、頭痛、じんま疹、発熱などの症状を呈するもので、重症になることは少なく、たいてい6〜10時間で回復する(抗ヒスタミン剤の投与により速やかに全治する)。そのため食中毒としての届出は少ないが、今でも家庭などでの小規模な事例は多発していると思われる。 |
| 海外でも以前からシイラやツナ缶詰などによるアレルギー様食中毒が知られているが、最近は魚食志向を反映して増加傾向にある。 |
| 図1.原因施設別ヒスタミン食中毒発生件数と患者数の推移(斎藤, 2009) |
| 表1.2008年に発生したアレルギー様食中毒事例(登田、2009に追加) |
|
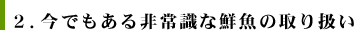 |
|
| 2008年に起こった具体的な食中毒事例として『食と健康』2009年8月号(齊藤智子氏)の記事より拾ってみた。 |
| 平成20年10月8日に都内の社員食堂で起こったマグロのマヨネーズ焼きによる事例では、490人中16名が発症した。このときのマグロのマヨネーズ焼きは残品が少なく、検査ではヒスタミンは検出されなかったが、原材料は冷凍輸入のキハダマグロ(インドネシア産)であり、原料加工者が保管していた輸入日、輸入業者、現地での製造者が同じキハダマグロロイン未開封品3検体中1検体から730mg/100gのヒスタミンが検出されている。したがって輸入時点ですでに高濃度のヒスタミンが生成されていたと考えられる。漁獲後、船上や市場、流通過程での取り扱いに問題(氷を使わなかったり、長時間放置など)があったのであろう。 |
| 11月22日には、都内の小学校の給食で、これと同時に輸入の原料を用いたマグロのケチャップ和えを食べた児童や教職員675名中43名の患者が発生し、検食のマグロのケチャップ和えからは20mg/100gのヒスタミンが検出されている。 |
| 10月15日に発生した別の事例では、都内の飲食店でブリ照り焼き定食を食べた2名が発症し、残品のブリ照り焼きからはヒスタミンが270mg/100g検出された。この店では、10月4日に市場で仕入れたブリを半身に切り分け、一方の半身を2,3日間、刺身や焼き魚として提供し、残りの半身は冷蔵し、11日後に12切れにカットし、たれに漬け、注文ごとに焼いて当日のランチとして提供したという。冷蔵庫で10日以上も経った鮮魚を提供する飲食店があるとは驚きである。 |
|
 |
|
| この食中毒の原因物質はヒスタミンという化学物質であるので、わが国の食中毒統計では化学性食中毒の中の「その他」として分類されているが、このヒスタミンは食品の貯蔵・加工中に増殖した細菌のヒスチジン脱炭酸酵素作用によって生成されるという点でほかの化学性食中毒とは性格を異にし、むしろ細菌性食中毒と考えるべきであろう。また免疫反応の異常によって起こる食物アレルギーと症状は似ているが発症機構が異なるので、アレルギー様食中毒と呼んで区別している。 |
| この食中毒はおもにマグロ、カツオ、カジキ、サバ、イワシ、アジなどの赤身魚やその加工品(みりん干し、照り焼き、フライ、竜田揚げなど)で起こるが、赤身魚が本食中毒の原因となりやすいのは、ヒスタミンの前駆物質となる遊離ヒスチジン含量が白身魚では数mg〜数十mg/100gであるのに対し、赤身魚では700〜1,800mg/100gと非常に高いためである。一般的には100mg/100g以上の食品で発症するとされているが、実際には摂取量が問題であり、食中毒事例から発症者のヒスタミン摂取量を計算した例では大人一人当たり22〜320mgと報告されている。 |
|
 |
|
| アレルギー様食中毒はかってはプトマイン中毒と呼ばれ原因不明であったが、1953年にこの食中毒が魚肉腐敗細菌によることが木俣らによって初めて明らかにされた。その分離株は低温増殖性などの点で当時の Bergey’s Manualの記載とは異なったためAchromobacter histamineum として報告されたが、これが現在、代表的な原因菌として有名なモルガン菌(Morganella morganii )である。 |
| これまで鮮魚やその加工品のヒスタミン生成菌としてよく知られているのは、M.morganii,Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, E. cloacae, Raoultella planticola などの腸内細菌科細菌であり、実際の食中毒事例からの分離株もM. morganii、R. planticola, Hafnia alvei などの腸内細菌科細菌であった。 |
| 一方、海洋や魚の腸管、体表などにも低温性と中温性の2種の好塩性ヒスタミン生成菌(Photobacterium phosphoreum およびP. damselae )が存在する。モルガン菌とこれら2種のヒスタミン生成菌の特徴を表2に挙げておく。海洋性のヒスタミン生成菌は従来あまり注目されていない菌群であるが、P. phosphoreum は冷蔵温度でもヒスタミンを生成することができ、一方P. damselae はM.morganii と同程度に強いヒスタミン生成能を有するという点で重要である。 |
| 表2.水産物の主なヒスタミン生成菌とその増殖特性 |
|
 |
|
| モルガン菌と2種の好塩性ヒスタミン生成菌の沿岸海域での出現状況を調べた結果では、低温好塩性のヒスタミン生成菌(P. phosphoreum )は主に冬から初夏にかけて存在し、夏には中温好塩性の菌(P. damselae )が多く出現する。一方、モルガン菌はもともと腸内の菌であるので、清浄海水(たとえば相模湾)からは検出されず、比較的汚れた海水(たとえば東京湾湾奥部)から検出される。 |
| また、市販鮮魚について調べた例(図2)では、中温好塩性菌やモルガン菌はおもに夏場に検出され、低温好塩性菌は周年高頻度に検出される。このうち、中温好塩性のヒスタミン生成菌は夏の鮮魚から多いときには103〜104/cm2検出されることがあるので、過去の食中毒事例の中には本菌によるものも含まれていた可能性がある。 |
| 一方、低温好塩性のP. phosphoreum は2.5℃貯蔵の魚肉中に多量(61〜144mg/100g)のヒスタミンを産生することが確認されているので、低温流通が主流の鮮魚介類では食品衛生上注意すべき細菌である。 |
| 海水や鮮魚からは好塩性ヒスタミン生成菌が分離され、実験例では貯蔵中にこれらが増殖してヒスタミンを蓄積するにもかかわらず、これまで食中毒事例からこれらの好塩菌がほとんど分離されないのは、(1)わが国ではアレルギー様食中毒が、行政的には化学性食中毒として扱われるため、原因菌の究明までは行われない事例が多いこと、(2)微生物検査が行われたとしても、本菌が検査に常用される食塩無添加培地では増殖できないこと、(3)低温好塩型菌が原因菌の場合には常用の35℃培養では増殖できないこと、(3)本菌群は冷凍に弱いので凍結保存したサンプルでは死滅してしまうこと、などによるのであろう。 |
| なお、P. phosphoreum を原因菌とする事例は丸干しいわしによる食中毒事件において、2004年にはじめて報告されている。 |
| 図2.鮮魚に付着しているヒスタミン生成菌数の季節変化(与口ら) |
|
 |
|
| 図3は、カツオ、サンマ、マサバなどの赤身魚を各種温度(5、20、35℃)に貯蔵して普通肉部のヒスタミン量の変化を調べた結果であるが、試料によって蓄積量や傾向が異なり、35℃がもっとも著しい場合、20℃の方が35℃よりも著しい場合、また35℃でもまったく蓄積しない場合があり。5℃においても5日以内に100mg/100g程度に達する場合、いったん蓄積したヒスタミンが減少する場合などがあり、一定の傾向がみられない。 |
| 魚肉中でのヒスタミン生成には、5℃貯蔵では低温菌(P. phosphoreum )が、35℃では中温菌(P. damselae、M. morganii など)が、20℃ではこの両者が関与すると考えられるが、試料によってヒスタミン蓄積の様子(増加開始時期や蓄積量、消長パターン)が異なる原因は、付着しているヒスタミン生成菌の種類や数が季節や海域によって異なるほか、ヒスタミン分解菌(腐敗菌のPseudomonas putida など)もいるので、その分布や消長などによっても大きく変動するためである。 |
| 図3.各種赤身魚(普通肉)の5、20、35℃貯蔵中のヒスタミン量の変化(山中ら) |
|
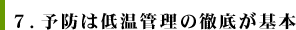 |
|
| 近年わが国近海での漁獲量が減少傾向にあるため、アジやサバ、カジキなどの加工用原料を外国から輸入したり、中には加工も海外で行うケースが増えており、現地での品質管理が十分でない場合には原料や加工段階でのヒスタミン蓄積が危惧される。 |
| 鮮魚にはもともと海洋性のヒスタミン生成菌が付着している可能性が高いので、室温での放置を避け、低温貯蔵によってその増殖を抑制することがもっとも基本的な予防対策である。ただし鮮魚を5℃で貯蔵しても、上記の低温性ヒスタミン生成菌が増殖して5日以内に100mg/100gに達することがあり、しかもこの菌は108〜109/gに達したときでもほとんど腐敗臭を発しないので要注意である。 |
| また学校給食ではカジキのフライや照り焼きなどによる事例がよく見られるが、原料のカジキは最終段階で切り身になるまでにいくつもの業者を経由し、そのたびに解凍凍結が繰り返されることがあり、その際の取り扱い不適による品質低下も心配される。 |
| 学校給食では原料が当日の朝に解凍された状態(切り身)で搬入されるが、この管理がなかなか難しいのではないだろうか。凍った状態では加熱調理に支障があり、解凍し過ぎても問題が生じる。また、切り身状態のカジキが調理台のそばの暑い所に放置(その間に菌が増えて原因物質のヒスタミンができる)されることがないような注意も必要である。最終的に加熱するという安心感があるのかも知れないが、実際にはいったん生成されたヒスタミンは調理加熱では分解されないことを十分理解すべきである。 |
| はじめにも述べたように、アレルギー様食中毒はわが国では化学性食中毒として扱われているが、ヒスタミンは原料魚の貯蔵中やその加工・調理中、最終製品の貯蔵・流通中にヒスタミン生成菌が増殖することによって蓄積されるので、アレルギー様食中毒防除の基本は微生物性食中毒としての対応を行うことである。 |
|
 |
|
本稿で触れなかった事項や文献は次の拙稿を参照ください。
(1)藤井建夫: ヒスタミン生成菌,『HACCPと水産食品』(藤井・山中編), p.59-74, 恒星社厚生閣 (2000).
(2)藤井建夫:アレルギー様食中毒, 日本食品微生物学会雑誌, 23, 61-71 (2006).
(3)藤井建夫:細菌性食中毒としてのアレルギー様食中毒, 食品衛生学雑誌, 47,J343-J348 (2006). |
|
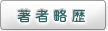 |
|
 |
|
藤井 建夫(ふじい たてお)
1975年京都大学大学院農学研究科博士課程修了,水産庁東海区水産研究所微生物研究室長を経て, 1986年東京水産大学食品生産学科助教授, 1993年同教授, 2003年東京海洋大学教授(大学統合により名称変更), 2007年 東京海洋大学名誉教授, 山脇学園短期大学教授, 2009年 東京家政大学特任教授, 現在に至る. 農学博士. |
|
|
| 【委員等】 |
日本食品衛生学会(前会長)、日本食品微生物学会(理事)、日本伝統食品研究会(会長)、内閣府食品安全委員会専門委員、ほか. |
|
| 【専門】 |
一貫して食品微生物の教育・研究に従事. とくに食中毒・腐敗菌など有害微生物制御および水産発酵食品の微生物機能に関する研究. |
|
| 【主な著書】 |
「微生物制御の基礎知識-食品衛生のための90のポイント」(中央法規出版, 1997)
「魚の発酵食品」(成山堂書店, 2000)
「食品微生物II -食品の保全と微生物」(幸書房, 2001)
「塩辛・くさや・かつお節(増補版)」(恒星社厚生閣, 2001)
「加工食品と微生物−現場における食品衛生」(中央法規出版, 2007)
「食品衛生学第二版」(恒星社厚生閣, 2007)
「日本の伝統食品事典」(朝倉書店, 2007)
「食品微生物標準問題集(改訂)」(幸書房, 2008)
「食品安全の事典」(朝倉書店, 2009)ほか. |
|
|
|