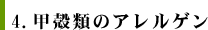 |
|
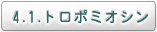 |
|
丂峛妅椶偺傾儗儖僎儞偵娭偡傞尋媶偼1980擭戙弶傔偐傜墷暷偱峴傢傟丄1993擭偵側偭偰傛偆傗偔丄晹暘傾儈僲巁攝楍暘愅寢壥偐傜僀儞僪僄價偺庡梫傾儗儖僎儞偼僩儘億儈僆僔儞偱偁傞偙偲偑徹柧偝傟偨丅偦偺屻丄奺庬僄價椶傗僇僯椶偺庡梫傾儗儖僎儞偼嫟捠偟偰僩儘億儈僆僔儞偱偁傞偙偲偑暘巕儗儀儖偱憡師偄偱柧傜偐偵偝傟偨丅僩儘億儈僆僔儞偼嬝尨慇堐僞儞僷僋幙乮墫梟惈僞儞僷僋幙乯偺堦庬偱丄傾僋僠儞丄僩儘億僯儞偲偲傕偵嵶偄嬝尨慇堐傪峔惉偟偰嬝廂弅偺挷愡傪扴偭偰偄傞丅傎傏慡挿偵傢偨偭偰α-傊儕僢僋僗峔憿傪偲偭偰偄傞暘巕検栺3.5枩偺僒僽儐僯僢僩2杮偑偍屳偄偵傛偠傟偁偭偰1暘巕偲側偭偰偄傞丅嫑椶偺庡梫傾儗儖僎儞偱偁傞僷儖僽傾儖僽儈儞偲摨條偵僩儘億儈僆僔儞傕壛擬偵旕忢偵埨掕側僞儞僷僋幙偱丄傾儗儖僎儞偵側傝傗偡偄偲偄偊傞丅
丂偙傟傑偱墷暷偱尋媶偺懳徾偲偟偰庢傝忋偘傜傟偨僄價椶丄僇僯椶偼偡傋偰怴擃峧垷峧廫媟栚偵懏偡傞峛妅椶偱偁傞丅昞2偵帵偡傛偆偵丄傢偑崙偺傾儗儖僊乕昞帵惂搙偺懳徾偲側偭偰偄傞乽偊傃乿乽偐偵乿傕偄偢傟傕怴擃峧垷峧廫媟栚偺拠娫偱丄乽偊傃乿偼斅橐垷栚偲書棏垷栚偺僐僄價壓栚丄僀僙僄價壓栚偍傛傃僓儕僈僯壓栚傪丄乽偐偵乿偼書棏垷栚偺堎旜壓栚乮儎僪僇儕椶乯偲抁旜壓栚乮僇僯椶乯傪巜偟偰偄傞丅昅幰傜偼廫媟栚偺僂僔僄價乮僽儔僢僋僞僀僈乕乯丄僋儖儅僄價丄儂僢僐僋傾僇僄價乮傾儅僄價乯丄僞儔僶僈僯丄僘儚僀僈僯丄働僈僯偩偗偱側偔丄僄價偺戙懼昳偲偟偰怘梡偵偝傟傞偙偲偑偁傞怴擃峧垷峧僆僉傾儈栚偺僫儞僉儑僋僆儈傾儈丄堦晹抧堟偱捒枴偲偟偰怘傋傜傟偰偄傞枲媟垷峧桳暱栚偺僇儊僲僥偍傛傃柍暱栚偺儈僱僼僕僣儃丄偝傜偵庻巌偹偨偲偟偰棙梡偝傟偰偄傞僩僎僄價垷峧岥媟栚偺僔儍僐偵偮偄偰傕専摙傪壛偊丄偡傋偰偺庬椶偱庡梫傾儗儖僎儞偼僩儘億儈僆僔儞偱偁傞偙偲傪妋擣偟偰偄傞丅廫媟栚埲奜偺峛妅椶偼傾儗儖僊乕昞帵偺懳徾奜偱偁傞偑丄傾儗儖僊乕偺揰偱偼乽偊傃乿乽偐偵乿偲摨摍偱偁傞偲峫偊傜傟傞偺偱拲堄偑昁梫偱偁傞丅偲偔偵僇儊僲僥傗僼僕僣儃偵偮偄偰偼丄峛妅椶偱偁傞偙偲傪棟夝偟偰偄側偄恖傕懡偄偺偱丄抦幆偺晛媦傕廳梫偱偁傠偆丅 |
|
| 昞2. 庡側怘梡峛妅椶偺暘椶 |
|
丂奺庬峛妅椶僩儘億儈僆僔儞偺傾儈僲巁攝楍傪恾6偵丄攝楍憡摨惈傪昞3偵帵偡丅奺庬峛妅椶偺僩儘億儈僆僔儞偼偍屳偄偵峈尨岎嵎惈傪桳偡傞偑丄偙偺偙偲偼傾儈僲巁攝楍偺椶帡惈偍傛傃IgE僄僺僩乕僾偺曐懚惈偺崅偝偐傜梕堈偵愢柧偱偒傞丅傑偢廫媟栚偺僩儘億儈僆僔儞偵拲栚偡傞偲丄傾儈僲巁攝楍偺憡摨惈偼偍偍傓偹90亾埲忋偲旕忢偵崅偄丅嬝擏偼廂弅懍搙偺嵎堎偵傛傝fast muscle乮懍嬝乯偲slow muscle乮抶嬝乯偵暘椶偝傟丄僩儘億儈僆僔儞偵傕fast muscle桼棃偺fast type偲slow muscle桼棃偺slow type偑偁傞丅slow type偼偝傜偵丄slow-tonic type偲slow-twitch type偵傢偗傜傟傞丅奺type偺僩儘億儈僆僔儞偺傾儈僲巁攝楍傪斾妑偡傞偲丄fast type偲slow type偺僩儘億儈僆僔儞偺傾儈僲巁攝楍偺娫偱偼椞堟39-79偵廤拞偟偰曄堎偑傒傜傟丄偝傜偵slow-tonic type偲懠偺2偮偺type偺娫偱偼C枛抂椞堟乮269-284乯偵傕懡彮偺曄堎偑傒傜傟傞丅嫽枴怺偄偙偲偵丄僄價椶僩儘億儈僆僔儞偼椺奜側偔fast type偱丄僇僯椶僩儘億儈僆僔儞偼僞儔僶僈僯摲擏偵slow-tonic type偲堦弿偵専弌偝傟偨fast type傪彍偔偲偡傋偰slow type偱偁傞丅
丂廫媟栚埲奜偺峛妅椶偺応崌丄枲媟垷峧偵懏偡傞儈僱僼僕僣儃偺僩儘億儈僆僔儞偩偗偼懠偺峛妅椶僩儘億儈僆僔儞偲曄堎偑旕忢偵戝偒偄乮攝楍憡摨惈偼60亾枹枮乯丅僼僕僣儃椶偼19悽婭弶傔傑偱偼擃懱摦暔偵暘椶偝傟偰偄偨偙偲偲娭學偟偰偄傞偺偐傕偟傟側偄偑丄儈僱僼僕僣儃僩儘億儈僆僔儞偺傾儈僲巁攝楍偼擃懱摦暔偺儅儖僆僗僟儗僈僀壢擇枃奓乮傾僒儕側偳乯偺僩儘億儈僆僔儞偵旕忢偵嬤偄乮攝楍憡摨惈偼95%埲忋乯丅廫媟栚偲摨偠怴擃峧垷峧偵暘椶偝傟偰偄傞僆僉傾儈椶偺僩儘億儈僆僔儞偼13-42偺椞堟傪偼偠傔偲偟偰偐側傝偺曄堎傪帵偟丄廫媟栚僩儘億儈僆僔儞偲偺攝楍憡摨惈偼82-92%偲傗傗掅偄丅堦曽丄僩僎僄價垷峧偵傢偗傜傟偰偄傞僔儍僐偺僩儘億儈僆僔儞偼柧傜偐偵廫媟栚偺fast type偵懏偟丄廫媟栚偺fast type偺僩儘億儈僆僔儞偲栺97亾偲偄偆崅偄攝楍憡摨惈傪帵偡丅
丂峛妅椶僩儘億儈僆僔儞偺峈尨岎嵎惈傪丄僽儔僂儞僔儏儕儞僾偺僩儘億儈僆僔儞偵懳偟偰採彞偝傟偰偄傞8偮偺IgE僄僺僩乕僾椞堟乮43-55丄88-101丄137-141丄144-151丄187-197丄249-259丄266-273丄273-281乯偺傾儈僲巁攝楍偺揰偐傜偝傜偵徻偟偔傒偰傒傛偆丅8偮偺偆偪5偮偺IgE僄僺僩乕僾椞堟乮88-101丄137-141丄144-151丄187-197丄249-259乯偼廫媟栚偲僔儍僐偺僩儘億儈僆僔儞偱偼姰慡偵丆僆僉傾儈椶偺僩儘億儈僆僔儞偱傕傎傏姰慡偵曐懚偝傟偰偍傝丄偍屳偄偺峈尨岎嵎惈傪暘巕儗儀儖偱棤晅偗偰偄傞偲偄偊傛偆丅曐懚惈偑掅偄巆傝3偮偺IgE僄僺僩乕僾椞堟乮43-55丄266-273丄273-281乯偼丄fast type偲slow type偺娫偱丄偁傞偄偼slow-tonic type偩偗偱曄堎偑挊偟偄椞堟偵憡摉偟偰偄傞丅椪彴尰応偱偼丄僄價乮fast type 僩儘億儈僆僔儞傪娷傓乯偵懳偟偰偩偗傾儗儖僊乕傪帵偡姵幰丄偁傞偄偼僇僯乮slow type 僩儘億儈僆僔儞傪娷傓乯偵懳偟偰偩偗傾儗儖僊乕傪帵偡姵幰偺懚嵼偑抦傜傟偰偄傞丅偦偺偨傔丄傾儗儖僊乕昞帵惂搙偱偼丄乽偊傃乿偲乽偐偵乿傪暿屄偵昞帵偡傞傛偆偵側偭偰偄傞丅僄價偩偗傑偨偼僇僯偩偗偵傾儗儖僊乕傪帵偡姵幰偺懚嵼偵偮偄偰偼崱偺偲偙傠暘巕儗儀儖偱愢柧偱偒偰偄側偄偑丄偙傟傜姵幰偼fast type偲slow type偺僩儘億儈僆僔儞偺娫偱曄堎偑挊偟偄椞堟傪摿偵嫮偔擣幆偟偰偄傞壜擻惈偑偁傞丅 |
|
| 恾6. 峛妅椶僩儘億儈僆僔儞偺傾儈僲巁攝楍 |
|
| 昞3. 峛妅椶僩儘億儈僆僔儞偺傾儈僲巁攝楍憡摨惈乮亾乯 |
|
| 丂僩儘億儈僆僔儞偼峛妅椶偺庡梫傾儗儖僎儞偱偁傞偙偲傪弎傋偰偒偨偑丄幚偼僩儘億儈僆僔儞偼柍愐捙摦暔偺僷儞傾儗儖僎儞乮pan-allergen丄暆峀偄岎嵎惈傪桳偡傞傾儗儖僎儞乯偲峫偊傜傟偰偄傞丅屻弎偡傞傛偆偵擃懱摦暔偺庡梫傾儗儖僎儞傕僩儘億儈僆僔儞偱偁傞偙偲偑傢偐偭偰偍傝丄峛妅椶僩儘億儈僆僔儞偲偺峈尨岎嵎惈偑妋擣偝傟偰偄傞丅傑偨丄怘暔傾儗儖僎儞偱偼側偄偑丄峛妅椶偲摨偠愡懌摦暔偵暘椶偝傟傞僟僯椶傗僑僉僽儕椶偺傾儗儖僎儞偺堦偮偲偟偰傕僩儘億儈僆僔儞偑摨掕偝傟丄偄偢傟偺僩儘億儈僆僔儞傕峛妅椶僩儘億儈僆僔儞偲峈尨岎嵎惈傪帵偡偙偲偑擣傔傜傟偰偄傞丅 |
|
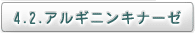 |
|
| 丂僽儔僢僋僞僀僈乕偍傛傃僔儘傾僔僄價乮僶僫儊僀僄價乯偺儅僀僫乕傾儗儖僎儞偲偟偰丄暘巕検4枩偺傾儖僊僯儞僉僫乕僛偑摨掕偝傟偰偄傞丅傾儖僊僯儞僉僫乕僛偼傾儖僊僯儞偲ATP偐傜傾儖僊僯儞儕儞巁傪惗惉偡傞丄偁傞偄偼傾儖僊僯儞儕儞巁偺扙儕儞巁壔傪怗攠偡傞峺慺偱偁傞丅傾儖僊僯儞儕儞巁偼柍愐捙摦暔偵偍偗傞廳梫側儂僗僼傽乕僎儞乮僄僱儖僊乕偵昁梫側ATP偺挋憼暔幙乯偱偁傞偺偱丄傾儖僊僯儞僉僫乕僛偼摉慠偺偙偲側偑傜柍愐捙摦暔偵峀偔暘晍偟偰偄傞丅傾儖僊僯儞僉僫乕僛偼丄堦晹崺拵椶乮僲僔儊儅僟儔儊僀僈丄僑僉僽儕丄僇僀僐乯偺傾儗儖僎儞偲偟偰傕摨掕偝傟偰偍傝丄峛妅椶偺傾儖僊僯儞僉僫乕僛偲偺峈尨岎嵎惈傕擣傔傜傟偰偄傞丅 |
|
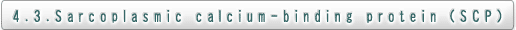 |
|
| 丂昅幰傜偼丄僽儔僢僋僞僀僈乕偺傾儖僊僯儞僉僫乕僛傪惛惢偟偰偄傞夁掱偱傾儖僊僯儞僉僫乕僛偲偼堎側傞暘巕検2枩偺怴婯傾儗儖僎儞傪尒偄偩偟丄晹暘傾儈僲巁攝楍夝愅偵傛傝sarcoplasmic calcium-binding protein乮SCP乯偲摨掕偟偨丅偦偺屻丄僶僫儊僀僄價偺SCP傕傾儗儖僎儞偱偁傞偙偲偑曬崘偝傟偰偄傞丅SCP偼柍愐捙摦暔摿桳偺Ca2+寢崌惈僞儞僷僋幙偱丄Ca2+偺娚徴傗嬝擏偺抩娚偺夁掱偵娭梌偡傞僞儞僷僋幙偲偄傢傟偰偄傞丅SCP偼婡擻揑偵偼丄嫑椶偺庡梫傾儗儖僎儞偲偟偰摨掕偝傟偰偄傞愐捙摦暔摿桳偺Ca2+寢崌惈僞儞僷僋幙偱偁傞僷儖僽傾儖僽儈儞偵憡摉偡傞偲峫偊傜傟偰偄傞丅僷儖僽傾儖僽儈儞摨條偵Ca2+彍嫀偵傛傝IgE斀墳惈偼偐側傝掅壓偡傞偙偲傪擣傔偰偄傞偺偱丄IgE僄僺僩乕僾偲偟偰偼棫懱峔憿偑廳梫偱偁傞偲巚傢傟傞丅側偍丄僀儉僲僽儘僢僥傿儞僌偱偼丄姵幰寣拞IgE偼僄價椶乮偲偔偵僋儖儅僄價壢僄價椶乯偺SCP偲嫮偔斀墳偡傞偑僇僯椶偺SCP偲偼傎偲傫偳斀墳偟側偄丅僇僯椶偼SCP娷検偑掅偄壜擻惈傕偁傞偑丄偄偢傟偵偟偰傕SCP偼僄價椶偵懳偟偰偺傒傾儗儖僊乕傪帵偡姵幰偺愢柧偵側傞偐傕偟傟側偄丅 |
|
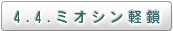 |
|
| 丂嵟嬤丄僶僫儊僀僄價偺拪弌塼拞偵暘巕検2枩偺怴婯傾儗儖僎儞偑専弌偝傟丄2師尦揹婥塲摦屻偺僎儖撪徚壔暔偺MALDI/MS暘愅偵傛傝儈僆僔儞寉嵔偱偁傞偙偲偑徹柧偝傟偨丅姵幰偺敿悢埲忋偵擣幆偝傟傞偺偱丄庡梫傾儗儖僎儞偲峫偊傜傟偰偄傞丅僶僫儊僀僄價埲奜偺峛妅椶傗偦偺懠偺摦暔桼棃偺儈僆僔儞寉嵔偺傾儗儖僎儞惈偼晄柧偱偁傞丅儈僆僔儞寉嵔偼嬝廂弅偵娭梌偟偰偄傞儈僆僔儞乮暘巕検栺22枩偺2杮偺廳嵔偲丄奺廳嵔偵2杮偢偮偺寉嵔偺崌寁6杮偺億儕儁僾僠僪偱峔惉偝傟偰偄傞乯傪峔惉偟偰偄傞僞儞僷僋幙偱偁傞丅儈僆僔儞寉嵔偼Ca2+寢崌惈僞儞僷僋幙偱偁傞偑丄Ca2+偲IgE斀墳惈偲偺娭楢偼晄柧偱偁傞丅 |
|