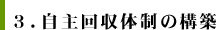 |
|
| 異物クレームが発生した際に事業者は、発生し得る健康被害の程度や事故拡大の可能性についての判断を行い、必要であれば、あらゆる手段を使って顧客(消費者含め)への問題発生の連絡、告知を行い、問題が発生し得る範囲の製品の飲食を防止する措置(製品回収も含め)を実施する。 |
|
自主回収は、弊財団が在る三重県では、「三重県食の安全・安心確保に関する条例」にて、食品による健康への悪影響を未然に防止するという観点から、県民への周知が必要な情報を県が把握し、その内容を正確かつ迅速に提供することを目的として、平成21年7月1日より自主回収の報告の義務規定が施行されている(参照:三重県ホームページ アドレス
http://www.pref.mie.jp/SHOKUA/HP/housin/kaisyu.pdf)。
条例による自主回収の報告義務は、三重県以外にも施行されており、例えば東京都食品安全条例に基づく「自主回収報告制度」(平成16年11月1日施行)のように都道府県において様々に取り組みされている。
事業者が問題発生時に自主回収を必要と判断した場合、必要となる様々な情報を正確に入手することで迅速かつ適切な回収対応の実施が可能となる。 |
|
| 迅速かつ適切な回収対応については、国際的にはCodex委員会が示した「食品衛生の一般原則」に「市場から迅速に回収できる手順を保証すること」とされており、国内では「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)について(食安発第227012号)」において、「問題となった製品を迅速かつ適切に回収できるよう、回収に係る責任体制、具体的な回収の方法、当該施設の所在する地域を管轄する保健所等への報告等の手順を定めること」とされている。また、この内容は、三重県においては、食品衛生の措置基準等に関する条例(三重県条例第8号)にも規定されている。 |
|
| このように事業者は問題が発生した場合に、誰がどのような情報を入手し、誰がどのような基準にて回収等の判断を行うのか、また、必要な利害関係者(関係行政機関、顧客、消費者等)への対応を誰がどのように行うか、問題となった製品等をどのように取り扱うかなどを想定した手順(書)を、普段から作成し、実際にその通りに対応が可能であるか確認を行っておくことが必要である。 |
|
顧客や消費者から寄せられる異物等のクレーム情報も確実にこの問題発生の一つに該当し、事業者はその情報に対する判断、対応が必要とされる。 |
|