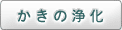 |
|
�@��L�������E�������̏V�X�e�����J�����A�咰�ۂ̂��Ȃ����ۂ�������邱�ƂɐS���𒍂����̂͂��̂��߂ł���B�咰�ۂ͓����̒������Z���Ƃ��闤���R���̋ۂł���B�����ɑ咰�ۂ����Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�ԗ���`�t�X�ȂǑ��̏�����n�`���a�̌����ۂ����Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă���B�C�������O���ŎE�ۂ��A�n���_�f�������Ȃ�V�����[�����ŏ����S�ʂɋϓ��ɊC������������B�����ł́A��������ꂽ�������P�i�����Ђ��A��藬���̐������ɂ���Ă������o�������Ȃǂ𐅑����ɗ����A�����ꂩ��T�C�t�H�������ʼn��D���O�ɔr�o����B���������e����S������ւ��邽�߂ɂP�W�`20���Ԃ��K�v�ł��邱�Ƃ������ɂ���č������E����͌��o�����B���̏������P�X�T�T�N�����o�^�ɂȂ������̂ł���B
�@�����A�悭�l���Ă݂�Ə͂����݂̈⒰�̒������ꂢ�ɂ��邱�Ƃ����ł͂Ȃ��B���������B�̍זE���Ɏ�荞��ł��܂����ۂ�E�C���X���A�������g�������̕a�����������������Đl�ւ̊����͂��Ȃ����Ă��܂����A���͖��������Ƃ��čזE�O�E�̊O�ɔr�����Ă��܂����Ƃ��Ӗ����Ă���B�]���āA�m���ɏ���A���Ȃ킿���Ԃ����炷�邱�Ƃ������̈��S�ɂ͌������Ȃ��B����܂ōۂ��w�W�Ƃ��������͎O�d���ł����{���A�P�W���Ԉȏ�ōۂ����o����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��m�F���Ă����B���݂ł�HACCP�����̓����ŏ͊m���Ɏ��{����Ă���B�������ߋ��ɂ́A�����������A����n�s��̌����ő咰�ۂ��ʍې����K�i��Ɉᔽ���邱�Ƃ��悭�������B���̌����́A���O���E�ۃ����v�̕s���A�����ɂ����̓���߂��i���ʕs���j�A���Ԃ̕s���ȂǗl�X�Ȍ������������B�������E���J�����������̏Z�p�́A�㔭�̂����{�B�Ǝ҂ɂ͂Ȃ��Ȃ����m�ɂ͓`����Ă����Ȃ������̂ł���B
�@�P�X�W�W�N4���A������2�x�ڂ̖{�������q���S���ƂȂ����B��y�̓w�͂ɂ���Ă��̔N���炩���̉q����R���N�v�悪�\�Z������Ă����B�������{�i�I�ɂ����̉q����ɌW��̂͂��̎�����ł���B�ɐ��ی����H�i�q���@���ǂƎu���ی����ɂ���āA�S�Ă̂����Ǝ҂̎{�݂��ʂɍׂ����������A�̖��_�����ׂĐo���B�����ėl�X�ȏ{�݂ɑΉ�������{�I�ȏZ�p�����o�����߂̏�����3�N�ԑ������̂ł���B�������E���J�������Z�p����Ԃ̐^�̈Ӗ������̂����Ǝ҂ɓ`���ɂ́A�ی����̒����N���ɂ킽�錵�����s���w����K�v�Ƃ����̂ł���B�g�O�d���̂����{�B�����W���������̎p�͕ی����̌��тł���B�h�Ƃ́A�����̒m�l�̐��Y�s���E���̌��t�ł��� |
| �}4 ������ |
| �݂��J�L���S���V�X�e����4��J�L�t�H�[�����u���Ҏ��� |
���R�[�q�[�u���C�N
�@�����݂̈⒆���B�̑g�D�ؕЂ��������Ŋώ@����ƁA���̂����ł̓v�����N�g���Ȃǂ̉a�����������邵�A������ǂɂ͕���������B�������A�ς݂̂����ł͂����͂قƂ�nj����Ȃ��B�����������Ƀ��������i���ĐH�ׂ����̂��̂������肵�����������́A���̂����ł��낤�B�������A�t���C�ɂ���Ƃ����̕������キ�ĕ�����Ȃ�����������̂ŁA�����t���C�͖��̂����Ɍ���B�����͂��̂悤�ɔ[�����Ă����������y����ł���B
�@�������A����Ƃ����͊ԈႢ�Ȃ����������Ă��܂��B���Ă����������������������E����͂ǂ̂悤�ɐ��Y�����̂��A���̘b�͕ʂ̋@��ɏ��낤�B
�@�������E����́A�P�X�W�P�N�A�u�����������Ǝ��Ɖ��ɕ������A�I��p�ł̖��ۃJ�L�{�B�v�̌��тŃT���g���[�������c����n�敶���܂���܂���Ă���B |
| �T���g���[�������c�̃z�[���y�[�W�����N |
�@�����������X�ɔ��������H�ׂ�ɂ́A���������|�k�i�������j�A���C����菃�ċ�����ƈꏏ�Ɋy���ނ̂��ō��ɑ����������Ǝv���Ă���B�����ɂ̓������������̂��B����Ȃ�č��Y��荑�Y�Ə����̓������̖�A�����B5�N�ڂł悤�₭�����������n���邱�Ƃ��ł����B�������A�������̍��肪�������Ă����̕����ɏ����Ă��܂����s�B�������^����H�ׂ邽�߂ɏd�Ă���|�k�Ŏ����Ă݂���A�_���͒��悭����͍T���ڂł҂�����ł������B���ċ���̓R�~�b�N���Œm���Ď����Ă݂��B�����̊C���ōA�����炪�炵�����ɂ́A���Ď��͗D��������悤�ɍA�����Ă����B����������B |