|
クロラムフェニコール試験法について
一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC
第二理化学検査室 1.はじめにクロラムフェニコールは、広域の抗菌スペクトルを持つ抗生物質であり、動物用医薬品として家畜の病気の予防や治療のために使用される。クロラムフェニコールは遺伝毒性を有すると考えられており、発がん性を有する可能性が否定できないことから、ポジティブリスト制度導入の際に、その基準値は「不検出」として設定された。不検出基準は、その物質の発がん性や毒性により閾値が設定できないことから、「食品に含有してはならない」とされている。 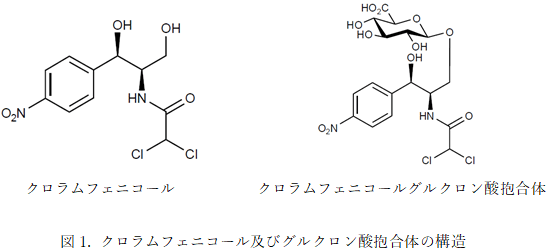 2.クロラムフェニコール試験法の概要クロラムフェニコール試験法のフローチャートを図2に示す。均一化した試料より、クロラムフェニコール及びグルクロン酸抱合体をメタノールにて抽出する。その後、緩衝液存在下でβ-グルクロニダーゼによりグルクロン酸抱合体を加水分解し、クロラムフェニコールへと変換する。加水分解後、クロラムフェニコールを酢酸エチルへ転溶し、ジビニルベンゼン-N-ビニルピロリドン共重合体カラムにより精製する。測定機器は液体クロマトグラフ-質量分析計(LC-MS/MS)を用いる。検出限界はクロラムフェニコールとして0.0005 ppm(ローヤルゼリーについては0.005 ppm)である。 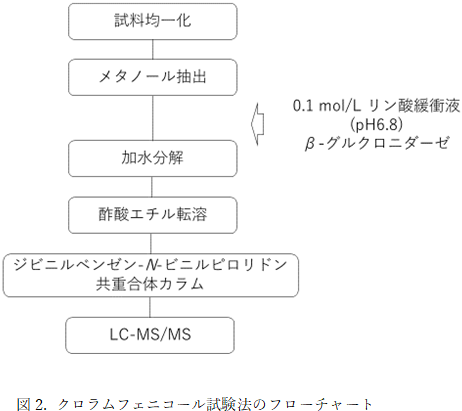 3.試験法の注意点クロラムフェニコール試験法の改正と同時に、試験実施に際しての留意事項が通知されており、特に重要な点はβ-グルクロニダーゼの取扱いである。β-グルクロニダーゼは、酵素由来の妨害ピークが認められる場合があるため、酵素は事前に酵素由来の妨害ピークが定量に影響を及ぼさないことを確認する必要がある。また、試験法に記載された反応条件で既知濃度のグルクロン酸抱合体を加水分解し、加水分解が十分に行われていることを事前に確認することが重要である。加水分解反応の設定温度および反応時間を変更する際には、事前に十分な検討を行わなければならない。 参考資料【1】生食基発0223第3号「食品、添加物等の規格基準に定められた食品に残留する農薬等の試験法における留意事項について」平成29年2月23日 【2】「平成26年度 食品・添加物等規格基準に関する試験検査等に関する報告書 クロラムフェニコール試験法(畜水産物)」 【3】「食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)」第1 食品の部 A 食品一般の成分規格の5の(9)クロラムフェニコール試験法
【4】食品分析開発センターSUNATEC メールマガジン「動物用医薬品の規制と検査方法」 【5】薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会議事録 2014年7月31日 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |
| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |

