|
倫理が厳しく問われている「機能性表示食品」制度
科学ジャーナリスト 松永 和紀
一般社団法人 Food Communication Compass 運営 2016年1月から開かれていた「機能性表示食品制度における機能性関与成分の取扱い等に関する検討会」(以下、検討会と呼ぶ)が11月末、第11回の会合をもって終了し、12月末に報告書がまとめられた1)。 審議を傍聴して印象的だったのは、学識者や消費者団体から選出された委員などが事業者の姿勢を追及し、とくに、消費者団体の委員が事業者の「倫理」を厳しく求めたことだ。その結果、報告書は、「本制度の適切な運用に向けた事業者の責務」という項目で、次のように記している。 本制度は、企業等の責任において届け出る制度であり、消費者の信頼があって初めて成り立ち得る制度である。平成27年度に実施した「機能性表示食品に係る機能性関与成分に関する検証事業」における買い上げ調査の結果、機能性表示食品の品質管理上の課題が見られた。届出者等には、届出前の届出資料の確認、品質管理、事後的な機能性及び安全性に関する科学的根拠の確認など届出者等自らが倫理観を持って本制度の信頼の確保のために努力することが求められる。 こうした報告書で「倫理観を持て」と書かれるのは異例のことだろう。報告書は、これまで届け出された製品に多くの問題があることを踏まえ、事業者が届け出すべき資料など、現状よりも高度で厳密な内容とすることを求めている。 ところが、同年12月に開催された規制改革推進会議医療・介護・保育ワーキング・グループの会合では、機能性表示食品の届出に係る改善策だけが話し合われた。意見を求められたのは事業者側のみで、消費者団体からの意見聴取はなく、事業者が一方的に制度のメリットを述べ、推進策を提言した2)。 この大きな乖離が、機能性表示食品制度の現状を象徴しているように思えてならない。産業推進にひた走る事業者や国と、学識者や消費者団体などの懸念が折り合う地点は見えない。制度はどこへ向かうのか。2016年2月号の「機能性表示食品、消費者はどう見るか?!」3)に引き続き、検討会や規制改革推進会議の動きを踏まえ、制度の現状と今後を考えてみたい。 機能性表示食品の現状機能性表示食品制度は2015年4月にスタートした。機能性表示を事業者の責任において行い、国の審査はない。その代わりに、企業は安全性や機能性、品質保証などについての情報を消費者庁に届け出し、消費者庁のウェブサイトで公開される4)。 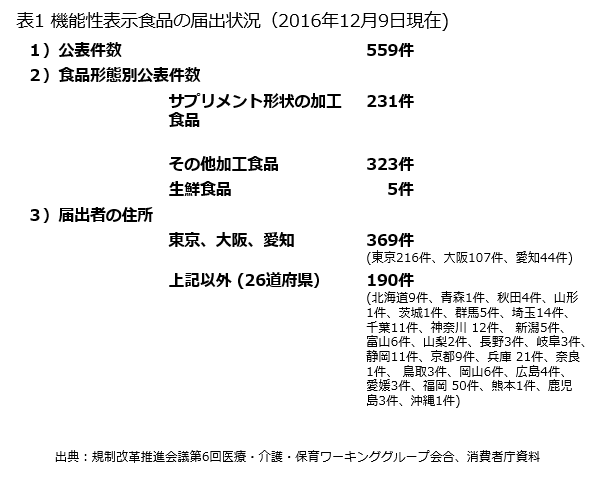 公益社団法人日本通信販売協会サプリメント部会が、規制改革推進会議 医療・介護・保育ワーキング・グループ第6回会合に提出した資料によれば、それ以前には年間売上額が8億円だった製品が、機能性表示食品になり1年で4.3倍の売上額に伸びたという2)。 一方で、株式会社インテージの健康食品・サプリメント市場調査によれば、日本の健康食品・サプリメントの2016年推定市場規模は1兆5,716億円で、対前年0.4%の微減、利用者数は5,784万人で、対前年0.5%の微増に止まっている5)。機能性表示食品制度は、事業者が期待したような“起爆剤”とはなっていない。事業者の中からは「結局、いわゆる健康食品から機能性表示食品に移行しただけで、市場規模はそのまま。機能性表示食品として届け出するには手間も費用もかかり、広告宣伝費をかけた製品が売り上げを伸ばしているのみだ。メリットがない。」という声も聞かれる。 消費者からの厳しい批判2016年1月に設置された検討会の主な議題は、「食事摂取基準が策定されている栄養成分」と「機能性関与成分が明確でない食品」を、制度の対象とするかどうかだった。制度創設の枠組みを決めた「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」で先送りされた議題を取り上げるもので、対象拡大を狙う業界の意向が強かった。 とくに厳しい言葉を連ね「事業者に倫理を求める」と何度か口にしたのは、全国消費者団体連絡会(全国消団連)事務局長の河野康子氏だ。全国消団連は同年9月、消費者庁長官や消費者委員会委員長、国民生活センター理事長などに対しても、意見書を提出している6)。 そこで触れられているのは、2015年度に消費者庁が行った二つの検証事業の結果だ。消費者庁は、研究レビューに基づき機能性を表示している製品の届出書類をチェックし、不備のある研究レビューに基づき届出販売されている製品が多いことを示した4)。 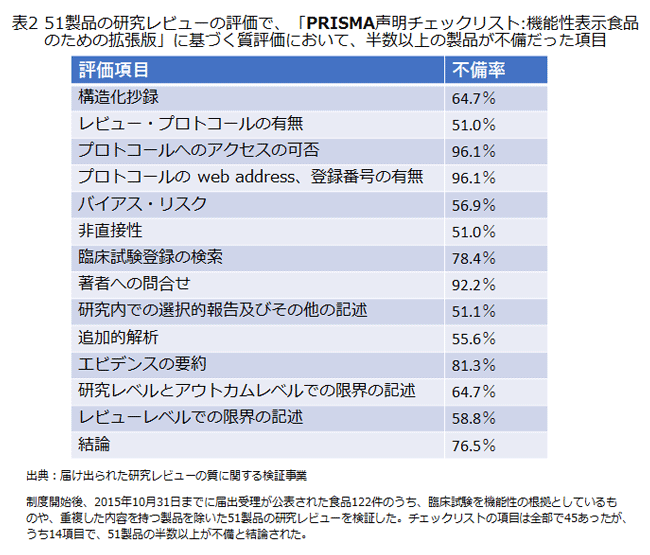 また、同年度の前半に届出された146製品を精査し、提出された分析法(非公開)では定量できない製品が、調べたものの4割近くに上ることを明らかにした。さらに、そのうちの17製品について買い上げ調査を実施し、機能性関与成分の表示含有量を下回ったり過剰に含まれていたりする製品があることや、同一製品であるにもかかわらず、ロット間で大きなばらつきがあることを突き止め、品質保証に大きな問題があることを明らかにした。 これらの結果に基づき、全国消団連の意見書は事業者への監視指導の強化や制度の見直しを国へ求めている。さらに、サプリメントの数年の販売歴を「食経験」として扱ったり、機能性の科学的根拠が弱い製品でも届出受理されているなどの問題点を述べている。私が2016年2月号のメールマガジン(http://www.mac.or.jp/mail/160201/02.shtml)で指摘したのと同様の内容だ。 学識者が指摘する企業の倫理学識者の事業者への不信感も強い。佐々木敏・東京大学大学院教授は、検討会第8回会合で「消費者教育」の材料として、研究における利益相反問題を指摘した。 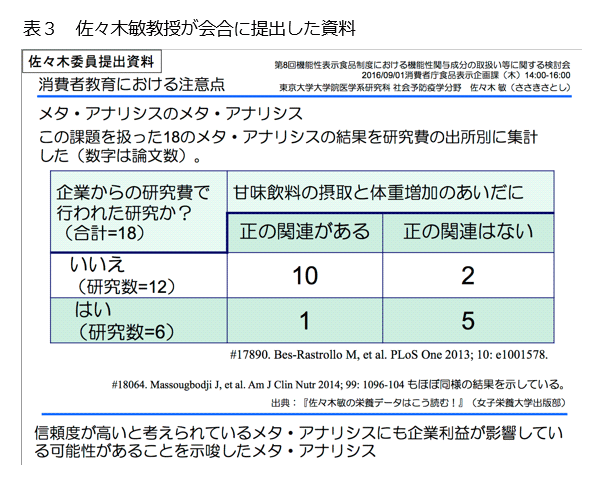 実は、規制は強化される方向制度の対象拡大を検討したい事業者と、その前に制度の不備を改善したい学識者や消費者……。議論はたびたびすれ違ったが、報告書はなんとかまとまった。一つ目の議題である「食事摂取基準の策定されている栄養成分」については、糖質・糖類、ビタミン・ミネラルに分けられ、検討された。糖質・糖類については、主としてエネルギー源とされるぶどう糖やでんぷんなどを除き、対象とすることが決まった。一方、ビタミン・ミネラルについては、過剰摂取の懸念や健康・栄養政策との整合性との問題から、対象としないと結論づけ、栄養機能食品制度において別途検討すべき、とした。 二つ目の議題の「機能性関与成分が明確でない食品」の取扱いについては、機能性の科学的根拠の一部を説明できる特定成分は判明しているものの、その成分のみでは機能性の全てを説明することはできない「エキス及び分泌物」(エキス等)を、新たに制度対象にすることを答申した。 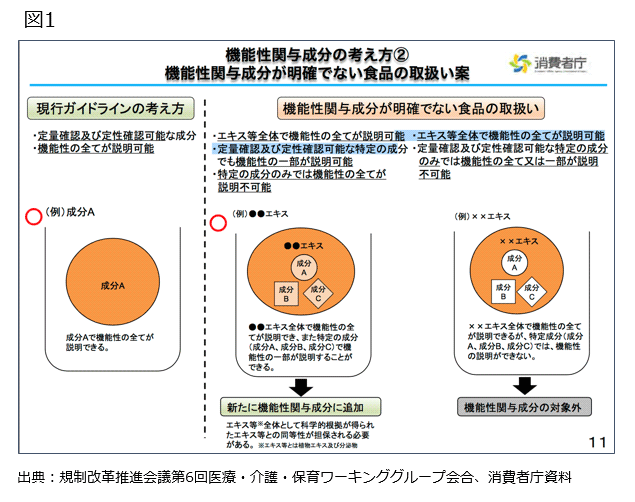 一見、制度の拡大に見えるが、報告書をよく読むと、そう簡単な話ではない。 また、この考え方を既に届出されている製品にも適用し、崩壊性試験、溶出試験なども求めて品質保証のレベルを上げて行くことが明記された。 報告書はこれに加え、消費者庁における人員体制を強化することや届出データベースの改善、健康被害情報の収集・評価に力を入れること、消費者教育を強化することなどを求めている。また、これまで非公開とされていた機能性関与成分の定性確認及び定量確認の分析方法は、原則公開することとしている。そのうえで、冒頭に紹介した「事業者の責務」で事業者自身が倫理観を持ち努力すべし、と強調している。 読めば読むほど、報告書は事業者への視線が厳しく、改善を求める内容だ。15年度の検証事業については、2016年9月に開かれた消費者委員会の第233回本会議でも取り上げられ、複数の委員が「科学的根拠が不十分なまま、不適切な品質管理によって製造された商品が、健康に関与する成分としての効果、そして、安全性が担保されているとして、既に販売されている」などと問題点を指摘した7)。 消費者委員会は「食品表示法違反ではないか」と消費者庁を責めるが、同庁は書類が揃っていることを確認し届出を受理しただけで、製品の中身や書類の内容を審査したわけではない。検証事業で、製品の不備が明らかとなっても、法律違反に問うかどうかは、さらに厳密な判断が必要。簡単に線引きをして、「ここから先はだめ、ここから先はいい」とは言いづらい。 規制改革推進会議ワーキング・グループは…ところが、規制改革推進会議になると検討の中身が一変する。もともと、機能性表示食品制度は、規制改革推進会議の前身である規制改革会議でプランが出され、創設されたもので、産業振興の色合いの強い制度である。 事業者2団体は問題点として、書類を消費者庁に届出してから受理公表までの期間の見通しがきかず、販売戦略を立てたり顧客等に説明したりしにくいことなどを挙げた。書類を提出して不備を指摘され出し直すということを5回繰り返し、1年近くかかった企業もあるという。 消費者庁の人員が足りないことや、企業側にもガイドラインの理解が足りなかったり誤字脱字などのケアレスミスが多発していたりすることなどが原因。そのため、事業者2団体は、届出前のチェック作業を第三者機関などに委託することなどを提案している。 なるほど、一つの制度であっても、立場が違えば見方はまったく異なるものだ。消費者や学識者、消費者委員会では、制度自体への批判が強く、事業者の倫理を厳しく問うていても、それはなかったかのように、別の場では事業者の見る“メリット”が語られる。 ワーキング・グループの非公開の会合の後、内閣府規制改革推進室による記者説明会で、健康食品業界誌の記者が「ワーキング・グループの一部委員が利害関係者に該当するのではないか」と質問したという8)。機能性表示食品制度の届出に必要な研究レビューを請け負う協会の副理事長を務めている大学教授や、機能性表示食品を販売する企業の副社長が、ワーキング・グループのメンバーとなっている。 業界誌の記者があえて、こうした視点から質問し、ウェブメディアで記事化している。消費者団体等から非難を浴びているにもかかわらず産業振興へ突き進むことへの危機感が、業界内でも出てきていることがうかがえる。私自身の取材でも、事業者の間で「このままでは良くない」「消費者からの信頼を得られなければ、市場拡大は望めない」などの声がある。だが、それは大きな声とはなっていない。 混乱を抱えたまま、機能性表示食品制度はもうすぐ3年目に入る。制度はどこへ向かうのだろうか。ガイドラインがどのように改訂されるかが、今後の焦点となる。報告書の内容をしっかりと反映し、学識者や消費者団体が納得できるガイドラインとなっていなければ、非難はもっと強まることだろう。 見直しは進むか付け加えれば、2016年は特定保健用食品(トクホ)制度が大きな曲がり角にあることを実感させた年でもあった。3月には、健康増進法初の違反勧告が、トクホ製品に対して行われた。許可されていた表示が「本品は食酢の主成分である酢酸を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です」なのに、「血圧低下作用」などと新聞広告でうたっていた。消費者庁は、「高血圧は、薬物治療を含む医師の診断・治療によらなければ一般的に改善が期待できない疾患」とし、この広告が「薬物治療によることなく、 本件商品を摂取するだけで高血圧を改善する効果を得られるかのように示す表示をしていた」とみなした9)。 また、9月には制度史上初めて、許可取り消しが行われた。1企業が販売していた6製品が対象で、機能性を発揮するのに必要な関与成分が、表示されていた規定量を満たしていないという理由だった10)。 1年前、機能性表示食品制度は問題が山積していると書いたが、より一層、複雑化しているように思う。個人的には、この制度を機に、健康食品業界が抱えている安全性や機能性の担保の不十分さ、品質保証のいい加減さなどの課題が、事業者自身の努力により解決されることを願っていた。だが、残念ながら、機能性表示食品はほかの健康食品とまったく同じ課題を抱え込むことになっている。 検討会報告書と同様に、事業者に倫理観に基づく事業活動と説明責任を求めたい。加えて、制度はさらなる情報公開を進めないと、消費者庁のいう「消費者の誤認を招かない、 自主的かつ合理的な商品選択に資する表示制度」とはならない。検証事業の結果を製品名等も含めて公開することなどが求められるのではないか。 参考文献1)消費者庁・機能性表示食品制度における機能性関与成分の取扱い等に関する検討会 2)内閣府規制改革推進会議 3)SUNATECメールマガジン2016年2月号、「機能性表示食品、消費者はどう見るか?!」 4)消費者庁・機能性表示食品に関する情報 5)株式会社インテージニュース・『健康食品・サプリメント市場実態把握レポート2016年度版』11月21日に発行 6)全国消費者団体連絡会・「機能性表示食品」の制度と運用に対する意見を提出しました 7)第233回 消費者委員会本会議議事録 8)健康情報ニュース.com 規制改革推進会議WG、機能性表示食品の運用で議論 9)消費者庁・ライオン株式会社に対する健康増進法に基づく勧告について 10)消費者庁・特定保健用食品の関与成分に関する調査結果について(第2報) 略歴松永 和紀(マツナガ ワキ) サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |
| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |

