|
食塩相当量について
一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC
第一理化学検査室 1. はじめに「食品表示法」が平成27年4月1日に施行され、1年以上経過した。食品表示法は「JAS法」、「食品衛生法」、「健康増進法」の3つの法律の食品表示に関する規定を統合し、従来の表示ルールを一元化することで、消費者と食品関連事業者の双方にとってわかりやすいものとなった。その中で大きく変わったのが栄養成分表示の義務化である。食品関連事業者に対して、原則として、全ての加工食品および添加物に、栄養成分表示が義務づけられた。栄養成分表示とは、どのような栄養成分がどのくらい含まれているのかをわかるようにしたもので、従来は、健康増進法によって定められていた。これまでは任意表示であり、全ての食品に表示されているものではなかったが、食品表示法では、「熱量(エネルギー)」、「たんぱく質」、「脂質」、「炭水化物」、「ナトリウム」の5項目の表示が義務付けられ、原則として、ナトリウムは食塩相当量として記載されることとなった。今回は、表示が義務付けられた項目の中から、私たちの食生活になじみ深いナトリウム及び食塩相当量について解説する。 2. ナトリウムと食塩相当量の関係ナトリウムは汗などの体液の成分として生理的に不可欠な元素である。食品中ではナトリウム塩またはナトリウムイオンとして存在しており、私たちはその多くを塩化ナトリウム(食塩)として摂取している。ナトリウムは普通に食事をしていれば不足することはないが、不足するとめまいやふらつき、脱水症状などが起こるといわれている。そのため、スポーツなどをして大量に汗をかいたときは適切な補給が必要となる。問題となるのは食塩のとりすぎである。日本人は昔から料理にだしや調味料を多く使用するため、どうしても食塩を過剰に摂取しがちである。食塩のとりすぎは、高血圧の原因となり、それに伴い動脈硬化、心筋梗塞や腎臓病などさまざまな病気を誘発する可能性がある。では、食塩をとりすぎるとなぜ血圧が上がるのか。血圧は心臓から全身に送り出された血液が血管壁を押す圧力のことで、心臓が収縮、拡張することで発生する。人の体は血液中のナトリウム濃度を一定に保とうとするため、食塩を過剰に摂取するとナトリウム濃度を下げるために水分を必要とし、細胞内の水分を血液に移行させる。その結果、血液量が増え、血管壁に強い圧がかかり、血圧が上がる。 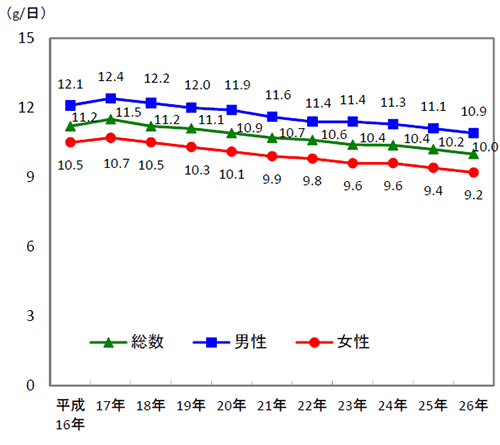 図1:食塩摂取量の平均値の年次推移(20 歳以上) 厚生労働省 平成26 年国民健康・栄養調査結果の概要(平成27年12月) 健康を維持するための食塩摂取量の目標値が定められているにも関わらず、栄養成分表示ではナトリウムとして記載されていた。そのため、食塩量を知るためにはナトリウムを食塩相当量に換算する必要があった。食塩つまり塩化ナトリウム(NaCl)は、質量数が23のナトリウム(Na)と質量数が35.5の塩素(Cl)からなる分子量58.5の化合物である。食塩相当量は、ナトリウム量に換算係数である2.54(=58.5/23)をかけることで求めることができる。
なお、消費者庁が公表した「栄養表示に関する消費者読み取り等調査事業」の調査結果報告書(平成26年3月)によると、食塩相当量の意味を理解していた消費者は、全体の50.3%であったにも関わらず、ナトリウムの表示から食塩相当量を正しく算出できたのは、わずか3.9%であった。 3. ナトリウムの表示1)表示のルール原則、ナトリウムを食塩相当量として表示することになったが、例外としてナトリウム塩を添加していない場合、任意でナトリウムの含有量を表示することができる。その場合はナトリウム量の次に食塩相当量をかっこ書きで併記する。 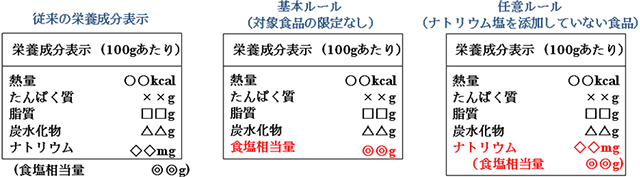 図2:表示のルール 2)強調表示強調表示では、欠乏や過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えている栄養成分について、補給や適切な摂取ができる旨の表示をする際の基準が定められている。強調表示は補給ができる旨の表示(栄養成分の量が多いことを強調)、適切な摂取ができる旨の表示(栄養成分の量又は熱量が少ないことを強調)、添加していない旨の表示(無添加の強調)の大きく3つに分けられる。ナトリウムは過剰摂取が問題となるため、ナトリウム量が少ないことを強調して表示することができる。その場合、食品100 gあたり(飲料の場合は100 mLあたり)のナトリウム量が5 mg未満の場合は、「無」、「ゼロ」、「ノン」、「レス」等の含まない旨の表示をすることができ、食品100 g中あたり(飲料の場合は100 mLあたり)のナトリウム量が120 mg以下の場合、「低」、「ひかえめ」、「少」、「ライト」等の低い旨の表示をすることができる。比較対象品とのナトリウム量の差(低減量)が、食品100 gあたり(飲料の場合は100 mLあたり)120 mg以下で、さらに規定された基準値である25%以上の相対差(低減差)がある場合、「○○%減」、「カット」、「オフ」等の低減された旨の表示をすることができる。その際は、「自社従来品○○」、「日本食品標準成分表2015 ○○」等の比較対象品を特定し、比較対象品に比べ、低減された量や割合を明記しなければならない。ただし、みそやしょう油はナトリウム量を25%以上低減することで保存性や品質等を保つことが困難であるため、みそは15%以上、しょう油は20%以上とする例外が認められている。 4. ナトリウムの分析方法「食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号)別添 栄養成分の分析方法等」に、ナトリウムの分析方法が記載されている。前処理方法として、塩酸抽出法と灰化法の2種類がある。 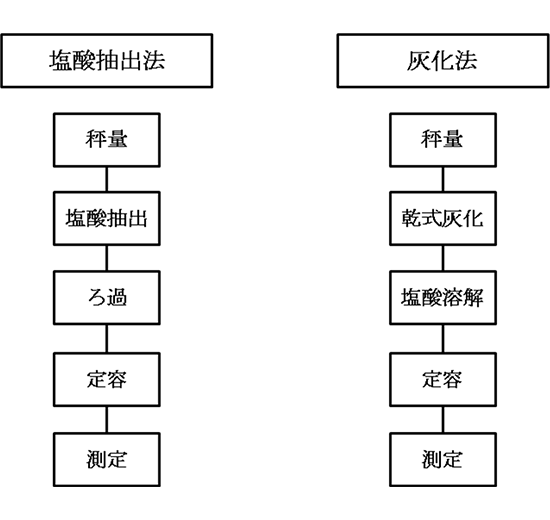 図3:ナトリウム分析方法の操作フロー 5. おわりに「食品表示法」では原則として食塩相当量の表示が義務化された。私たちの食生活において食塩は必要不可欠なものであるが、過剰摂取は健康を損なう可能性がある。食塩相当量とは何かを正しく理解し、適切な量を摂取することが必要である。消費者の方々が、健康的な食生活を行うためにも、栄養成分表示や強調表示に着目していただきたい。 参考文献国立循環器病研究センター 循環器病情報サービス 血圧の話 第1版 平成27年3月 消費者庁食品表示企画課 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |
| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |

