|
金属の溶媒抽出法について~鉛を例に~
一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC
第一理化学検査室 2014年9月の豆知識では、重金属試験法について紹介した(http://www.mac.or.jp/mail/140901/03.shtml)。この方法は、重金属類が総量としてどれぐらいの濃度域で試料中に含まれているかを知る手段としては、高額な分析機器を必要としない有効な方法である。しかし、平成26年3月26日に行われた薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会の資料として公開されている第9版食品添加物公定書作成検討会報告書を見ると、重金属規格が主に鉛規格へと改正される予定であることから、今後、食品等の規制には、重金属類としてではなく、各個別の金属元素として規格が設定されていくと思われる。(第9版食品添加物公定書案は、平成27年12月25日に行われた同部会の資料として公開されている。)個別元素は、通例、試料を灰化したのち、その酸溶解液を原子吸光光度計や誘導結合プラズマ(ICP)発光分析装置などで測定するが、金属元素の種類、試料によっては、感度不足や干渉等の影響で測定できない場合がある。そのような時に採用する前処理法の1つとして溶媒抽出法がある。方法の概要は、まず、目的金属を含む水溶液に親水性が小さいキレート剤などの抽出試薬を加えて目的金属を錯化または抽出試薬とのイオン対とする。そこに有機溶媒を加えて、抽出試薬との相互作用で水和水を失い、疎水性を増した目的金属を有機溶媒中に転溶する方法である。転溶の際に、水溶液量よりも少ない量の有機溶媒に転溶することで濃縮できる点や不要な成分が溶媒中に抽出されないことで測定時の妨害を抑制できる点など、溶媒抽出法を用いることの利点は大きい。本稿では、清涼飲料水の成分規格にある鉛の試験法に溶媒抽出法が用いられているので、これを例として紹介する。 清涼飲料水の成分規格における鉛の試験法試験操作の概要を図1に示す。試料の湿式灰化または乾式灰化ののち得られた試験溶液に対し溶媒抽出を行
う(灰化手順については省略する)。まず、試験溶液にクエン酸アンモニウム溶液を加え、指示薬にブロモチモールブルー溶液を用いてアンモニア水で中和する。この液に硫酸アンモニウム溶液を加えたのち、ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウム(DDTC)溶液を加えて鉛を錯化し、メチルイソブチルケトン(MIBK)を加えて激しく振とうする。静置後、分離した上層(MIBK相)について原子吸光光度計で測定を行う。
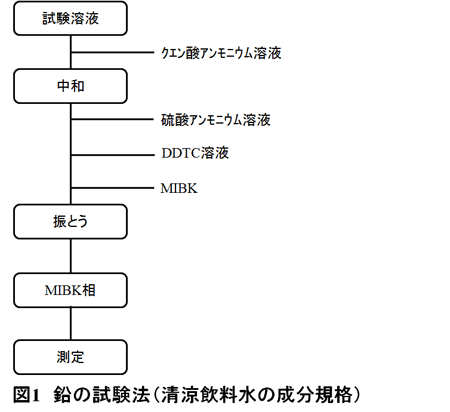
溶媒抽出法の応用清涼飲料水の成分規格における鉛の試験法を紹介したがその他の試験法では、DDTC以外のキレート剤としてピロリジンジチオカルバミン酸アンモニウム(APDC)やジチゾンを用いる方法がある。また、キレート剤ではないがヨウ化カリウムを加えてヨウ化物として抽出する方法もある。また転溶する有機溶媒例としてMIBK以外に、ジイソブチルケトン(DIBK)、クロロホルム、酢酸ブチル、ベンゼンなどもある。キレート剤と抽出する金属の組み合わせごとに最適なpHがあるので、抽出する際のpHには注意が必要である。キレート剤や溶媒の種類により抽出効率が100%ではない場合があるため、標準液も同様に抽出する、もしくは抽出操作を複数回行い目的金属を完全に抽出する必要がある。より精確な測定を目指すのであれば標準添加法を行うことが望ましい。 鉛以外での溶媒抽出法の例鉛以外の金属でも溶媒抽出法が用いられている試験法があるので簡単にその例を紹介する。清涼飲料水の成分規格におけるスズの試験法では、キレート剤にサリチリデンアミノ-2-チオフェノール(SATP)、抽出溶媒にキシレンを用いる。第2版食品中の食品添加物分析法のミョウバン類の試験法では、アルミニウムの測定に際し、キレート剤にアセチルアセトン、抽出溶媒に酢酸ブチルを用いており、ポリソルベートの試験法では、ポリソルベートとコバルトチオシアン酸錯体からなる錯体をジクロロメタン中に抽出している。第十六改正日本薬局方一般試験法の鉄試験法B法では、鉄(Ⅱ)を2,2’-ビピリジルと2,4,6-トリニトロフェノールからなる三元錯体として1,2-ジクロロエタンに転溶させて検液としている。 最後にICP質量分析装置などの高感度で選択性の高い測定機器を用いることができるようになり、特別に精製・抽出操作などをしなくても金属元素は測定できるようになってきた。また、溶媒抽出法ではなく、カートリッジカラムやディスクなどを用いた固相抽出法も用いられるようになってきており、振とうなどの手作業が不要で、検液を負荷し、リンスののち、溶出させるだけのより簡便な操作での抽出も可能となってきた。しかし、より高性能な機器はより高価であり、固相抽出のアクセサリはその性能にロット間差やメーカー間差があるため、比較的簡便に安価で実施できる溶媒抽出法は今後も主要な試験法としてあり続けると考えられる。 参考文献1) 日本薬学会編:“衛生試験法・注解2015” 金原出版 (2015) 2) “第8版食品添加物公定書解説書” 廣川書店 (2007) 3) “第十六改正日本薬局方解説書” 廣川書店 (2011) 4) 平成26年3月26日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会 5) 平成27年12月25日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会 6) 日本食品衛生協会編:“第2版食品中の食品添加物分析法 2000” (2000) 7) 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC):“肥料分析法(農林水産省農業環境技術研究所法)-1992年版-” 8) 厚生労働省 監修:“食品衛生検査指針理化学編” 日本食品衛生協会 (2015) 9) 厚生労働省:“食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法 10) 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長通知「食品中の食品添加物分析法」の改正について 平成20年4月30日食安基発第0430001号(2008) サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |
| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |

