|
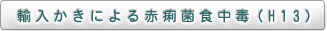 |
|
|
|
平成13年11月から12月にかけて、日本はBSE(牛海綿状脳症)騒動の真っ盛りであったが、全国30都府県にまたがり160名の赤痢患者の発生(diffused outbreak)があった。もちろん海外渡航歴によるものではなかった。この事例は、三重県健康危機管理対策室(当時)が他県にも積極的疫学調査を行い、赤痢患者に共通するものは、特定の2加工業者が出荷した生かきであることを突き止めたものである。かきの加工業者を所管する自治体に適切な措置を進言し、回収命令等の行政処分と原因究明が行われたが、関連のある施設やかきから赤痢菌は分離されなかった。しかし、2加工業者の共通事項が、韓国産かきを仕入れていたことであったことから、その関与が強く疑われた。 |
|
そして年末仕事納めの12月28日、麻痺性貝毒検査用かきの残品(韓国産かき)から分離された赤痢菌の遺伝子型が患者由来株と同じであったことから、今回の散発的赤痢は、韓国産輸入かきを原因とする赤痢菌食中毒であったことが判明した。まだ記憶に新しいかきによる大きな健康被害事例である。この事件によって、輸入かきが国産として産地偽装されていたことが明るみとなり、三重県でも風評被害の発生を危惧する事態となった。「真面目にやっている我々も新聞報道されると同じような目で見られる。BSE対策のようにかきもトレーサビリティーの仕組みを作って、もっと厳しく取り締まってほしい!」。漁協組合長から強い憤懣の声が出た。三重県の場合、かきの養殖業者は、それぞれが顧客を持つ加工業者でもある。売っているかきは自分が養殖した、トレーサビリティーがしっかりしたプリプリのかきなのである。 |
|
|
|
※コーヒーブレイク:三重県の決断と量販店の英断 |
|
上記赤痢事件が全国的に問題となっている12月初旬、小生も保健所で赤痢患者の届出に直面した。迅速に対応し、かきとの関連を徹底的に調査した結果、健康危機管理対策室で把握していた特定の加工業者のかきを、1週間前に患者さんが食していたことが明らかとなった。家族で発症したのは生かきを食べた人だけであった。また、県内で数人の赤痢患者に共通する食品は、やはり特定の加工業者が出荷した生かきで、このかきを原因食品とする赤痢の流行であることが疫学的にはっきりしたのである。 |
|
しかし、新たな問題が発生した。ロットも加工年月日も全く異なり、赤痢菌の存在の可能性も全く不明であるが、この特定の加工業者が出荷したかきを、その日から3日間にわたって特売する新聞の折り込み広告を、保健所職員が偶然見つけたのである。届出のあった日である。どうすべきなのか、まさに公衆衛生行政の根幹に係る事態の発生である。 |
|
いつ加工されたかきが問題であるのか全く不明の段階である。加工業者を所管する自治体の回収命令や業者の自主回収もまだ出ていない。かきの残品はなく、かきから赤痢菌も検出できていない状況では、量販店に自主回収を指導すれば、今後の調査結果如何によっては損害賠償請求の対象となるリスクを覚悟しなければならない。風評被害につながるリスクも高く、発生すればその責任はどうするのか。科学行政である公衆衛生行政に携わる者は、いつもこのジレンマに悩むのである。 |
|
結論は、当時取り組んでいた行政経営品質賞の仕組みから導いた。顧客本位の考え方である。新たな赤痢患者が出る可能性は少ないが、もし存在する場合は一刻も早く医療につなげ県民の生命を守るのが公衆衛生行政だ、早く事実を公表したほうがいい。また、リスクは低いがこの情報は当該量販店に報告し、量販店として顧客本位で自ら措置をどうするか考えてもらおう。 |
|
前者の措置は、深夜であったが本庁健康危機管理対策室がプレスし、事実を公表した。しかし、その後の関係施設等の調査でも、赤痢菌は検出されなかったことから、本庁の担当者はさぞかし厳しい精神状態が続いたことであろう。そして年末12月28日、厚生労働省から「赤痢菌を原因とする食中毒に関する対応について」として、検査結果がプレスされた。三重県の調査結果および措置の正当性が明らかとなったのである。三重県健康危機管理対策室を設置して1年目、全国的にもその存在が高い評価につながった事例であった。もちろん担当者も損害賠償請求のリスクから解放され、安心して新年を迎えることができた。 |
|
他方、保健所から事実を知らされた量販店は、どう行動したのか。翌日からの販売は中止するとともに、販売済のものについては各購入者に連絡し、リスクを知らせて自主回収した。もちろん、既に食してしまった消費者には、保健所の指導により加熱調理したかどうかを尋ね、生食した場合のリスク対応を知らせたのである。会員カードで購入する顧客が多く、購入者の多くは特定できるとはいえ、この地元量販店のとった適切な措置に爽やかなものを感じた。また、幸い新たな赤痢患者の発生の届出はなかった。あれから7年間、食品の安全安心について講演する機会が多かったが、安心(信頼)できる食品事業者としてこの量販店の対応をよく紹介したものだ。 |
|
|
|
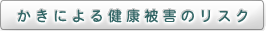 |
|
|
|
上記のように、かきによる健康被害は、食中毒だけでなく集団感染症としても多くの実例が報告されている。また、河川河口部や内湾の潮間帯には多くの天然マガキが付着し、もちろん周囲に広がる干潟にはアサリなど多くの二枚貝も生息している。これらの二枚貝は、人の食料としての価値だけでなく、海の環境浄化の大きな役割も担っている。そして、宿命として様々な病原細菌やウイルスに汚染されるリスクももっている。実際、東京湾におけるウイルス保有状況の調査結果が報告され、汚染が現実であることが示されている。 |
|
しかし、これらの事実が明らかになる以前から、人々は天然の二枚貝を加熱調理して食べてきた。小さな天然のマガキは、主に炊き込みご飯にするなど、いずれもリスクの高い二枚貝の中腸腺を加熱する調理を行い、まさに生活の知恵を働かせて利用してきたのである。 |
|
宮川河口部マガキ分布(PDF:888KB) |
|
他方、養殖かきによる健康被害のリスクはどう考えるべきなのであろうか。生食用かきは、食品衛生法でも食中毒や感染症リスクの非常に高い食品として、前号で紹介したように規格基準が設定されている。養殖海域の水質規制があり、浜に原料かきを水揚げした直後から養殖業者・加工業者・販売者には厳しい衛生管理が要求されている。 |
|
したがって、表示が「生食用」とされているかきは、清浄海域で養殖されたもの又は三重県のように殺菌海水で浄化されたかきである。このように各基準を遵守したかきについては、これまで述べたかきによる健康被害は、ノロウイルスを除きほとんど問題となっていない。佐藤忠勇さんが開発した浄化システムによって、赤痢等の病原細菌による健康被害のリスクについては、ほぼ安全が確保できていると考えることができる。 |
|
2009かき養殖(PDF:632KB) |
|
みえのカキ安心情報:カキ養殖の作業工程フロー |
|
それでは、問題であるかきが保有するノロウイルスによる健康被害はどうであろうか。 |
|
かきを食中毒発生の推定原因食品とするには、「かきを食した人の発症率が高いのは当然であるが、かきを食しなかった人の発症率が非常に低い」という疫学調査結果が特に重要である。メニューに生かきが含まれていても、ノロウイルスは人を介した汚染食品によっても食中毒が引き起こされるし、その確率の方がむしろ高いからである。そして、かきを原因とする食中毒はもう一つ特徴がある。小生は、1997年から2001年の5年間において、三重県産のかきが原因食品(推定を含む)となって、所管保健所が集団食中毒と判断したこと、しかも患者便のノロウイルス遺伝子検査で陽性となっている事例を養殖海域別にピックアップしたことがある。三重県の場合、かきの出荷・消費量はもちろん12月にピークを迎えるのだが、それに反し食中毒発生は、1月2月の厳冬期にほとんどが集中していたのである。 |
|
SRSV食中毒の原因カキ(三重県産)の養殖海域別月別一覧(PDF:35KB) |
|
2006/2007〜2008/2009、全国週別SRSV検出報告数(PDF:88KB) |
|
|