 |
|
| 図1は、『朝日新聞』に掲載されたそのような「食」に関する記事の割合を適当なキーワードで検索し、時系列で示したものである。 |
| 1990年代半ばくらいまでは多少の変動があるものの、全記事に対する出現確率は0.5%以下であったが、96年の夏に一つ山ができているのが分かる。これは多発した「O-157食中毒事件」によるものだ。学校給食が原因で堺市を中心に発生した集団食中毒では、約8000名の患者を出し、3名が死亡した。このアウトブレイクを含め、この年は全国でO-157により8名の尊い命が奪われている。 |
| 2000年の夏にも山があるが、これは当時の「雪印乳業」の製品による、黄色ブドウ球菌エンテロトキシン食中毒によるものだ。全国で1万数千名の有症者を出した、大規模食中毒事件であった。この夏は全ての記事の1%近くを「食の事件」が占めている。この頃までは、報道量の変化の原因は、比較的説明がつきやすいものとなっている。 |
| さて、2001年秋、日本に牛海綿状脳症(BSE)、いわゆる「狂牛病」が上陸した。周知の通り、BSEの侵入を許したことで、我が国の食品安全行政に対する信頼は著しく失墜した。政府は大いに批判され、その結果、食品安全委員会の新設にもつながった。また様々な食品関連産業が大きなダメージを受けるなど、社会全体に広範な影響があったことは間違いない。 |
| ところがグラフを見ると分かるとおり、「食」に関する報道量は、その翌年に大きな山ができている。基本的に、行政のBSE緊急対策は2001年中に出そろっており、また事件の影響で暴落した牛肉の価格も2002年春に底を打っている。BSE問題そのものは、少なくとも一旦は、比較的早期に収束しているのだ。それではなぜ翌年に著しく報道量が増大したのだろうか。 |
| 実は、似たような現象は2008年にも起きている。2008年の山は二つあるが、前半は、あの中国製冷凍餃子による食中毒事件であった。だが、後半はまた別の事件「群」によるものだ。これらの報道を精査してみると、興味深いことがわかってくるのだが、この点については、のちほど改めて検討してみよう。 |
|
| 図1 新聞紙面における、食品問題に関する記事の割合 |
|
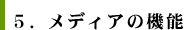 |
|
| 以上の議論から見えてくるのは、報道によって作られるわれわれのイメージと、統計的なデータとのギャップである。前者からは、我が国の食の安全性が近年著しく悪化しているかのような印象を受けるかもしれないが、すでに述べたように、少なくとも食中毒の死亡者数は減っている。 |
| また、もう一つ指摘すべきこととして、近年の「食の問題」として報じられる内容には、産地や原材料、賞味期限などの「偽装」に関するものが多いという点である。これは、表1からも明らかであろう。これらの事件は、安全性と全く無関係であるとまでは言えないが、多くの場合は、直ちに健康被害が出るほど危ない食品ではない。むしろ、企業活動などに関する信頼性の問題としての「食の問題」と見るべきであり、しばしばこれらが間接的に「食の安全性」への社会的な不安を惹起してきた、と考えられる。 |
| このような状況においては、先ほども少し指摘したように、いわゆる食の「プロ」、「専門家」のサイドからしばしば、「報道は、社会に誤ったイメージを与えている」という批判が聞こえてくる。いわゆる「風評被害」などの問題も、この種の文脈で捉えうるものもある(このような苦言は最近、「食」に限らず、様々な分野の「プロ」から聞こえてくる)。 |
| 仮にメディアを単なる情報の「伝達手段」と見なすならば、あながち間違いでもないかもしれない。しかしここでは、メディアの、とりわけジャーナリズムの機能は、本来、より幅広いものであることを指摘しておくべきであろう(メディアとジャーナリズムの違いについては、林 2002を参照のこと)。 |
| 民主的な社会においてメディアは、理念的には、以下の三つの機能を期待されている。まずは、公平で正しい情報を伝えること。また、公共的な懸念や問題を議論する、開かれた言論空間を作ること。そして最後に、政府や企業の行動を監視する機能である。上記の「苦言を呈するプロ」は、メディアの機能を矮小化して捉えているようにも思われるのだ(神里 2008)。 |
| また、このことを逆に見れば、理想的なメディアであればあるほど、その中身は「現実」の単純なコピーではあり得ない、ということを意味している。明示的にであれ暗黙的にであれ、メディアが伝えるイメージは、「現実」に対して、なんらかの加工を施したものであるし、またそうあるべきなのである。 |
|
| 表1 「平成」のおもな食品問題・事件(神里作成) |
|
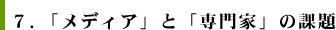 |
|
| メディアのアジェンダ・セッティングは、公共的な課題を、広く社会的に議論していくうえで、重要な機能である。しかし同時に、いわゆる「報道過熱」が生じることで、特定分野に過度に注目を集めさせてしまい、バランスを欠いた社会的対応をもたらしたり、逆に他の重要な課題が社会的に見過ごされてしまう原因を作ってしまう、といった危険性があることを否定できない。 |
| これらの問題を解消しながら、社会全体としてメディアを有効活用するにはどうすべきか。難しい課題であり、また字数の都合もあるので、ここでは、二点だけ指摘しておきたい。 |
| まず、メディア自身が、多様性を持つことである。 |
| 一つの報道機関が、ある種キャンペーン的に特定の問題を追及していくという姿勢は、ジャーナリズムの手法として健全なものである。だが、そのキャンペーンに、他の報道機関が次々と追随するとすれば、それは望ましくないことだ。また、報道の世界には「特落ち」という言葉がある。これは、他の新聞社が報道していることを、自社だけが報じられなかった場合を指す。担当の記者にとっては非常に不名誉なことであるらしいが、消費者の立場からすれば、正直、たいした問題ではない。むしろ、他のメディアが気づかなかった課題をいち早く見出し、スクープしてくれるかどうかの方が、社会にとっては重要だろう。 |
| こういう「業界的慣習」にとらわれることなく、一人一人の記者が独自の視点で調査報道を重ねていくことが、結局は、バランスの取れた良質な報道への近道であると考えられる。 |
| 他方、さまざまな分野の専門家−本稿で取り上げているのは食品安全の専門家であるが−にはどのようなことを期待すべきだろうか。 |
| まず、適切なアジェンダの設定には、「専門知」の素早い動員が不可欠である。だが、メディアと専門家の適切なコラボレーションは、案外簡単ではない。それにはいくつか理由がある。 |
| 専門家は一般に、自らの専門性に基づいた「厳密性」を重視する。また、自らの「領分」に忠実であることが普通であり、専門分野の越境には禁欲的である。たとえば、何かの事件が起こった際、ジャーナリズムは専門家に意見を求めることがある。しかし、自らの専門性に忠実であろうとするあまり、「自分はふさわしくない」と取材を拒否する「きまじめな専門家」もいるだろう。また逆に、専門性において適切ではない人物がテレビなどでコメントをすると「あいつはちゃんと分かっていないのに」「売名行為にすぎないよ」などと、学者の仲間内で非難される場合もあるだろう。 |
| 確かに、専門的能力において著しく乏しい人物が「専門家」としてメディアに登場することは危ういことである。しかし「“真の専門家“がメディアに登場してくれないから、仕方なく“ど真ん中ではないが近そうな専門家”にコメントをお願いした」という場合も多いだろう(本人にはそうは言わないだろうが)。そうであったとしても、視聴者にとっては有益であることも多いはずだ。 |
| また、そもそも当該の問題とその専門家の専門性が合致しているかどうかは、誰が判断すべきことなのだろうか。「それは、その人物を登場させたメディアの側の責任だ」という声もあるかもしれない。だが、そもそもメディアは、「その問題のことがよく分からない」から専門家に助言を求めているのだ。従って、そこまでの責任を負わすのは普通に考えて酷だろう。となれば、専門家が進んで社会的責任を果たし、自ら声をあげることが期待されるのだが(もちろんそういうケースも増えている)、上記の通り、とりわけアカデミズムの世界では、そのようなことはあまり推奨されていない(尤も、近年はこのような規範も変化しつつあるようだ)。 |
| この種の問題は、現代社会における専門家のあり方をめぐるさまざまな議論とつながっているため、簡単に正解を示すことのできる話ではない。だが少なくとも、専門家も、メディアとのコミュニケーションにおいては、上記のような厳密さや専門性の限定については若干、自己規制を緩め、その分、社会的意義や、分かりやすさといった、別の基準を一定程度受け入れることも必要な時代に入っているといえるだろう。そうすることで、より適切なアジェンダが設定され、意義のある「公論」が展開する可能性が高まっていくに違いない。 |
|
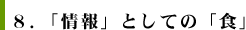 |
|
| 以上、「果たして、われわれの食は危うくなっているのか?」という問いから、メディアや専門家のあり方にまで話が発散してしまったが、最後に、このような「報道過熱」的な現象が、今後どうなっていくのか、そして、その時われわれの「食」はどうなっているのかを、少しだけ考えておきたい。 |
| まず、一点指摘すべきは、これまで述べてきたような、社会全体を巻き込むアジェンダ・セッティングは、実はマス・メディアの存在を前提とした現象である、ということだ。だが、90年代以降のネットワークの発達により、マス・メディアを支えてきた「広告収入」というビジネスモデルが、急速に崩壊してきていることは周知のとおりだ。米国ではすでに、多くの新聞社が消滅しており、かの有名なニューヨーク・タイムズですら、倒産の危機が何度もささやかれている。日本でも、今後、テレビ・新聞の大規模な統廃合は不可避であろう。 |
| 一方で若者を中心に、そのような旧来の巨大メディアに対する人々の関心そのものが低下しているのを感じる。SNSやミニコミ的なネットワークなど、より個人的な嗜好に基づくパーソナルなメディアへと軸足を移してきているのだ。そのような時代においては、社会的なアジェンダ、いわば「大文字の公共性」と言うべきものは、構築されないか、仮にされたとしても、実は代表性において疑わしい、といったことが起こりうるだろう。 |
| そうなれば、大規模な風評被害などは起こりにくくなるかもしれないが、同時に、社会的に真に注目すべき共通の課題にも、人々はあまり関心を持たなくなるだろう。また、一旦生じた噂やデマは、多数の細かなネットワークの奥深くに沈殿し、容易に修正することができなくなるかもしれない。 |
| そのような時代においては、「食」に関しても有力なポータルサイトやトレーサビリティ・システムを構築し、RFIDなども含めた情報の標準化を進めることで「対抗」するよりないだろう。それらは本来、安全行政の仕事であったはずだが、おそらく現実には流通企業が中心となってシステムが形成されるように思われる。巨大流通企業は、生産現場と消費者の間を独占的に媒介し、物質としての「食品」のみならず、「食に関するあらゆる情報」の流通をも担うことを目指すはずだ。これはすなわち、流通企業こそが「メディア」となる時代の到来を意味する。そして、それはすでに始まっている(当然そのような「集中」に対してはさまざまな弊害が出てくる可能性もあるだろうが、解決への道筋もないわけではない 神里 2003などを参照のこと)。 |
ともかく、時代は大きく変わりつつあるが、われわれの時代における「食」の最大の変化は、食べ物の機能が、単に「エネルギーを得て身体の材料とする」という、生物としての本来の目的を越えて、「情報としての食」という側面がクローズアップされてきたことにあるといえる。メディアの問題が重要になってきたのも、風評被害が無視できなくなってきたのも、また、ブランド食材がブームとなり、機能性食品が売れているのも、「情報としての食を消費する」という時代が来たことに起因する。われわれは、いつの間にか「記号を食べる」ようになったのだ。そのことが人類にとってどういう意味を持つかについては、また別の機会に検討することとしよう。
(了) |
|