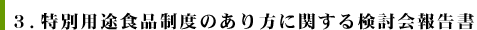 |
|
特別用途食品の使われ方の実態について厚生労働科学研究において、平成18年に全国約2,000の医療機関の管理栄養士を対象として、全国病院栄養士協議会の協力の下に、使用状況の調査を実施された。この調査の中では、実際に特別用途食品という許可を得たもの以外に、病者用食品として使われているもの自体についても併せて調査をしている。その結果、「病者用食品の使用頻度」について「頻繁に使用する」が52.5%、「時々使用する」が42%であり、ほとんどの医療施設で病者用の食品というものは使われていた。「病者用の食品を使用する理由」は、「便利である」が79.1%、「治療効果が期待できる」が72.2%であり、便利であって治療の効果が期待できることから使用されていた。「病者用食品を選択する際、特別用途食品であるかどうかを考慮するか」では、「考慮しない」が60%となっており選択する際に特別用途食品であるかどうかは余り考慮されているとは言えない結果が出ていた。特別用途食品であることを考慮する理由では、86.7%が「品質が保証されているから」、「安全性が高いから」が62.5%であり、高い品質と安全性が保証されているということが評価されていた。一方、考慮しない理由は61.6%が「企業の表示を信頼しているから」であった。「特別用途食品制度に今後希望すること」という設問では、「購入しやすくなる」が66.5%、「安全性と有効性が検証、保障できる制度にする」が60.4%で、より購入しやすいものになること、安全性と有効性がより検証、保障できる制度となることが期待されていた。
このような知見を受けて、平成20年7月にまとめられた特別用途食品制度のあり方に関する検討会報告書の概要は以下のようである。 |
|
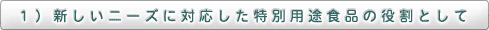 |
|
|
特別用途食品は、通常の食品では対応が困難な特別の用途を表示するものであり、対象となる者に十分認知されれば、適切な食品選択を支援する有力な手段である。今後高齢化が進展する中で、在宅療養における適切な栄養管理を持続できる体制づくりが求められており、特別用途食品もこうしたニーズへの的確な対応が必要だある。併せて、許可の対象となる食品の範囲について、当該食品の利用でなければ困難な食品群に重点化を図る必要がある。 |
|
|
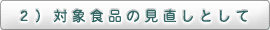 |
|
|
特別用途食品制度の対象とする食品の範囲について、以下のとおり見直しが必要である。
在宅療養も含め病者の栄養管理に適するものに、総合栄養食品(いわゆる濃厚流動食)を病者用食品の一類型として位置付ける。病者用単一食品と栄養強調表示との関係を整理して、高たんぱく質、低カロリー、低ナトリウムについては、栄養強調表示により代替的役割とする。病者用組合わせ食品を宅配食品栄養指針による管理に統合する。在宅療養の支援には、宅配病者用食品の適正利用の推進が適切であり、病者用食品についても宅配食品栄養指針に基づき栄養管理を図るべきである。高齢者用食品については、単なるそしゃく困難者用食品を許可の対象から外すとともに、高齢者用食品という名称をえん下困難者用食品に変更する。妊産婦、授乳婦用粉乳については、粉乳以外にも様々な栄養源が利用可能であることから、許可の対象とする必要性が相対的に低下している。 |
|
|
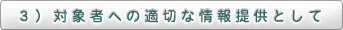 |
|
|
対象者に的確に選択され、利用され、適正な栄養管理がなされるよう、医師、管理栄養士等による適切な助言指導の機会が保障される必要がある。特別用途食品制度に関する認知度を高め、必要な流通の確保を図るため、一定の広告も認めるなど情報提供の手段を拡充する必要がある。また、表示内容の真正さを担保するため、収去試験の適正な実施などに努める必要がある。 |
|
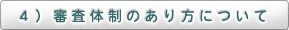 |
|
|
特別用途食品については、乳児や病者など特別の用途のためのものであるので慎重な審査手続が要請されているため、特に個別評価型病者用食品については、最新の医学、栄養学的知見に沿ったものとなるよう審査体制の強化を図る必要がある。 |
|
|
|