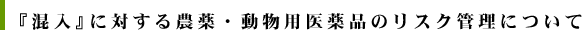 |
|
| 「混入」としているが、ここではドリフト的な残留も含めた非意図的残留や混入についても取り上げる。まず非意図的な残留・混入についてである。環境経由や製造・流通・保存時における汚染についての事例をいくつか挙げることとする。非意図的残留・混入に関してはこれらの事例を参考に自社での管理の参考にしていただきたい。 |
|
 |
|
|
| <アジア湖産魚から難分解性農薬(BHC・エンドスルファンなど)の検出> |
|
環境汚染物質が湖に流れ込み蓄積したものを生物濃縮的に蓄積 |
| <中国木耳からメタミドホスの検出> |
|
他の作物で使用された水溶性農薬が多量河川に流れ込みこの水によって栽培した木耳を汚染した可能性が有る |
| <宍道湖のシジミからチオベンカルブ、クミルロンの検出> |
|
稲に使われた農薬が湖に流れ込み汚染 |
| <中国産ショウガからBHCの検出> |
|
保存土壌中にBHCが残留していたため汚染 |
| <国産きゅうり、かぼちゃからディルドリン、ヘプタクロルの検出> |
|
既に国内では使用されなくなり数十年が経過するが、瓜類はドリン剤と類似構造物を特異的に蓄積するため検出 |
|
|
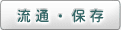 |
|
|
| <防カビ剤(ポストハーベスト農薬)> |
|
ポストハーベストとして使用されたかんきつ類のイマザリル・チアベンダゾール・オルトフェニルフェノール・ジフェニルは皮ごとの窄汁などの場合を中心に果汁にも残留。精油分とともに残留する。 |
| <家庭用殺虫剤> |
|
家庭用殺虫剤(農作物に使わないため農薬とは呼ばない)での保存庫の殺虫など |
|
|
 |
|
|
|
ゴム製品の加硫剤からチラムと同様物質の汚染、瓶詰め製品の蓋コーティング樹脂からのセミカルバジド、ポリエチレン製品安定剤のジフェニルアミン(冷凍ヤケ防止として使用の可能性も有り) |
|
|
 |
|
|
|
|
次に事件的「意図的混入」に対してである。このような意図的混入に関しては、検査での防御では「全品検査」しか方法は無く、現実的には不可能で有る。よって、事後にはなってしまうのだが、初期のクレームに対しての迅速な対応が必要であると考えられる。そのような場合の有効な検査を提案する。
まずは、残留農薬検査をベースとした一斉分析でスクリーニング検査が有効であると考えられる。一律基準の0.01ppmレベルを測定するには1週間程度が必要であるが、中毒を起こすと考えられるレベルの数百ppm以上であればもちろんのこと、実際には、数ppm程度の検査であれば1日程度での対応は可能である。
また、もうひとつの有効な検査は「異臭・異物検査」である。今回のメタミドホス事件の場合も「異臭・異味」を感じたと報道された。農薬が原因の場合は少なくとも数百ppm以上の混入が無ければ中毒にはならない。このような高濃度な場合であれば特別に農薬にターゲットを当てているわけではない「異臭」検査でも十分に農薬の特定が出来ると考えられる。以下に当財団で異臭・異物のクレーム検査において、農薬や農薬様化学物質が原因だった例を示す。
|
|
| <異臭マッシュルーム> |
|
クロロフェノール類が臭気の原因物質(次亜塩素酸消毒などによる生成の可能性) |
| <トマトの塩素臭> |
|
2,4-ジクロロフェノールが臭気の原因物質で、プロチオホス(有機リン系農薬)の分解による生成。同時にプロチオホスも検出 |
| <野菜にペレット状異物> |
|
メタアルデヒド(ナメクジ誘引駆除剤)のペレット |
|
|