 |
|
| 先月号では、抗酸化物質、及びその能力の測定方法の1つであるORAC(活性酸素吸収能力)の概要、並びに測定原理について説明させて戴きました。今月号では、ORACの分析値例の紹介、及び今後の課題について説明致します。 |
|
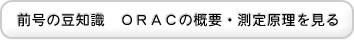 |
|
 |
|
抗酸化剤の能力を測定するORACには親水性と親油性が存在しており、親油性のORACの測定に関しては、Huangらによって開発されたランダムにメチル化されたβ−サイクロデキストリンを溶解促進剤として使用する方法が開発されています。
野菜や果物における親水性と親油性の割合は、多くの品種で親水性が全体の90%以上を占めており、このことから野菜や果物では、親水性ORACの値が総ORAC値と見なせる場合がほとんどです。また、果物において高いORAC値を示すベリー類では、高いアントシアニン含量も示すことがわかっており今後注目していく点だと考えられます。そして、野菜ではホウレンソウ、アスパラガス、カボチャが高い親油性ORAC含量を示しています。これらの野菜は暗緑色であり、緑色色素に関する親油性の成分が比較的高い親油性の原因ではないかと示唆されます。
一方、ナッツや香辛料の親水性・親油性の割合は品種によっても異なりますが、親油性ORACの割合が高いものも数種見られ、中でも香辛料のターメリックやショウガでは親油性の方が著しく高い値を示しています。更に、野菜や果物のORAC含量と比較すると親油性ORACの値は遥かに高く、数値で表すと一桁、なかには二桁も高い値を示しています。 |
|
| 【果物のORAC値】 |
|
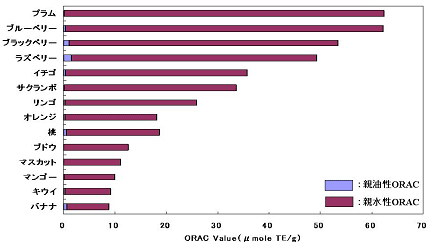 |
|
| 【野菜のORAC値】 |
|
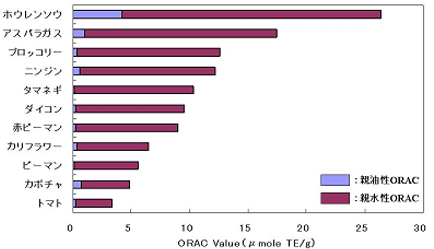 |
|
| 【ナッツのORAC値】 |
|
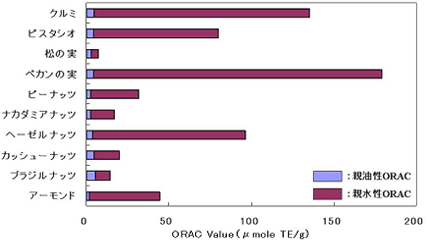 |
|
| 【香辛料のORAC値】 |
|
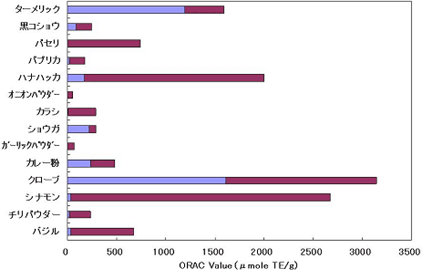 |
|
| 参考文献 J Agric Food Chem. 2004,52, 4026-4037 |
|
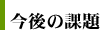 |
|
| ORACの測定原理は、水素原子移動メカニズムを測定原理としていることから連鎖切断型であれば測定できますが、カロチノイドなどの抗酸化剤に関しては測定できません。もう一つが、ORACや他のin vitro法により測定された抗酸化力が必ずしも生体内における抗酸化力と一致しないということです。このことに関しては、血清中のORAC測定、臨床試験、あるいは他の試験法との組合せで更なる抗酸化能力の測定に関与できるのではと考えられています。 |
|
|