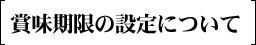 |
|
平成15年5月の食品衛生法改正により食品事業者の責務が明確に示され、賞味期限等の設定についてもより科学的・合理的な知見に基づき表示が求められています。
食品の日付表示に関しましては、平成7年4月から製造年月日の表示に代えて、「消費期限」または、「賞味期限」を表示することとなり定着してまいりました。
また、平成15年7月には、表示基準が改正され「賞味期限」と「品質保持期限」の2つの用語が「賞味期限」に統一され2年間の猶予期間を経て実施となっています。また、平成17年2月には「食品表示の設定のためのガイドライン」が発表され基本的な考え方が示されました。ここで改めて、賞味期限の設定について一般に行われている試験について紹介させていただきます。 |
|
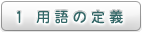 |
|
| 従来、食品衛生法とJAS法で用語や定義が異なっていた加工食品の期限表示については、食品の表示に関する共同会議を経て、次のように統一されました。 |
|
| 賞味期限: |
定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるのもとする。
賞味期限を表示するべき食品は、消費期限を表示すべき食品以外の食品であり、例えば スナック菓子、即席めん類、缶詰、牛乳、乳製品などがあります。 |
|
| 消費期限: |
定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなる恐れがないと認められる期限を示す年月日をいう。
消費期限は賞味期限にくらべ、品質が劣化しやすく、製造日を含めておおむね5日以内で品質が急速に劣化する期限表示の用語です。
消費期限を表示する食品の例としては、弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、食肉、生めん類などがあります。 |
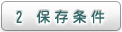 |
|
| 食品を保存する温度で賞味期限の1.5倍程度の安全係数をかけた期間の保存を行うのが一般的です。また、流通段階等で過酷に扱われる事を考えて過酷試験も行うことが必要と思われます。 |
|
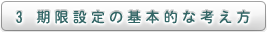 |
|
| 食品は多種多様な製品があり、その品質特性に応じて管理項目等は異なり、賞味期限の設定方法が異なってきます。さらに、安全である他に、おいしさ、香り、外観等の官能的な面を含め検討する必要があります。客観的な指標とは、理化学検査、微生物検査等において数値化することが可能な項目(指標)であり、色、風味等であっても適正に数値化された場合は客観的な項目とすることが可能となります。 |
|
| 【試験項目】 |
|
| 理化学検査: |
食品の製造日からの品質劣化を理化学的に評価するものであり、水分、水分活性、酸価、過酸化物価、pH、ビタミン類、エタノール、脂肪酸組成などが挙げられます。これらの項目を指標として、製造日の測定値と保存後の測定値を比較することにより品質劣化を判断します。 |
|
| 微生物検査: |
一般細菌数、大腸菌群、大腸菌、ブドウ球菌、サルモネラ、ビブリオ、セレウス、カビ、酵母などが挙げられ、食品の種類、製造方法、保存条件などに応じて選択する必要があります。 |
|
| その他項目: |
測定装置を用いて評価できる項目として、色調、香気成分分析などが挙げられます。 |
|
|
 |
検査項目例 |
|
| 検査項目 |
目的 |
| 一般細菌数 |
食品の衛生学的品質を評価する衛生指標菌 |
| 大腸菌群 |
環境衛生管理上の汚染指標菌又は食品の品質を評価する衛生指標菌 |
| 黄色ブドウ球菌 |
人の鼻、髪の毛、切り傷、にきびなどに存在する食中毒菌 |
| カビ数 |
製造・保管環境の確認 |
| 好気性芽胞形成菌 |
原料に由来。加熱工程の確認 |
| セレウス菌 |
自然環境に存在。熱に非常に強い菌 |
| クロストリジウム属菌 |
酸素が無い状態(嫌気性)で発育する菌 |
| 水分活性 |
品質保持の確認 |
| 水分 |
品質保持の確認 |
| pH |
品質保持の確認 |
| 酸価(抽出油脂酸価) |
油の劣化指標 ※酸敗 |
過酸化物価
(抽出油脂過酸化物価) |
油の劣化指標 ※酸敗 |
|
|
試験検査項目の設定は、製品はもちろんのこと、原材料、製造方法、包装形態、表示希望期限、保存条件や過去の事故事例などを鑑みて設定する必要があります。
また、食肉製品や麺類など、食品衛生法や衛生規範において細菌学的な基準が定められている食品があります。これらは賞味期限内にあっては基準に適合する必要があるため注意が必要です。 |
|
| 細菌検査についての検査項目の目安を別表にまとめましたので、ご活用ください。 |
|
|
|
|
|