|
リコピンについて
一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC
第三理化学検査室 リコピンは、生活習慣病予防において注目されている食品由来のカロテノイドの一つである。カロテノイドとは野菜や果実を彩る脂溶性色素成分であり、自然界には約600種類が存在しているといわれる。このうち日常の生活で摂取し、生理機能などが明らかになっているものは、リコピンの他、α-カロテン、β-カロテン、β-クリプトキサンチン、ルテイン、ゼアキサンチンなどがある。カロテノイドは炭素と水素のみからなるカロテン類と、炭素と水素の他に酸素が構成元素となるキサントフィル類に分類される。リコピンはカロテン類に属し、赤い彩りを与える天然色素である。 リコピンの特徴リコピンを含む主な食品はトマト、金時人参、スイカ、柿、あんず、パパイア、マンゴーなどがある。リコピンは、その名前が元々ギリシア語でトマトを意味する「Lycopersicon」に由来するように、食品としてよく使用されているトマトやトマトペースト、トマトソースのようなトマト加工品が主な供給源となっている。リコピンは、生鮮トマトで、約9㎎/100gも含まれており、トマト加工品についても、加工する工程で失われにくく、さらには濃縮されることもあるため、加工品の方が多く含まれることもある。さらに、リコピンの吸収率は、生鮮トマトよりも加工処理や調理されているトマト加工品の方が高いといわれている。食品として摂取されたリコピンは、ヒト組織に集積される。その後、血漿にβ-カロテン、ルテインと共に含まれる。また、腎臓、副腎、精巣などには高い濃度で蓄積されることから、各臓器での機能発現が期待されている。 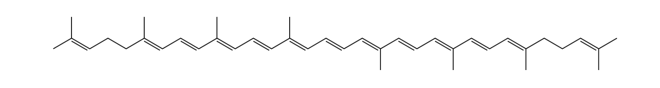 図1 リコピンの構造式 リコピンの作用、効果リコピンはカロテノイドの中でも秀でた抗酸化作用(活性酸素を消去する作用)を持つ成分であり、その効力はβ-カロテンの2倍以上、ビタミンE(α-トコフェロール)の約100倍ともいわれている。活性酸素は、がんの発生の原因の一つといわれており、リコピンの抗酸化作用により、がん予防が期待されている。他にも、肺疾患予防、糖尿病予防、動脈硬化予防、老化遅延、抗アレルギー、美容効果(メラニン生成抑制効果)、視覚機能の改善などの効果があるといわれている。近年、リコピンの生理機能に対する関心が高まり、多くの研究報告が行われている。 リコピン分析方法リコピンの定量分析については、同じカロテノイドであるα-カロテン、β-カロテンと同様に有機溶媒を用いた抽出法を行い、分光光度計を用いて抽出液中のリコピンの吸光度を測定する吸光光度法や、高速液体クロマトグラフにより抽出液中の成分からリコピンを分離し、紫外可視吸光光度検出器を用いて測定する高速液体クロマトグラフ法といった分析方法が一般的である。 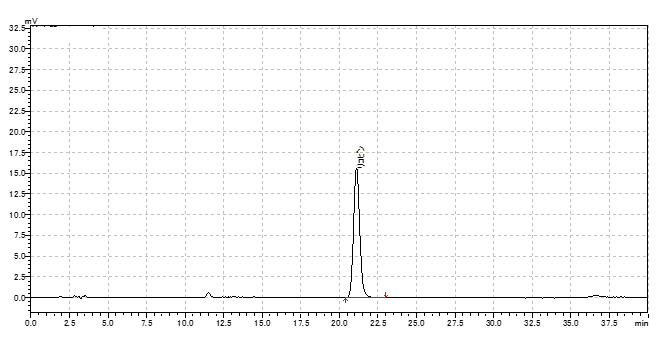 図2 トマト中のリコピンのクロマトグラム おわりにリコピンは様々な機能をもち、ルテインやβ-カロテンのように広範囲な種類の野菜・果物に豊富に認められるカロテノイドではないが、その供給源となるトマトやトマト加工品は入手しやすいだけでなく比較的長く貯蔵できるものが多いことから、日常的な摂取が容易な有効成分である。 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |
| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |

