|
母乳から見た有機ハロゲン化学物質
-長期モニタリング調査で分かったこと- 元大阪府立公衆衛生研究所
堀 伸二郎 はじめに近年、人々を取り巻く社会環境、生活環境は大きく変わってきており、それに伴い、環境の汚染や変化がヒトの健康などに悪影響を及ぼす可能性(=環境リスク)が増大しているのではないかという懸念がもたれている。なかでも、化学物質など環境中の有害物質が胎児および子どもの成長・発達にもたらす影響について、大きな関心を集めている。 1.有機塩素系化合物1)母乳中の有機塩素系化合物濃度2~4)1973年から2008年の大阪府在住の授乳婦(25~29歳の初産者のみ;各年19〜33名)より採取した母乳脂肪中有機塩素系化合物濃度の経年変化を図1に示した。 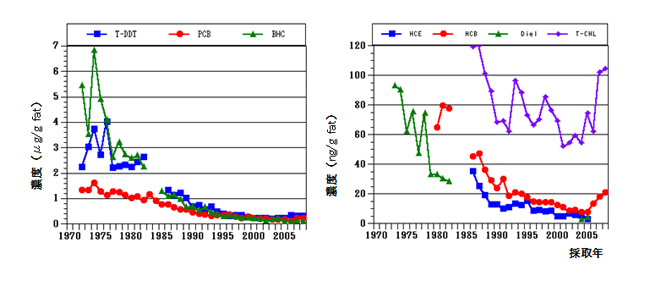 図1 母乳(大阪)中のPCB,有機塩素系農薬の濃度 1970年代の母乳脂肪中の有機塩素系化合物はBHC(HCH)、T-DDT(総DDT)、PCBの順で高い値であり、これに比べてDiel(ディルドリン)、T-CHL(総クロルデン)、HCE(ヘプタクロルエポキシド)およびHCB(ヘキサクロロベンゼン)は低い値であった。 2)母乳中の有機塩素系化合物の暴露評価5)乳児が母乳から摂取する有機塩素系化合物の量を評価する基準は見当たらない。そこであえて成人のADI(1日摂取許容量)を用い参考とした。1970年代は表1に示したごとく、これらの化合物はそれぞれのADIを越えていたが、現在(2000年代)はADI を下回っている(5〜46%)。 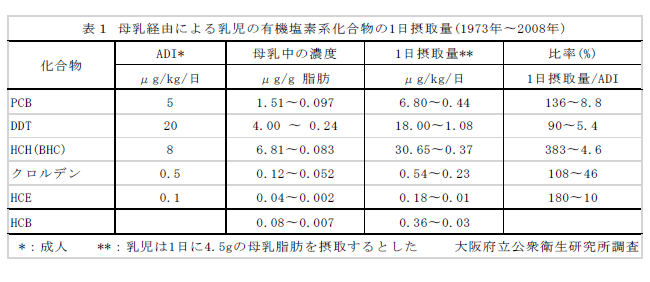 3)有機塩素系化合物の食事からの1日摂取量6,7)大阪府立公衆衛生研究所でマーケットバスケット方式で調製された、1977年〜2003年の大阪府民の食事からのPCB、T-DDT、T-HCH(BHC)等の有機塩素系化合物の1日摂取量を経年変化が分かるように図2に示した。 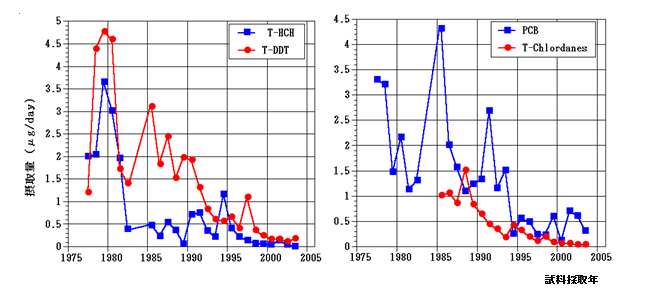 図2 食事(大阪)経由による有機塩素系化合物の1日摂取量(成人) 各化合物の経年変化については、1970~1980年代の最高値に比べて2003年は約1/20(PCB)、1/25(T-DDT)、1/50(T-CHL)、1/90(T-HCH)にそれぞれ減少していた。しかしいずれの化合物も、2000年以降の2〜3年では明らかな減少は見られず、低いレベルでの汚染が継続していた。 4)食事中の有機塩素系化合物の暴露評価5)表2から明らかなように、1977年~2003年の食事からのPCB、 T-DDT、T-HCHの1日摂取量は、それぞれ4.31〜0.11μg、4.77〜0.11μg、3.65〜0.04μgであったのに対し、T-クロルデンは1.51〜0.03μg、HCEは0.17〜0.00μg、HCBは0.90〜0.005μg、ディルドリンは0.49〜0.005μgというように低い値であった。アルドリンとエンドリンは、1988年以降分析しているが、すべての試料で定量限界(0.005μg)未満であった。 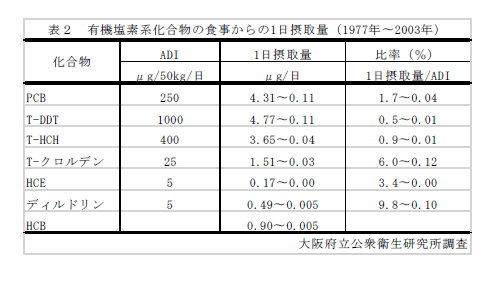 PCBの成人ADI(μg/50kg/日)は250μgである。PCB摂取量の最大値4.31μg(1985年)はADI値の1.7%であった。T-DDT摂取量の最大値4.77μg(1979年)はADI(1000μg)の0.5%であった。同様に、T-HCHは0.9%(1979年)、T-クロルデンは6.0%(1988年)、HCEは3.4%(1992年)、ディルドリンは9.8%(1992年)であった。したがって、全期間におけるPCB及び有機塩素系農薬の1日摂取量は、各化合物のADIをいずれも大きく下回っており、現時点では問題はなかったと考えられる。 2.ダイオキシン類1)母乳中のダイオキシン類濃度8,9,10)1994年及び1995年度報告によれば、日本における母乳中のダイオキシン類(T-PCDD :総ポリ塩化ジベンゾ-p-ジオキシン、T-PCDF:総ポリ塩化ジベンゾフラン、T-Co-PCB:総コプラナーPCB)の脂肪中濃度は平均26.6 pg-TEQ/g fatである。同時代のイギリス、ドイツ、カナダ等の先進国における母乳中のダイオキシン類濃度も同程度であり、日本を含めた先進国での母乳中のダイオキシン類濃度は同程度と考えられている。 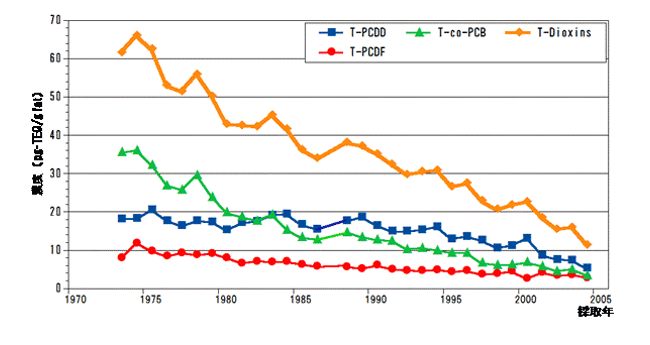 図3 母乳(大阪)中のダイオキシン類濃度 PCP(ペンタクロロフェノール:除草剤等)及びCNP(クロルニトロフェン:除草剤)を例に、環境中に放出(使用)された化学物質量とヒトの蓄積量を図4に示した。 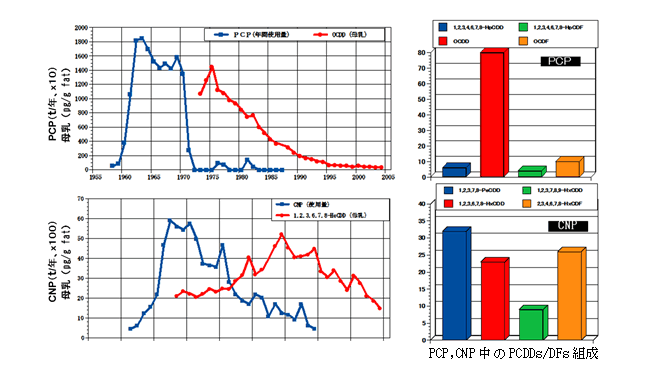 図4 母乳(大阪)中のPCDDs異性体濃度とPCP,CNP使用量(日本) 大阪府立公衆衛生研究所と益永等のデータを基に作成した PCP中には副生成物として1,2,3,4,6,7,8-Hp-CDD、1,2,3,4,6,7,8-Hp-CDF、OCDD、OCDFが含まれており、中でもOCDDが一番多く含まれている。PCPの年間使用量と母乳中のOCDD濃度を示したものが図4(左上)である。 2)ダイオキシン類の食事からの1日摂取量11)図5に大阪府下(2010年以降は関西地区)でマーケットバスケット方式で調製された食事からのダイオキシン類1日摂取量の経年変化を示した。 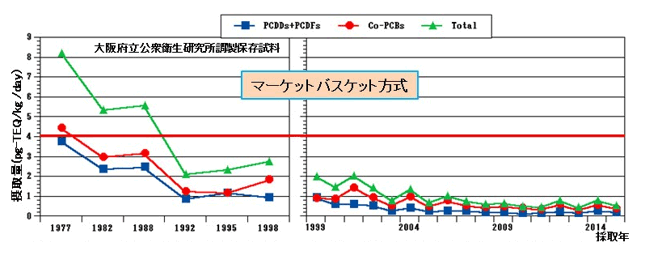 図5 大阪地区における食事中ダイオキシン類の経年変化(厚生労働省調査を基に作成した) ダイオキシン類1日摂取量は、経年的に減少傾向を示した。 3.大阪母乳中PBDEs (ポリ臭素化ジフェニルエーテル)13)臭素系難燃剤として使用されているPBDEsの3~6臭素化成分はヒトの母乳や魚、肉類、乳製品など幅広い食品群から検出されている。全般的にPenta-BDEの使用量が多い北米地域(アメリカ合衆国およびカナダ)の魚類から高濃度のPBDEsが検出される傾向にあるが、その他の地域においても、工業地帯や大都市近辺の閉鎖系水域に生息する食物連鎖上位の肉食魚などでは、高濃度の検出例がいくつか報告されている。 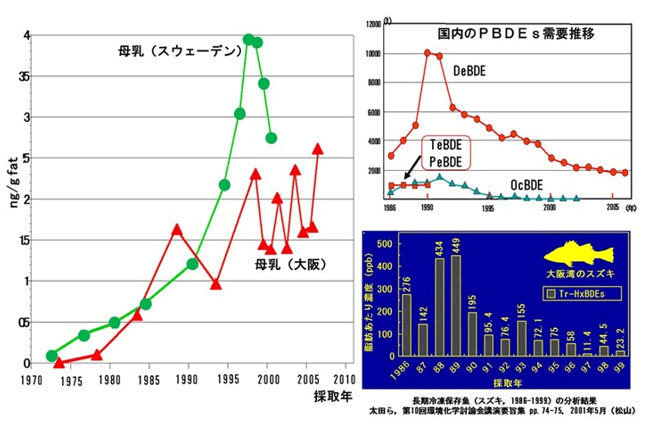 図6 母乳中PBDEs濃度の経年変化 2002年にミョーサ湖(ノルウェー最大の湖)で採取されたカワメンタイ(タラ科の淡水魚)からは、魚介類における現時点での最高報告値である、米国ヴァージニア州の野生のコイの汚染レベル(47,900 ng/g fat)に匹敵する7,066~45,144 ng/g fatの高濃度のPBDEsが検出されている。また、わが国では1998年に採取された東京湾のコノシロから280~440 ng/g fatのPBDEs(2~7、10臭素化物の合計)が検出されたとの報告がある。我々の調査では、瀬戸内海産の食用魚(1998年)における代表的な3~6臭素化物(BDE-28,47,99,100,153,154)の濃度は2.3~57 ng/g fatであり、養殖ハマチやボラで比較的濃度が高かった14)。 おわりに我々は1973~2008年まで36年間大阪府内在住、出産後1~3ヶ月の授乳婦を対象に、母乳中の残留性有機汚染物質(POPs)のモニタリング継続調査を行ってきた。また、これらの試料(母乳脂肪)は冷凍保存した。これと並行して、マーケットバスケット方式に基づくトータルダイエットスタディーも行ってきた。その結果、母乳中の有機塩素系化学物質濃度および成人に対するこれら化合物体内暴露量(1日摂取量)は経年的に減少していた。また、1日摂取量においては、調査期間(1970~2000年代)を通じてそれぞれの化合物のADIまたはTDIを下回っていることを明らかにした。 文献1 http://www.env.go.jp/chemi/ceh/ 2 井上 清、薬師寺 積、浜野 米一、村田 弘、渡辺 功、大阪府立公衛究所報 食品衛生編 第5号 19、昭和49年 3 Y.Konishi, K.Kuwabara, S.Hori, Arch. Environ. Contam. Toxicol., 40, 571(2001) 4 小西 良昌、柿本 建作、阿久津 和彦、尾花 裕孝、大阪府立公衛研所報、 47, 21(2009) 5 堀 伸二郎、食衛誌、51、373(2010) 6 K.Kuwabara, A.Harada, H.Matsumoto, S.Hori, Toxicological and Environmental Chemistry, 73, 93(1999) 7 桑原克義、松本比佐志、村上保行、堀伸二郎、食品衛生学雑誌、38、285-295(1997) 8 S.Hori, Organohalogen Compounds,13,65(1993) 9 S.Hori、Y.Konishi, K.Kuwabara, Organohalogen Compounds,141,65(1999) 10 小西良昌、田中 之雄、堀 伸二郎、多田 裕、環境化学、16、677(2006) 11 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kagaku/ 12 K.Akutsu, M.Kitagawa, H.Nakazawa, T.Makino,K.Iwazaki, H.Oda, S.Hori, Chemosphere, 53, 645(2003) 13 阿久津和彦、堀 伸二郎、食衛誌、45、175(2004)。 14 K.Akutsu, H.Obana,H.Okihashi, M.Kitagawa, H.Nakazawa, Y.Matsuki, T.Makino, H.Oda, S. Hori, Chemosphere,44,1325(2001) 15 S.Ohta, D.Ishizuka, H. Nishimura, T. Nakao, O. Aozasa, Y. Shimidzu, F. Ochiai, 16 D. Meirenyte, K. Noren, In:BFR 2001 Proceedings, May 14-16, Stockholm, Sweden, 2001, p.303-305 17 K. Akutsu, PBDEs in Human Milk, http://www.ee-net.ne.jp/ms/e-08/akutsu-090801.pdf ・ ダイオキシン類: PCDDs + PCDFs + Co-PCBsを示す。 ・ ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(Polychlorinated dibenzo-p-dioxins/PCDDs) ・ ポリ塩化ジベンゾフラン(Polychlorinated dibenzofurans/PCDFs) ・ コプラナーPCB(Coplanar polychlorinated biphenyls/Co-PCBs): PCDDs及びPCDFsと類似した生理作用を示す一群のポリ塩化ビフェニル(PCB)類。 ・ トータルダイエットスタディー: ヒトが通常の食生活において、食品を介して化学物質等の特定の物質がどの程度実際に摂取されるかを把握するための調査方法。トータルダイエットスタディーには、「マーケットバスケット方式」と「陰膳方式」の2種類あり、本調査では「マーケットバスケット方式」を採用している。 ・ マーケットバスケット方式: 広範囲の食品を小売店等で購入し、必要に応じて摂食する状態に加工・調理した後に分析し、食品群ごとの化学物質等の特定の物質の平均含有濃度を算出する。これに、特定の集団(例えばすべての日本人)におけるこの食品群の平均的な消費量を乗じることにより、食品群ごとに特定の物質の平均的な摂取量を推定する。この結果を全食品群について足し合わせることにより、この集団の特定の物質の平均的な摂取量を推定する。 ・ 陰膳方式: 調査対象者が食べた食事と全く同じものの1日分を食事試料とし、食事全体を一括して分析し、1日の食事中に含まれる化学物質の総量を測定する。これにより、調査対象者が食べた食品に由来する化学物質の摂取量を推定する。 ・ TEF(Toxic Equivalency Factor/毒性等価係数): ダイオキシン類は異性体により毒性の強さがそれぞれ異なっており、ダイオキシン類として全体の毒性を評価するためには、合計した影響を考えるための手段が必要であることから、最も毒性が強い2,3,7,8-TeCDDの毒性を1として他のダイオキシン類の仲間の毒性の強さを換算するための係数のこと。なお、今回は2005年にWHOで再評価されたTEFを用いている。 ・ TEQ(Toxic Equivalent/毒性等量): ダイオキシン類は通常、毒性強度が異なる異性体の混合物として環境中に存在するので、摂取したダイオキシン類の量は、各異性体の量にそれぞれのTEFを乗じた値を総和した毒性等量として表す。 ・ TDI(Tolerable Daily Intake/耐容1日摂取量): 長期にわたり体内に取り込むことにより健康影響が懸念される化学物質について、その量まではヒトが一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと判断される1日当たりの摂取量。 ・ ADI(acceptable daily intake/ 1 日摂取許容量): ヒトがある物質を毎日一生涯にわたって摂取し続けても、現在の科学的知見からみて健康への有害影響がないと推定される1日当たりの摂取量。 略歴堀 伸二郎(ホリ シンジロウ) 薬剤師 薬学博士(大阪大学) 著書 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |
| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |

