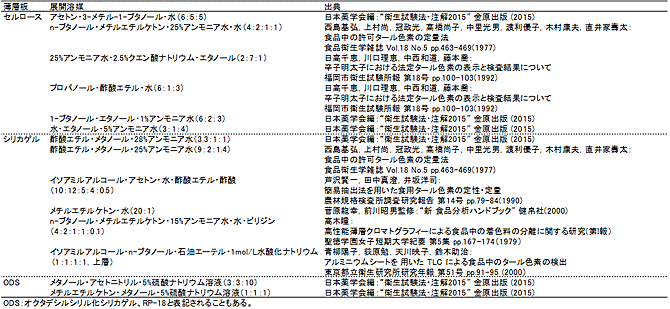|
食品に含まれる酸性タール色素の試験法
一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC
第一理化学検査室 はじめに食品の色は、食欲を左右する重要な要素である。赤いマグロの刺身はおいしそうに見えるが、褐色だと食欲はわかない。また、同じ料理を食べるとしても、彩りがある盛り付けのほうがよりおいしそうに感じる。“おいしそう”と感じさせる効果以外にも、“好奇心や楽しさ”を刺激する知育菓子などでは、色の鮮やかさや色の変化を付加価値としている。バナナの可食部は白いがバナナ味の食品では、バナナの皮と同じ黄色に着色されることでバナナ味の食品であることが見て想像できるようになる。食品への着色は栄養学的な観点でみれば不要かもしれないが、前述のように、食品の色に対して抱く印象が食品の価値を左右するため、着色料の存在は不可欠である。 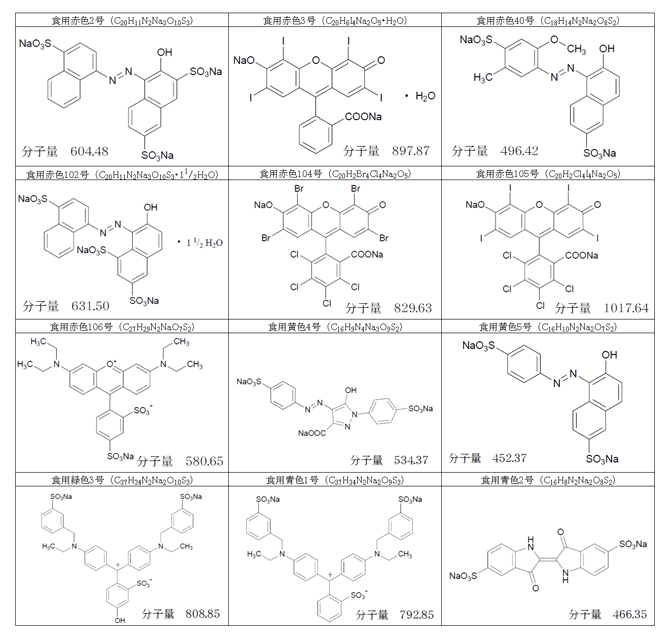 図1 各色素の構造式(第8版食品添加物公定書より引用) 表1 各色素の名称およびColor Index(C.I.) 等
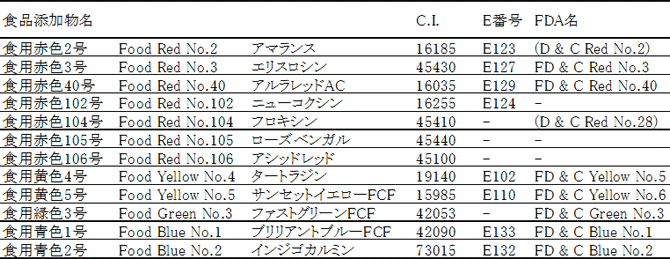 試験操作試験のフローチャートを図2に示す。まず、粉砕した試料に抽出溶媒を加えて加温抽出し、ろ過または遠心分離によって抽出液を得る。抽出液に酢酸を加えてpH3~4としたのち、ポリアミドを加え、ポリアミドに色素を吸着させる。上清を傾斜法やろ過等で捨てたのち、着色したポリアミドを水とメタノールを用いて洗浄する。吸着した色素をエタノール・アンモニア混液で溶出し、エバポレーター等を用いて濃縮した後、これを試験溶液とし、TLCにより定性を行う。 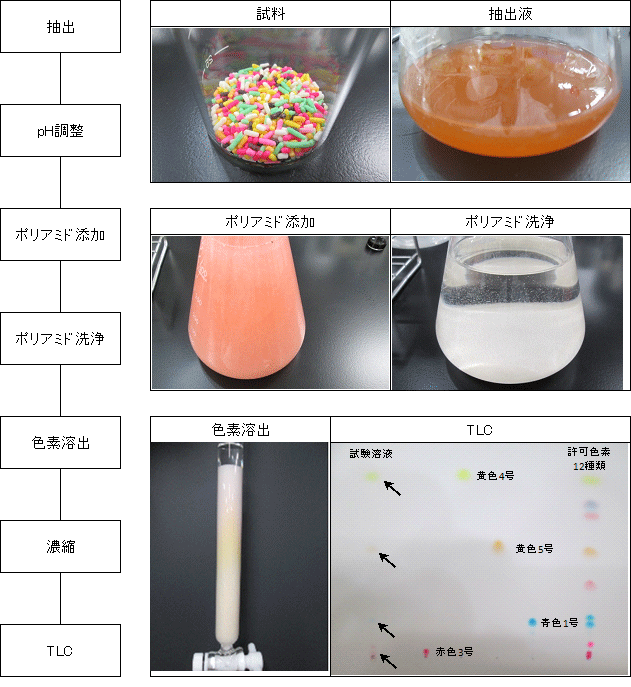 図2 試験のフローチャートと市販のチョコレートスプレーの試験の様子 最後に冒頭でも述べたように、食品の着色は必要なものと考えられるが、タール色素については安全性が疑問視され、使用禁止となるものが出現し、さらには消費者からも忌避されるようになってきた。それに伴い、天然色素が好まれるようになったものの、タール色素と比較して、着色に必要な添加量が多く、着色が不安定なものがあるなどの問題がある。また、天然物由来ということで安全なイメージがあるが毒性試験のデータが少ないものもある。一方、酸性タール色素については、厚生労働省のホームページより閲覧できる「マーケットバスケット方式による年齢層別食品添加物の一日摂取量の調査」に調査結果が公開されており、現在の摂取量であれば安全性上問題ないとされている。着色料の安全性に対する意見は肯定的なものもあれば否定的なものもあるため、得られる情報の正しさを判断することが大切である。 参考文献1) “第8版食品添加物公定書解説書” 廣川書店 (2007) 2) 日本薬学会編:“衛生試験法・注解2015” 金原出版 (2015) 3) 宮 武 ノリヱ,永 山 敏 廣:東京衛研年報,56,145-151,2005 4) 厚生労働省:マーケットバスケット方式による年齢層別食品添加物の一日摂取量の調査 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |
| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |