|
アフラトキシンM1について
一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC
第二理化学検査室 1.はじめにカビ毒はカビが産生する化学物質のうち、人や家畜に対して有害な影響を及ぼす物質であり、マイコトキシン(Mycotoxin)と呼ばれている。カビ毒の毒性は発がん性、肝毒性、腎毒性など、様々な毒性が報告されており、食品のカビ毒による汚染を防ぐことは食品衛生上の重要な課題である。国内においては一部のカビ毒に対して規制値が設定されている。アフラトキシンは平成23年10月1日より、総アフラトキシン(アフラトキシンB1、B2、G1、及びG2の総和)として、全食品に対して10 μg/kgの規制値が設定された。また、平成28年1月23日より、アフラトキシンM1は乳に対して0.5 μg/kgの規制値が設定された。(乳とは、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第2条第1項に規定するものをいう。) 2.アフラトキシンM1とはアフラトキシンM1は、アフラトキシンB1に汚染された飼料を摂取した家畜の体内において、アフラトキシンB1の代謝産物として生成される。アフラトキシンM1は体内において主に乳に移行することが知られているため、汚染リスクの高い乳に対して規制値が設定された。アフラトキシンM1は諸外国等においても規制又はガイドライン値が設定されている(表1)。アフラトキシンM1の汚染を低減するため、国内においては家畜に供する飼料に対して、アフラトキシンM1生成の要因となるアフラトキシンB1の指導基準及び管理基準を設定している。 表1. 諸外国等における食品中のアフラトキシンM1の規制又はガイドライン値
3.乳におけるアフラトキシンM1試験法乳を対象として通知された試験法のフローチャートを図1に示す。調製した試料をイムノアフィニティカラムにより精製後、HPLC-FL又はLC-MS(/MS)で定量する方法であり、試験法の定量限界は0.05 μg/kgに設定されている。試験法上の注意点にはアフラトキシンM1のガラス吸着について記載されており、分析時に使用する器具等に注意しなければならない。機器分析による定量法の他に、イムノクロマト法を用いた分析キットによるスクリーニング法が示されている。スクリーニング法では検出限界が100 ppt以下であることとされている。 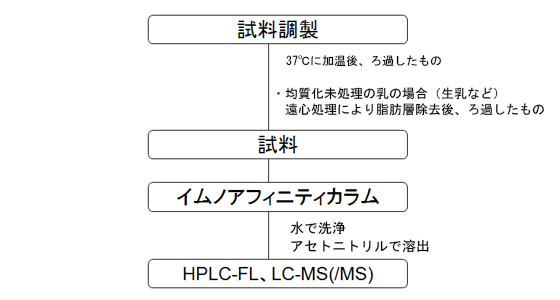 図1. 試験法のフローチャート 4.おわりにカビ毒は熱に耐性を有するため、一度汚染された食品からカビ毒を除去することは困難である。従って、未然に汚染を防ぐことが重要であるが、食品のカビ毒汚染はカビ毒産生菌による非意図的な汚染であるため、管理が難しく、汚染状況の確認には精度の高い分析法が必要となる。国内において基準値が設定されているカビ毒は一部であるため、今後もカビ毒の規制が進むと考えられる。 参考資料[1] 食安発0331第5号「アフラトキシンを含有する食品の取扱いについて」 [2] 食安発0723第1号「乳に含まれるアフラトキシンM1 の取扱いについて」 [3] 食安発0723第5号「乳に含まれるアフラトキシンM1 の試験法について」 [4] 食品安全委員会 かび毒評価書「乳中のアフラトキシンM1及び飼料中のアフラトキシンB1」 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |
| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |

