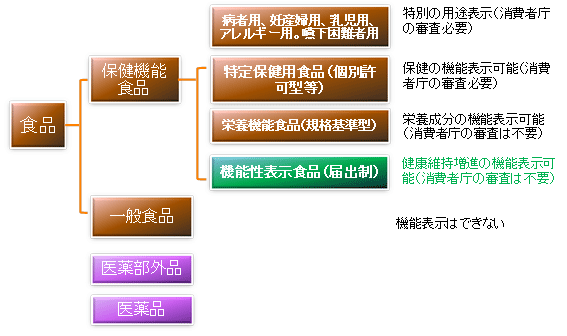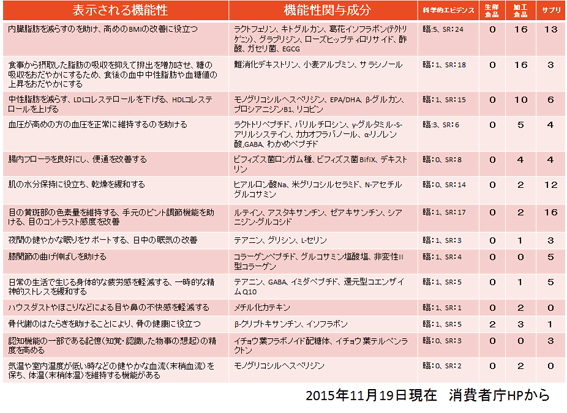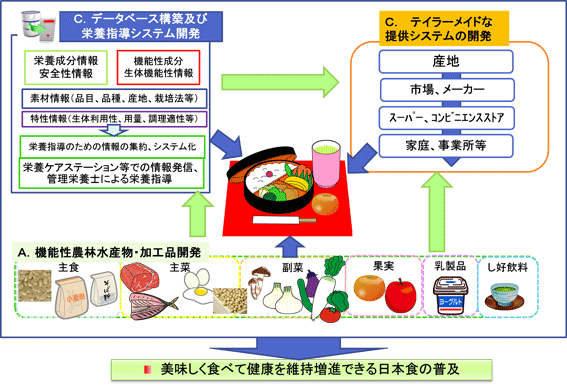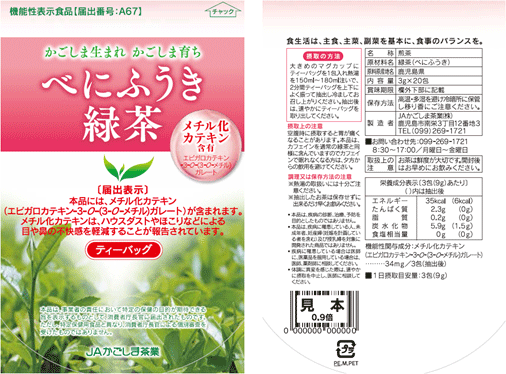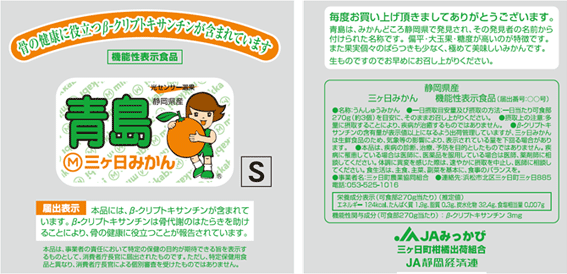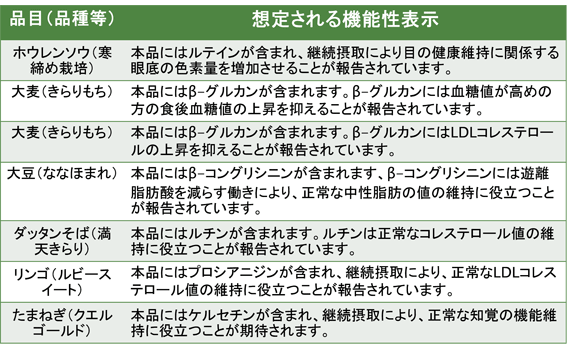|
新たな機能性表示制度における機能性農林水産物
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
食品総合研究所 食品機能研究領域長 山本(前田)万里 1.はじめに医食同源という言葉があるように、食品は健康の維持増進や疾病予防に大きな役割を果たしている。それを明らかにしてきたのが、食品機能性研究であり、農産物や食品の機能性研究においては、機能性成分の探索、同定、分析、エビデンス獲得、作用メカニズムの解析や機能性成分を多く含む農産物開発などを経て機能性食品が生み出されてきた。機能性を持った食品成分としては、食物繊維、ポリフェノール類、カロテノイド類が主要なものとされている。それらの研究成果としての機能性食品は、特定保健用食品として機能性が表示されて販売されるか、いわゆる健康食品として販売されている。新たな機能性表示制度の検討が規制改革の一環として消費者庁で実施され、2015年4月から、事業者が責任を持って自主的な機能性表示が可能とした制度(農林水産物も対象)がスタートした。「機能性表示食品」1)は、事業者の責任で、科学的根拠(臨床試験、研究レビュー)を基に商品パッケージに機能性を表示するものとして、消費者庁に届け出された食品であり、健常人や未病者の健康維持・増進に係る部位表現も範囲となった。農産物や低次加工食品の機能性表示も認められているので、現在、農研機構で実施している機能性農産物開発を含めて想定される機能性表示食品などを紹介したい。 2.従来の制度と新制度の特徴従来、日本で健康や栄養の表示が可能な食品は、特定保健用食品、栄養機能食品、特別用途食品であった(図1)2)。特定保健用食品は、からだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、おなかの調子を整えたりするのに役立つ、などの特定の保健の用途に資する旨を表示するものをさす。製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要がある。疾病リスク低減表示(規格基準型)では、カルシウム(骨粗鬆症予防)、葉酸(障害を持つ子供が生まれるリスクの低減)が認められている。
1) 国ではなく、その食品を販売しようとする事業者(農家も含む)が、自らの責任で、その科学的根拠を評価したうえで、その機能を包装表示できる。 2) 農林水産物、加工食品、サプリメントが対象である。 3) 栄養摂取基準のある栄養素や栄養機能食品、アルコール含有食品、塩分・糖分・飽和脂肪酸・コレステロールなどを過剰に摂取させる食品は対象外である。 4) 安全性の確保を前提として健常人や未病者の健康維持増進に係る食品の構造・機能表示が可能である。疾病に罹患していない方(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む。)及び授乳婦を除く。)を対象にした食品である。 5) 機能性表示のための科学的根拠は、その食品でヒトが介入した試験を実施するか、食品もしくは機能性関与成分での系統的な研究レビュー(システマティックレビュー)のどちらかで得る必要がある。 6) 本制度を活用するには所定の書類を販売60日前までに消費者庁へ届け出る必要がある。受理された場合、その情報は、事前に消費者庁のホームページで公開される。消費者が誤認することなく商品を選択できるよう適正な表示などによる情報提供が行われる。 7) 容器包装に表示されるのは、「機能性表示食品(届出番号)」、「届出表示」、「消費者庁が認可していない旨」、「栄養成分表示」、「1日当たりの摂取目安量」、「1日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分含有量」、「賞味期限」、「保存方法」、「摂取の方法」、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを」、「定められた文言を含む留意事項」、「製造者」、「お問い合わせ先」である。 なお、2015年11月19日現在、140品目の機能性表示食品が届出を受理されており、それらの機能性のカテゴリー、機能性関与成分、食品の種類を表1に示す。 表1 届出が受理された機能性表示食品(A142まで:2品目撤回) 3.事業者、消費者にとってのメリットと消費者に求められる判断力事業者(農家等生産者や販売者)にとっては、今まで機能性成分の含有量しか表示できなかったものが、部位(目、鼻、骨など)を示して機能性表示ができることや主観的なスコアでの効能実証による機能性表示ができるようになったことがメリットである。これは、より正しい情報を消費者に伝えられるということで、農産物や加工食品の付加価値を向上させるためのメリットになりうる。しかし、届出制ということで、安全性や機能性(ヒト試験による効果の実証、作用機序の考察)の評価を厳しく行わなくてはならないこと、農林水産物の場合は1日で摂取できる分量の中に機能性が見込める機能性関与成分量を担保するとともにバラツキを抑えるように栽培、加工、流通面で管理しなければいけないこと6)、それに伴い機能性関与成分のモニタリングのための定期的な分析が必要なこと、健康被害情報を集める体制を組まなければいけないことなどが事業者に求められている。一方、消費者にとっては、消費者庁にたくさんの届出情報が開示されているためより正しい情報が得られるというメリットがあり、商品選択の機会が増える。ただし、特定保健用食品や栄養機能食品などとの違いを見分け、たくさんの情報から自分にとって必要な食品を選択する「能力やセンス」が求められてくる。今後は、セルフメディケーションと深く関わる食に関する教育を幼児期から系統的に行う必要があると考えられる。 4.農産物の機能性を巡る現状機能性成分を多く含む農産物については、民間種苗会社や独法等で開発されてきた。表2は、農研機構で今までに育成されてきた機能性成分高含有農作物の例7)を示している。ここに示すように、食物繊維、ポリフェノール、カロテノイド、リグナン、ビタミンなどの含有量を従来の品種より高めた品種が育成され、これらを活用した製品開発もいくつか行われてきた。 表2 農研機構で育成された機能性成分高含有農作物
5.機能性農林水産物・食品開発プロジェクト2013度から農研機構主体の機能性農林水産物・食品開発プロジェクトが実施されている8)。このプロジェクトでは、国立研究開発法人、公設試験研究機関、大学、民間企業等との連携により、健康上のリスク低減等に効果が期待される農林水産物やその加工品の開発及びそれらの生産・流通技術の確立を行うとともに、医療機関等との連携により、農林水産物やその加工品について、疾病リスク低減への影響評価や、栄養・健康機能性、安全性、特性情報等を盛り込んだ農林水産物データベースの構築、個人の健康状態に応じたテーラーメイドな提供システム・栄養指導システムの開発を行うことになっている。以下がその概要である。 1) 国ではなく、その食品を販売しようとする事業者(農家も含む)が、自らの責任で、その科学的根拠を評価したうえで、その機能を包装表示できる。 2) 農林水産物やその加工品を対象として、今後活用が有望と考えられる新たな健康機能性に関する基礎的研究を行う。例えば、日常のストレスを軽減する効果のある農林水産物やその加工品の開発、丈夫な体を作る効果のある農林水産物やその加工品の開発、今までにはない新しい機能性評価手法や機能性成分分析法の開発などを行う。 3) 医療機関等との連携により、上記で開発された農林水産物やその加工品について、健康への影響評価や個人の健康状態に応じたテーラーメイドな供給システムの開発を行う。この中には、収集された情報の有効活用を図るため、機能性を持つ農林水産物及びその加工品の評価情報(機能性を持つ農林水産物の主な栄養・機能性情報、産地・栽培方法・調理等加工特性・機能性成分の含有量(分析法も含まれる)・機能性成分の生体利用性等の特性情報、エビデンスに関する文献情報(有効性判定)、安全性に関する情報、参考情報など)を収載した「健康に寄与する農林水産物データベース」の構築、地域において栄養指導を実施する栄養ケアステーションを設置し、管理栄養士が個人の健康状態と食生活を簡易に診断し、機能性農林水産物・食品を使用したレシピ開発などを行うとともに、機能性農林水産物・食品を活用して生活習慣病の予防や栄養改善に資する食生活を提案するシステムの構築などが含まれる(図2)。 本プロジェクトでは、特にエビデンスに基づく機能性農林水産物の開発を目指しており、今回、ヒト介入試験(無作為割付プラセボ対照群間比較試験)を行って、効果を検証しようとしている農作物は、高アミロース米、アミロペクチンロングチェーン米、表面加工玄米、β-グルカン高含有大麦、全粒小麦、高タンパク大豆、ルチン高含有ダッタンソバ、高リコピンニンジン、高ルテインケール、ゴーヤ、ケルセチン高含有タマネギ、β-クリプトキサンチン高含有カンキツ、高カテキン緑茶である。
6.機能性表示農産物前述のように、農研機構では今までに、いくつかの農産物について機能性の評価を行ってきた。1つは緑茶で、アレルギー鼻炎有症者にメチル化カテキンを多く含有する「べにふうき」緑茶とメチル化カテキンを含まない「やぶきた」緑茶を飲用させて、「べにふうき」緑茶で有意に目や鼻の症状の悪化が抑制された9-11)。この結果を利用して「べにふうき」緑茶ティーバッグ(A67:図3)12)及び「べにふうき」緑茶ペット飲料(A69)12)が機能性表示食品として消費者庁にすでに受理されている(機能性表示:メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減することが報告されている)。機能性関与成分はメチル化カテキン(エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル)ガレート)であり、マスト細胞や好塩基球でのチロシンキナーゼ抑制やカテキン受容体を介した情報伝達系の阻害によりヒスタミン遊離が抑制されることが作用メカニズムである13-15)と考察している。緑茶カテキンでは、メチル化カテキンのLDLコレステロール低下効果(後述の機能性食品開発プロジェクト)があり、その他、エピガロカテキンガレートの血圧上昇抑制効果、エピガロカテキンの免疫賦活作用などが、今後の機能性表示食品のターゲットとなり得ると考えている。また、2003年度から浜松市(旧三ヶ日町)と合同で行ってきた栄養疫学調査(「三ヶ日町研究」)で、ウンシュウミカンなどの果物や野菜に含まれるカロテノイド類と健康状態との関連を経時的に調査してきた。その中で、ウンシュウミカンをよく食べ(機能性関与成分であるβ-クリプトキサンチンで1日3-4mg)、閉経女性での骨粗鬆症のリスク16)、アルコール飲用者でのγ-GPT値の上昇リスク17)、血中のβ-クリプトキサンチン濃度の高い人では動脈硬化のリスク18)、喫煙者におけるメタボのリスク19)、インスリン抵抗性のリスク20)が低いことが明らかにされた。これらの成果を活用して、飲料メーカーから、β-クリプトキサンチンをウンシュウミカン3個分含んだ飲料が上市された。特に、長期コホート研究14)を基にウンシュウミカン(A79:図4)21)が初めての生鮮食品として受理された(機能性表示:本品には、β-クリプトキサンチンが含まれています。β-クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康に役立つことが報告されています)。
表3 農林水産物で今後上市が想定される機能性表示
7.おわりに機能性農産物の研究については、今後、ヒトレベルでの有効性の検証及び機能性成分を多く含む品種の育成、最適な加工・調理法の開発などを行う必要がある。農林水産物の場合は、機能性関与成分のバラツキをできるだけ少なくするような品質管理システムの開発が重要となる。機能性農産物の付加価値を高め、健康維持増進に活かしていくために、ここで説明した新たな機能性表示制度を活用できるような支援体制も整えていくことが重要である。また、今後は、単に三次機能やその有効成分だけの研究を行うのではなく、栄養成分、嗜好成分についても同時に考慮した栄養・健康機能を総合的に考えた農林水産物・食品の開発が重要であると考えている。できるだけ多くの、エビデンスがしっかりと検証された農林水産物が広く市場に出回り、国民の健康維持・増進、健康寿命延伸に寄与することを期待している。 参考文献1) 機能性表示食品に関する情報(消費者庁):http://www.caa.go.jp/foods/index23.html 2) 栄養と健康に関する表示について(消費者庁):http://www.caa.go.jp/foods/ 3) 諸外国の機能性表示制度(消費者庁): 4) 規制改革実施計画(内閣府): 5) 食品の新たな機能性表示制度に関する検討会(消費者庁):http://www.caa.go.jp/foods/index19.html 6) 農林水産物の機能性表示に向けた技術的対応について(農水省): 7) 農研機構品種2012: 8) 機能性を持つ農林水産物・食品開発プロジェクト(農研機構): 9) 安江正明ら:通年性アレルギー性鼻炎患者を対象とした「べにふうき」緑茶の抗アレルギー作用並びに安全性評価、日本臨床栄養学会誌, 27(1),33-51(2005) 10) 安江正明ら:「べにふうき」緑茶の抗アレルギー作用並びに安全性評価:軽症から中等症の通年性アレルギー性鼻炎患者、並びに健常者を対象として、日本食品新素材研究会誌, 8(2),65-80(2005) 11) S. Masuda et al.:‘Benifuuki’ green tea containing O-methylated catechin reduces symptoms of Japanese cedar pollinosis: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial, Allergology International, 63:211-217(2014) 12) 届出詳細情報(消費者庁):http://www.caa.go.jp/foods/todoke_51-75.html 13) M. Maeda-Yamamoto et al.: O-methylated catechins from tea leaves inhibit multiple protein kinases in mast cells. Journal of Immunology, 172: 4486-4492 (2004) 14) Y. Fujimura et al.: Antiallergic Tea Catechin, (-)-Epigallocatechin-3-O-(3-O-methyl)-gallate, Suppresses FcepsilonRI Expression in Human Basophilic KU812 Cells. J. Agric. Food Chem., 50: 5729-5734 (2002) 15) Y. Fujimura et al.: The 67kDa laminin receptor as a primary determinant of anti-allergic effects of O-methylated EGCG. Biochemical and Biophysical Research Communications, 364: 79-85(2007) 16) M. Sugiura et al.:High Serum Carotenoids Associated with Lower Risk for Bone Loss and Osteoporosis in Post-Menopausal Japanese Female Subjects: Prospective Cohort Study, PLOS ONE,7(12):e52643 (2012) 17) M. Sugiura et al.: High serum carotenoids are inversely associated with serum gamma-glutamyltransferase in alcohol drinkers within normal liver function. J Epidemiol, 15:180-186 (2005) 18) M. Nakamura et al.: High beta-carotene and beta-cryptoxanthin are associated with low pulse wave velocity. Atherosclerosis, 184: 363-369 (2006) 19) M. Sugiura et al.: Associations of serum carotenoid concentrations with the metabolic syndrome: interaction with smoking. Br J Nutr, 100: 1297-1306 (2008) 20) M. Sugiura et al.: The homeostasis model assessment-insulin resistance index is inversely associated with serum carotenoids in non-diabetic subjects. J Epidemiol, 16: 71-78 (2006) 21) 届出詳細情報(消費者庁):http://www.caa.go.jp/foods/todoke_76-100.html 22) 農産物の有する機能性やその関与成分に関する知見の収集・評価(農水省): 略歴
学位取得平成4年9月九州大学農学博士「食品成分の抗体産生調節に関する研究」 学会賞等
日本茶インストラクター4期生(04-0933) 【研究内容】 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |
| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |