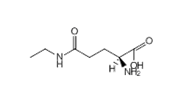|
テアニンについて
一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC
第一理化学検査室 2015年4月1日、食品表示法が施行され、あらたに機能性表示食品制度が導入されました。これまでは、食品に含有されている栄養成分の生理機能を表示できる制度は、国が個別に許可した特定保健用食品(トクホ)と、国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られていましたが、今回新制度ができたことにより、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能をもつ栄養成分(機能性成分)について、表示することが可能になりました。 テアニンとはテアニン(L-Theanine) テアニンはアミノ酸の一種であるグルタミン酸の誘導体であり、緑茶や紅茶、特に玉露のような高級な「お茶」に多く含まれています。その含量は、お茶に含まれるアミノ酸の中で最も多く、お茶の代表的な旨み成分の1つです。お茶の主成分は、苦みの成分であるカフェイン、渋みの成分であるカテキン類、そして甘み旨みの成分であるテアニンです。テアニンは一番茶(新茶)のように初期の若い芽に多く含まれ、二番茶、三番茶と成熟した葉では極端に少なくなります。また、玉露のように日光を遮って栽培すると、テアニンからカテキンの生成が抑えられるため、茶葉中にテアニンを豊富に含んだままの状態になります。逆に言えば、高級茶ほどカテキン含量は少なくなります。よって新茶や玉露にはテアニンが多く含まれ、旨味の多い味わいとなることが報告されています。 テアニンの働きお茶を飲むと気持ちがゆったりとして、リラックスした気分にさせてくれます。お茶には神経を高揚させる働きのあるカフェインが含まれているにも関わらず、気持ちが落ち着くのは、お茶に含まれるテアニンの作用であるといわれています。その原因は、カフェインとテアニンの同時摂取により、カフェインによる興奮作用が抑制されるからであると報告されています。 テアニンの分析方法テアニンは食品添加物としても使用が許可されています。食品中のテアニンを分析する方法として、現在では様々な分析方法が報告されていますが、その中の主要な方法の一つが、他のアミノ酸と同様にアミノ酸自動分析計を用いた液体クロマトグラフ法です。その他にも、トリメチルシリル化し、水素イオン化型検出器付ガスクロマトグラフ(GC-FID)で分析する方法や、細管式等速電気誘導法等の分析方法も知られています。 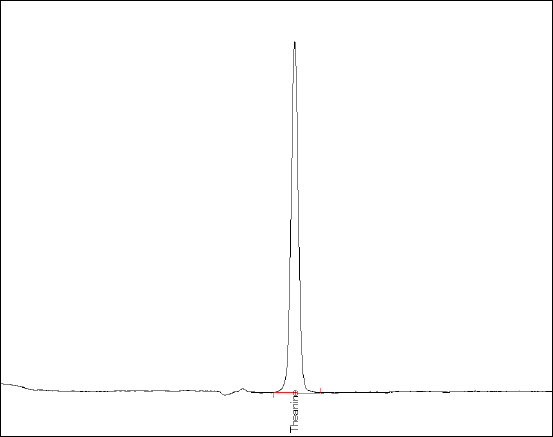 図1 アミノ酸自動分析計を用いたテアニンのクロマトグラム まとめ日常摂取する食品中には、タンパク質合成に利用される約20種類のアミノ酸以外にも多くのアミノ酸が含まれており、これらのアミノ酸は栄養効果が明確にされていないため、ほとんどは研究がされていません。その中でテアニンは様々な機能を有しており、さらなる研究が続けられています。今後も研究、実験によってテアニンの機能が解明されるに伴い、ますます注目があつまる成分と考えられます。 参考文献食品衛生検査指針 食品添加物編2003 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |
| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |