|
���H�H�i���ɍ��Z�x�܂܂��_�̐v�����o�@�ɂ���
��ʍ��c�@�l�@�H�i���͊J���Z���^�[SUNATEC
����w������ ����20(2008)�N1���ɔ��������������Ⓚ�L�q�ɂ��L�@�����n�_�^�~�h�z�X�ɂ�钆�Ŏ����A����25�N12���ɔ��������Ⓚ�H�i�_�������ȂǁA�ߔN�H�i�̈��S���Ɋւ����肪�����N������Ă���B�H�i�̈��S���ɑ���S�̍��܂��w�i�ɁA����25(2013)�N3��26���t���̎����A���ɂ��w���H�H�i���ɍ��Z�x�Ɋ܂܂��_�̐v�����o�@�ɂ��āx���������ꂽ�B�{�e�ł́A���̐v�����o�@�̊T�v�ɂ��ĉ������B �v�����o�@�̖ړI�{�v�����o�@�́A���N��Q�̖h�~�̊ϓ_����A���H�H�i���ɍ��Z�x�Ɋ܂܂��_���ȕւ��v���Ɍ��o���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��ĊJ�����ꂽ���̂ł���B �����Ώۉ��������N��Q�h�~�̊ϓ_����A�Ő��A���o���ᓙ���l�����Ĉȉ���1�`6�Ɏ����_��ΏۂɌ������ꂽ�B
* �}���Q�Ɨp��(ARfD:Accute Reference Dose) �v�����o�@�̒��ӓ_�v�����o�@�̓K�p�ɂ������Ă͒��ӓ_���\���ɗ�������K�v������B��Ȓ��ӓ_���ȉ��Ɏ������B
���o�@��������H�i��Ώ۔_��ɉ�����3��ނ̌��o�@���f�ڂ���Ă���B �@ �v�����o�@-1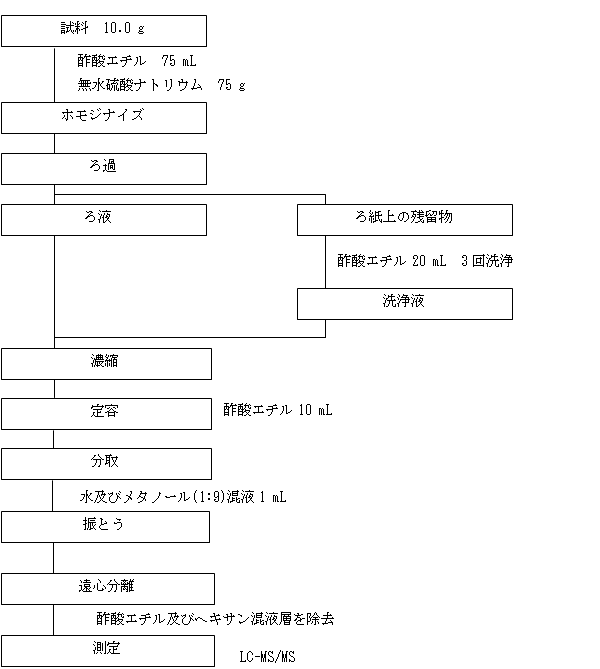
�A �v�����o�@-2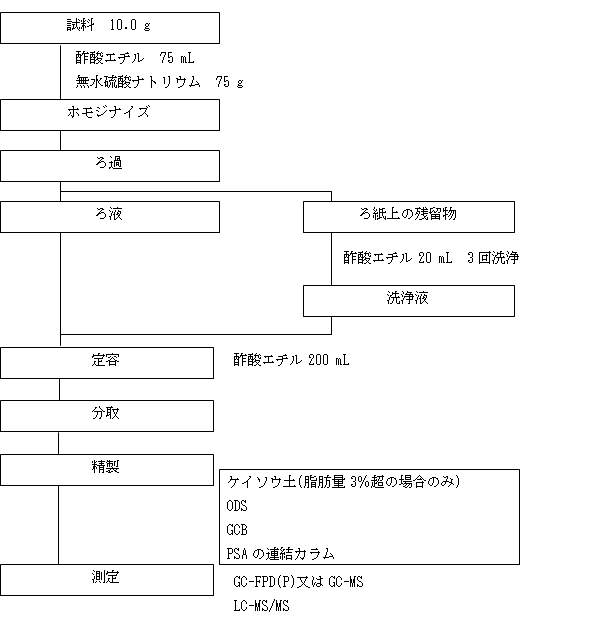
�B �v�����o�@-3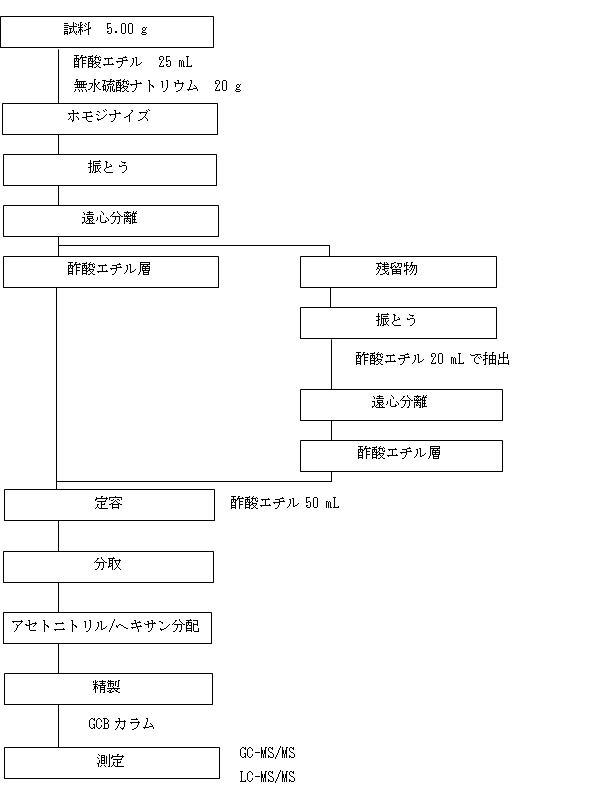
�v�����o�@�̕]���Z�x�{�v�����o�@�ł́A��ߐ��̐ێ�ɑ�����S�]����ł���}���Q�Ɨp�ʂ�p���ĕ]���Z�x�����肵�Ă���B�]���Z�x�̐ݒ�ɂ�����A�}���Q�Ɨp�ʂ�������Ă���_��̒��ōł������Ȓl�ł���g���A�]�z�X�̋}���Q�Ɨp��(0.001 mg/kg�̏d/��)���p�����Ă���A�]���Z�x��0.1 mg/kg�ɐݒ肳��Ă���B�]���Z�x�̎Z�o���ȉ��Ɏ������B �E�]���Z�x�̎��Z [0.001 mg/kg�̏d]�~[�̏d20 kg]��[�ێ��0.2 kg]��0.1 mg/kg �Ȃ��A�Ώۉ������̓Ő����ɉ����đΏۉ��������ɁA�]���Z�x��ύX���邱�Ƃ��\�����A���̏ꍇ�ɂ́A�ύX���悤�Ƃ���_��Ő��\�]�������{���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ���o�@���\�]���c����l�ւ̓K�������ړI�Ƃ��������@�̏ꍇ�A�����@�̑Ó����]���̕��@�́A�u�H�i���Ɏc������_�Ɋւ��鎎���@�̑Ó����]���K�C�h���C���v�Ɏ����ꂽ�菇�ɏ]���K�v������B�Ó����]���K�C�h���C���ł͕]���Z�x��0.01�`0.1ppm�ȓ��̏ꍇ�A�^�x(�����)70�`120���A���s���x(RSD)15���ȉ����ڕW�l�ƂȂ�B�������A�{�v�����o�@�̐��\�]���ɂ��ẮA�^�x(�����)50�`200���A���s���x(RSD)30���ȉ����ڕW�l�Ƃ���Ă���A���\�]�������Ó����]���K�C�h���C�������傫���ݒ肳��Ă���B�]���āA���ӓ_�ł��q�ׂ��ʂ�A�c����l�ւ̓K�������ړI�Ƃ��������ɂ͓K�p�ł��Ȃ��B �܂Ƃ��{�v�����o�@�ł́A�v�����y�ъȈՐ���D�悵�Ă��邽�߁A�K�������X�̔_�ɑ��ēK�������o�����ƂȂ��Ă��Ȃ��ꍇ������B�]���āA�Ó����]���K�C�h���C���ɏ]���đÓ����]�����������{���A���̖ڕW�l�������ꍇ�ł����Ă��A�c����l�ւ̓K�������ړI�Ƃ��������ɂ͓K�p�ł��Ȃ��Ƃ���̂Œ��ӂ��K�v�ł���B �Q�l�����w���H�H�i���ɍ��Z�x�Ɋ܂܂��_�̐v�����o�@�ɂ��āx�i�����J���Ȏ����A���@����25�N3��26���t�j �H�i�̈��S���Ɋւ���p��W(��4��)�@����20�N10���@�H�i���S�ψ��� �w�H�i���Ɏc������_�Ɋւ��鎎���@�̑Ó����]���K�C�h���C���x(�����J���Ȓʒm�@����22�N12��24���t�H����1224��1���ʓY) �c���_�͒m���Ă��������ⓚ���ꂱ��@����3��2012�@���{�_��w�� �T�i�e�b�N���[���}�K�W���ւ̂��ӌ��E�����z���qe-magazine@mac.or.jp�r�܂ł����������B |
| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |

