|
微生物定量法によるビタミン分析
一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC
微生物検査室 1 はじめに栄養表示基準においてビタミン類の表示値は、ビタミンA,D,Eを除いて表示の-20~+80%の範囲内であることが必須であり、その分析方法は、微生物の生育度を指標とした微生物定量法とHPLC(高速液体クロマトグラフィー)を用いた理化学定量法(HPLC法)がある。これらの分析方法にはそれぞれ特徴があり、今回は微生物を用いた微生物定量法について詳しく紹介する。 2 微生物定量法とはビタミンを必須の栄養素として要求する微生物の栄養要求特性を利用して、試料中のビタミン含量を測定する方法である。 3 微生物定量法の原理微生物の増殖に必要なすべての栄養素を含む培地から、定量したいビタミンのみを除くと、そのビタミンを合成できない微生物は生育できないが、目的のビタミンが存在すれば微生物は生育できる。微生物の生育量は一定の範囲内であればビタミンの濃度に比例するため、その範囲に合わせて、試料を希釈し培地を添加して培養を行う。 4 微生物定量法の特徴(長所、短所)
5 使用菌株、培養温度及び培養時間ビタミンの種類によって、使用菌株、培養温度及び培養時間が異なる。 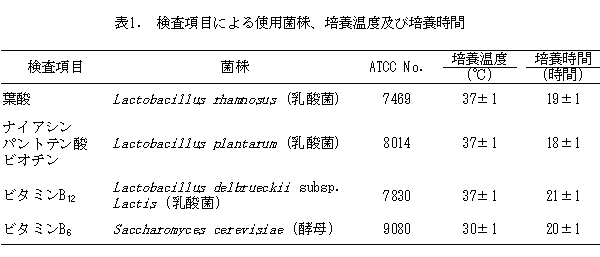 6 検査方法微生物定量法の一例としてナイアシンの検査フローを図1に示す。 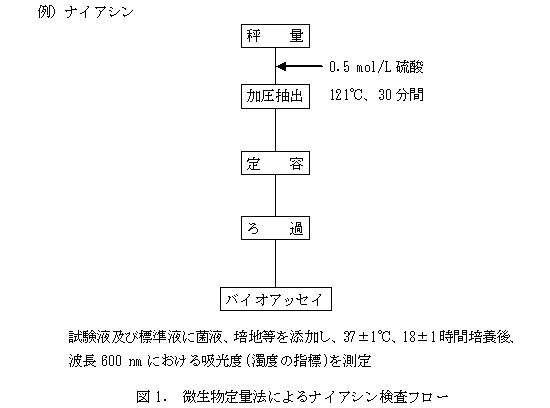 7 まとめ微生物定量法によるビタミン分析は、微生物を指標としているため、使用する微生物の活性が試験結果に大きな影響を及ぼす。使用する微生物の活性が良くないと、結果が安定しない。また逆に活性が良すぎる場合も試験結果がばらつく要因のひとつになる。そのため、使用する微生物の活性を、ほぼ一定に保つことがこの検査の鍵となる。 参考文献四訂 早分かり栄養表示基準 解説とQ&A 荘村明彦 中央法規出版 2011年5月20日 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |
| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |

