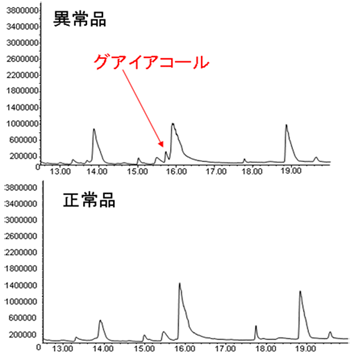|
微生物の接種試験について
7月号から掲載してきた本シリーズですが、今月号で最後となりました。これまで、食中毒菌、衛生指標菌といった微生物検査、そして微生物の詳細を知るための微生物同定検査を紹介しました。最後は、このようにして調べた微生物を実際に食品に接種し、傾向を分析する微生物の接種試験について説明します。 1 微生物の接種試験とは? 食品と微生物は、切っても切れないとても密接な関係にあります。食品では、ヒトにとって微生物の働きが有益であった場合「発酵」、有害であった場合「腐敗」と呼んでいます。このように、微生物の働きが同様であっても、ヒトにとってどうであるかの違いよって、見方も大きく変わります。すなわち、我々にとって食品における微生物のコントロール(制御)がとても重要ということになります。目的の微生物は増殖させ、それ以外の微生物は増殖させないことが必要です。ここで役に立つのが「微生物の接種試験」です。目的の食品に微生物を接種し、所定の温度及び時間保存後、食品に対してどのような影響がもたらせるかについて検証することが出来ます。
2 検査目的 微生物の接種試験といっても、どのような目的で行うか想像がつきにくいと思います。品質劣化によるクレームが発生した場合、食品では微生物が関与していることも多く、衛生指標菌や食品の種類を考慮した食中毒菌について微生物検査を行うケースが一般的です。ここで、原因究明及び再発防止に役立つのが前月号で取り上げた微生物の同定検査と今回紹介する「微生物の接種試験」です。微生物の同定検査で同定された原因菌を実際に食品に接種することで、再現性を確認することが出来ます。例えば、緑色に変色した食肉が社内で保管中に発見されたとします。文献調査やネット検索等を通じて、緑変の原因が微生物である可能性が想定された場合、まず要因とされる微生物の特性を考慮した微生物検査を行います。検査の結果、正常部分と比較して緑変部分の方が明らかに菌数が高かったもの、または緑変部分のみ発育が認められたものについて、微生物の同定検査を行います。同定された微生物について変色の要因となるか否かを精査した上で、緑変をもたらす可能性が考えられる微生物を食肉に接種し、同様の事象が再現されるか否かを確認します。保存試験を開始して数日後、微生物を接種した食肉に緑変が確認されたことから、接種した微生物が原因菌であると特定されました。
その他にも、食品特有のクレーム原因となる可能性がある微生物を接種してリスク管理に応用することが可能です。 3 試験方法 微生物の接種試験は、特に定められた方法はありません。したがって、お客様のご要望、目的に応じて接種する微生物、食品を自由に選択することが可能です。試験の概要は、接種したい微生物を一定の菌数に合わせ、接種します。この時、接種する菌液の量は、食品の状態をできるだけ変えないようにするため、できるだけ少量にすることが望ましいです。菌液を接種後、所定の温度、期間保存し、食品そのものに変化(例えば、変色、異臭の有無、カビ発育の有無、膨張、ネト発生など)、また接種した微生物の経時的変化を適切な方法で測定します。
4 応用例
ここでは、前月号と同様に品質劣化によるクレームが起こった場合の微生物の接種試験を用いた解決への一例を紹介します。
〜薬品臭がするゼリー〜
テスト製造したゼリーから薬品臭がするという官能評価の結果が得られため、本製造を前に至急原因を特定する必要があるとします。まずは、薬品臭がするということから、異臭品と正常品を比較する臭気分析を行い、異臭品からのみ検出される臭気成分を特定します。臭気分析の結果、グアイアコールが検出されました。(図1参照)グアイアコールは、耐熱性好酸性菌が産生することが知られているため、耐熱性好酸性菌について微生物検査を行った結果、異臭品からのみ耐熱性好酸性菌が検出されました。また、微生物検査で得られた培養物について遺伝子解析手法による微生物の同定試験を行った結果、Alicyclobacillus acidoterrestris (AAT)であると同定されました。そこで、同定されたAATを正常品に接種し保存試験を行った結果、異常品と同様の異臭が確認されました。
以上の結果から、AATが混入、増殖したため異臭を発したと原因が特定されました。原因特定に続き、再発防止に向けて現場調査を行います。原料別、工程別に製造現場をくまなく調査、必要に応じて微生物検査を行います。その結果、原料果汁から原因菌(AAT)が検出されました。原材料規格の見直しや殺菌条件の変更、作業後の清掃作業の見直しを行います。効果検証も含めて再度製造現場の衛生調査を実施した結果、AATは、検出されなかったことから、再発防止策の有効性も合わせて確認されました。
6 まとめ 6回に渡って掲載してきた本シリーズでは、食品衛生の自主管理から、品質劣化によるクレーム時の分析まで、幅広い微生物検査を説明しました。弊センターでは、今回紹介出来なかった検査以外にも、微生物に関わる様々な検査、コンサルティング業務も行っておりますので、是非ご利用ください。
参考文献
食品微生物の科学 ( 清水 潮 著 )
食品の保全と微生物 ( 藤井 建夫 編 ) 耐熱性好酸性菌統一検査法ハンドブック ( 一般社団法人 日本果汁協会 ) サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |
| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |