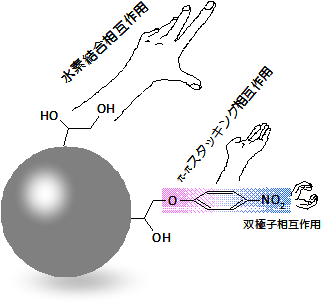|
残留農薬分析に適した高選択性吸着剤開発の可能性
中部大学応用生物学部
山本 敦、三輪 俊夫 1.はじめに 試料前処理に適用される数ある手法の中でも固相抽出(SPE; Solid-Phase Extraction)法はこの四半世紀の中で最も進化を遂げた手法といっても過言ではない。SPEはカラムクロマトグラフィーの一種で,液‐液抽出法と比較して環境負荷が小さく,また自動化しやすいというメリットを有していることから,近年の残留農薬分析に欠かせない前処理手法としてすでに確立されている。この手法に用いられるミニカラム用充てん剤は一般にSPE剤と呼ばれ,国内外問わずあらゆるメーカーが多種多様なSPE剤を取り揃えていることは承知のとおりである。特にC18やシリカゲル,Waters社のOasisシリーズなどはSPE剤の代名詞的存在である。これらは共通して溶質が有する“極性”の差異に基づいた分離特性を発揮することから,ユーザ視点で考えれば比較的扱いやすいともいえる。
さて,我々は被検農薬成分及びそれが溶解している溶媒に適するSPE剤を選択し精製を試みようとするのだが,ふと現行の通知試験法や公定試験法,あるいは報告されている論文などに記載されている試料前処理工程に目を落とすと,多くの場合使用されるSPE剤は1種類だけに留まっていないことに気が付く。ミニカラムからの溶出液は溶媒除去・転溶を経て,また別種のミニカラムを用いてSPEが行われ,プロトコル全体は煩雑化している。分析者が長時間の手作業に拘束されることは容易に想像がつく。このような事態を招く原因こそ,今回の主題としたい“残留農薬分析におけるSPE剤の問題点”である。つまり残留農薬分析の場合,上述のように“極性”の差異に基づく分離特性を有するSPE剤を1種類だけ選択して精製を図ろうとも,被検農薬成分と夾雑成分との分離は到底達成し得ない。SPE剤の持つ被検農薬成分に対する吸着選択能を高めない限り,これは叶わない。では実際にこのようなSPE剤は存在するのだろうか。無いわけではない。その一例として農薬成分に対し高い吸着選択性を発現するSPE剤としては分子鋳型ポリマ(MIP; Molecularly Imprinted Polymer)やイムノアフィニティーカラム(IAC)があり,近年ではアプタマーもある。市販されているものを調達することも,また自身の手で調製することも可能である。しかしこれらも完全無欠のSPE剤というわけでもない。本稿では,残留農薬分析と固相抽出をキーワードに,抽出・精製技術の最近の進歩,並びに選択的SPEの可能性について概説したい。
2.選択的吸着剤開発の歴史 選択的吸着剤(ここで敢えて「吸着剤」と言い換えるのは基材の表面,あるいは官能基との分子間距離が細密であり,強く選択性が発現していることを強調するため)開発の歴史を遡るとMIPの開発にたどり着く。MIPはその名の通り,ポリマ基材の表面に目的化合物の形状の穴が存在するイメージを想像しがちであるが,実際はそんなに単純なものではない。MIPの作製法自体は比較的簡単で,実験室レベルで十分作製可能ではあるが,分析者が求める性能を有するMIPを作ることができるかという点では決して容易ではない。というのも MIPの調製に使用するモノマーやテンプレート分子,希釈溶媒の種類やその配合比はすべて手探りで,最適化までには多大な労力と時間を要するからだ。MIPの調製はまず適当なモノマーなどの種類と割合で調製したMIPをいくつか試作し,それぞれの吸着特性を評価することからはじめる。ここで良好な吸着特性を有するMIPが得られれば良いのだが,得られなかった場合には試行錯誤の繰り返しある。最適なレシピさえ決定すれば,MIPの最大の特徴である優れた分子認識能を利用し目的分子を高選択的に濃縮することが可能となる。ただし,これまでに多くの論文などでMIPの問題点が報告されていることも留意すべきである。毒性物質や希少な物質を鋳型に使用することが困難であること,MIP内部の鋳型分子を完全に除去できないこと,MIPの内部に閉鎖的な吸着部位ができてしまうこと,高水溶性分子に適用が困難であること,柔軟な立体構造を有する分子への適用が困難であることなど,実用性に関する問題点は数多くあげられる。しかし,まぎれもなく分子認識能は高く,残農分析に適用したMIPによる固相抽出報告例は引きも切らない[1]。ただ,測定対象となる農薬数に比べてMIP数は限られており,多成分一斉分析という残農分析のトレンドと相反する。今後はマトリクス除去を目的としたMIP開発が増大するものと思われる[2]。
同様に歴史のある選択的吸着剤として,抗体を基材に固定化したIACが知られている。IACは生体物質が有する特異的な分子間の親和力を利用することで目的分子への選択性を発現する。例えば酵素-基質,抗原-抗体,レセプター-リガンド間の親和力は生命活動には欠かせない分子認識能である。この親和力をクロマトグラフィーに適用するためには,上記の関係のうちのどちらか一方を固定相に固定化し,他方を目的分子とすれば可能となる。ただ,IACの調製は,目的化合物へのハプテンの導入,動物への感作と抗体産生細胞の摘出,ハイブリドーマの形成と培養,抗体の精製及び基質特異性の評価,そして固定化までと長期に及び,一個人で行える操作ではないので、市販品に頼らざるを得ない。その市販品も,他の吸着剤に比べ安定性や耐有機溶媒性に劣る。これだけ問題点を挙げると,さもデメリットばかりで実用性が無いように思えるかもしれないが,オンサイト分析におけるIACの利用価値は疑うべくもない。食品に残留する危害因子検出用のELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) キットから,薬局で売られているような妊娠検査薬に至るまで現場で簡単に,迅速に結果を生み出すという点で優れている。このELISAでは,抗体の欠点を補うために上記のMIPで代用した報告例もある[3]。 最近,抗体類似の吸着剤として,アミノ酸や核酸の人工オリゴマーであるアプタマーが紹介されている。アミノ酸アプタマーは,化学的性質の異なる多種のアミノ酸からなるペプチドであり,酵素や抗体様の高い親和性の発現が期待される。しかし,合成とスクリーニング,その後の量産化の困難さが適用を妨げている。これに対し,生化学的に不安定な核酸アプタマーの方が,PCR (Polymerase Chain Reaction) 装置によって容易に増幅可能という利点を活かして幅を利かせている。SELEX (Systematic Evolution of Ligands by EXponential enrichment) 法という目的化合物と特異的に結合する核酸オリゴマーを作り出す技術を利用し,得られたオリゴマーはPCR増幅した後,基材に固定化して吸着剤とする方法である。アプタマーは抗体以上に不安定であるが,その調製法は確立されているため,ユーザ自身で調製することになる。MIPも含めて,これら選択性吸着剤は,何れも特定の目的分子に対する選択性を極限まで高めた吸着剤として非常に優れている。ただし,良くも悪くも対象化合物が限定されている点で,農薬の抽出・精製に利用されるというよりはむしろ,フローインジェクション分析 (FIA) での固相発光の基材としての需要が高まることが想定される[4]。最近では,選択性吸着剤に蛍光団を導入したセンサー分子としての報告例が増大している[5,6]。 3.多足型吸着剤の評価 吸着剤に働く相互作用の種類とそのポテンシャルエネルギーは,イオン交換体での静電的相互作用やキレート樹脂での配位結合力を最強に,電気的に陽性の水素原子と電気的に陰性の原子の間に働く水素結合,逆相系吸着剤での親油性相互作用や
 スタッキング相互作用,分子間に普遍的に働く弱いファンデルワールス相互作用と多種に亘る。市販の固相抽出剤と呼ばれているものの大半は,これらの内のポテンシャルが比較的強いとされる相互作用一つを利用している。一方,Waters社のOASISR HLBは,ベンゼン環による親油性 ( スタッキング相互作用,分子間に普遍的に働く弱いファンデルワールス相互作用と多種に亘る。市販の固相抽出剤と呼ばれているものの大半は,これらの内のポテンシャルが比較的強いとされる相互作用一つを利用している。一方,Waters社のOASISR HLBは,ベンゼン環による親油性 ( ) 相互作用とピロリドン基による親水性(水素結合)相互作用を併せ持った二足型吸着剤の典型である。逆相系の吸着剤とシリカゲルを混床させても同様の効果が得られないことより,異なる相互作用を持った官能基が特定の距離を保って相補的に働くことで新たな吸着力が発現されることは明白である。上述のMIPも広義の多足型吸着剤である。 ) 相互作用とピロリドン基による親水性(水素結合)相互作用を併せ持った二足型吸着剤の典型である。逆相系の吸着剤とシリカゲルを混床させても同様の効果が得られないことより,異なる相互作用を持った官能基が特定の距離を保って相補的に働くことで新たな吸着力が発現されることは明白である。上述のMIPも広義の多足型吸着剤である。それでは,選択性を発現可能な多足型吸着剤として,どのような官能基設計が必要となるのであろう?イオン性を持った有機化合物の選択的捕集を例にとる。一般的なイオン交換樹脂は,スチレン-ジビニルベンゼン共重合体にイオン交換基を導入した一見二足型吸着剤のようであるが,選択性はまるで無い。イオン交換体は,全体で大きな電荷を帯びた微粒子と考えられ,表面には電気二重層が存在し,電荷を持った溶質は交換体表面に近づくことが許されない。従って,単純なイオン交換相互作用しか発現しないのである。筆者らは,親水性の基材樹脂上に四級アンモニウム基とC18基を導入した二足型の吸着剤を合成・評価した。有機溶媒中でアルキル鎖は電気二重層の外まで伸びることで,塩で洗浄しても陰イオン性有機化合物が脱着しない強い選択性が得られたと考えている[7]。 多足型吸着剤では,そのポテンシャルエネルギーが比較的強いとされる相互作用が組合せられてきた。吸着剤に用いられる相互作用に必要な要件は,ポテンシャルエネルギーだけではない。遠くの溶質を吸着剤表面に引き寄せる距離依存性も重要となる。クーロン力のような距離依存性の大きな官能基で溶出を引き寄せることができれば,ポテンシャルの小さな相互作用も働く場が生まれると考えた。そこで筆者らは,距離依存性の大きな水酸基とポテンシャルエネルギーの低い双極子相互作用を持ったp-ニトロフェノールを導入した吸着剤を合成・評価した。図1にその模式図を示す。ここでは  スタッキング相互作用も働く,いわゆる三足型吸着剤である。この吸着剤は,水素結合能を有する溶質のうち,ベンゼン環に基づく平面性と大きなモル屈折率を持った化合物に対し,極めて高い選択性を示した[8]。モル屈折率とは,溶質が置かれた電場環境による分子内電荷の偏り易さを示す指標と関連する定数で,p-ニトロフェノキシ基の配向双極子によって生じた誘起双極子間との双極子-双極子相互作用が吸着に大きな役割を果たしているものと考えている。以上の物性を持った農薬種は,フェノキシ酢酸系,一部のネオニコチノイド系やフェニルウレア系薬剤と多岐に亘り,分離分析装置の前処理基材としては最適であった[9]。 スタッキング相互作用も働く,いわゆる三足型吸着剤である。この吸着剤は,水素結合能を有する溶質のうち,ベンゼン環に基づく平面性と大きなモル屈折率を持った化合物に対し,極めて高い選択性を示した[8]。モル屈折率とは,溶質が置かれた電場環境による分子内電荷の偏り易さを示す指標と関連する定数で,p-ニトロフェノキシ基の配向双極子によって生じた誘起双極子間との双極子-双極子相互作用が吸着に大きな役割を果たしているものと考えている。以上の物性を持った農薬種は,フェノキシ酢酸系,一部のネオニコチノイド系やフェニルウレア系薬剤と多岐に亘り,分離分析装置の前処理基材としては最適であった[9]。
4.選択的吸着剤の未来 カラム充てん剤の微粒子化技術の進歩に伴いHPLC用カラムが高理論段化ばかりに気を取られ,固定相が持つ溶質選択性に関する進化はずっと置き去りになっている。それが理論段数の低い固相ミニカラムで顕著になり,残留農薬分析において表面化した今,分離分析を見直す時期に来たのだ。クロマト分離のための担体技術を駆使して,各分野のユーザが求める分離剤を創出していく必要があると強く感じている。しかし,汎用の吸着剤を排他的に捉えているわけではない。筆者らが試作した多足型吸着剤と組み合わせることで,従来の前処理法よりもはるかに短時間で高い精製効果を得ることが可能という点を考えれば相補的な関係と捉えた方が良い。また,MIPやIACに関しては残留農薬の一斉分析には不向きな一面もあるが,オンサイト分析やスクリーニング分析など,直ちに結果が求められる分析こそ向いているだろう。分析のニーズに合わせ,既存の技術と組み合わせることで分析手法の幅を広げることも非常に重要である。問題は,試行錯誤的に行われている溶質選択性吸着剤の開発方法である。
気固吸着は,吸着剤表面と吸着質単分子の二成分系として取り扱うことができるため,古典的分子動力学法を使った計算化学で吸着現象をシミュレーション可能である。ところが,液固吸着は溶媒が第三の成分として加わるため,溶質~溶媒間と吸着剤~溶媒間の相互作用も考慮しなければならない。例えば,水素結合性の受容体を持つMIPでは,プロトン供与性溶媒中では選択性を発現できない。古典的な溶液中での溶質間に働く力 (J/cm3) を表すパラメータとして,Hildebrandの溶解度パラメータが知られている[10]。しかし,ここで用いられる分散力,双極子モーメント,水素結合の各パラメータは経験的なもので,得られる結果も定性的でしかない。最近,溶媒中の異なる二種類の溶質間の距離を変数とした自由エネルギー変化量を求める分子動力学シミュレーションが可能になった[11]。この種のソフトが容易に使いこなせるようになれば,溶媒中での吸着剤官能基と農薬間の相互作用が定量的に把握できるようになり,目的農薬群に対して選択性を発揮する吸着剤の設計が容易になるものと期待している。 5.おわりに 本メルマガの読者層は,何らかの形で食品に関与している人たちであろう。読者の興味や編集者の意向を無視して筆者らの趣味の世界を語ってしまったが,もう後の祭りである。複雑な食品マトリクス中から農薬類だけを選択的に取り出すのは不可能なことは誰の目にも明らかなことである。我国において検出率の高い100農薬だけで,検出される農薬全体の9割を超えるというデータもある。10個程度の官能基認識型吸着剤があれば,これらを網羅できることになる。少しでもマトリクスの影響を抑えつつ農薬を捕集したいのであれば,官能基認識型の吸着剤を組合せればよい,という筆者らの意向を汲み取っていただけたら満足です。
参考文献 [1] L.X. Yi, R. Fang, G.H. Chen, J. Chromatogr. Sci., 51, 608, 2013.
[2] B.S. Batlokwa, J. Mokgadi, R. Majors, C. Turner, N. Torto, J. Chem., 2013, Article ID: 540240. [3] Y. Tang, G. Fang, S. Wang, J. Sun, K. Qian, J. AOAC Int., 96, 453, 2013. [4] A. Molina-Diaz, J.F. Garcia-Reyes, B. Gilbert-Lopez, Trends Anal. Chem., 29, 654, 2010. [5] Y. Zhao, Y. Ma, H. Li, L. Wang, Anal. Chem., 84, 386, 2012. [6] J. He, Y. Liu, M. Fan, X. Liu, J. Agric. Food Chem., 59, 1582, 2011. [7] 塚本友康,清水 愛,山本 敦,小玉修嗣,上茶谷若,井上嘉則,食品衛生学雑誌,51, 58, 2010. [8] T. Miwa, A. Yamamoto, M. Saito, Y. Inoue, Molecules, 18, 5167, 2013. [9] 三輪俊夫,鈴木志穂,斎藤 勲,井上嘉則,山本 敦,分析化学,61, 673, 2012. [10] 近藤精一,石川達雄,阿部郁夫,「吸着の科学 第2版」,丸善㈱,2001. [11] 岡崎 進,吉井範行,「コンピュータ・シミュレーションの基礎 第2版」,化学同人,2011. 略歴
山本 敦
1979年金沢大学大学院薬学研究科修了。同年富山県衛生研究所勤務。2004年より中部大学応用生物学部教授。現在に至る。
三輪 俊夫
中部大学応用生物学研究科博士後期課程2年 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |
||
| Copyright (C)Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |