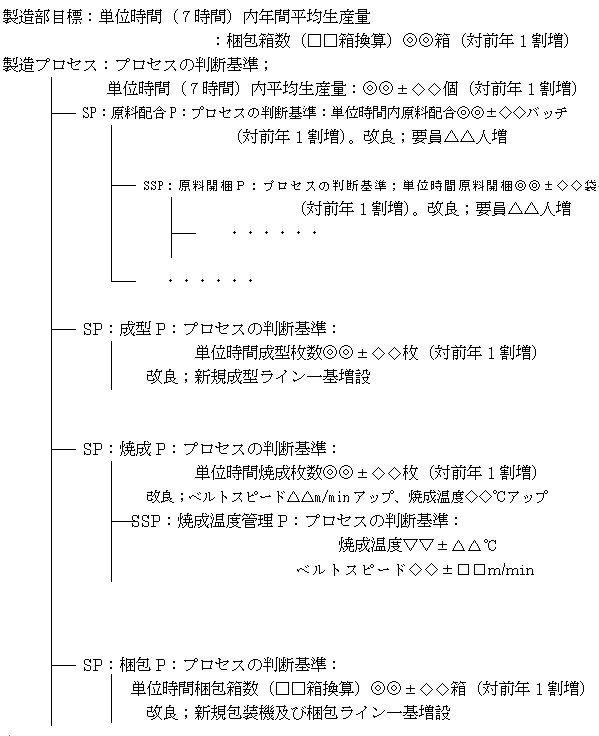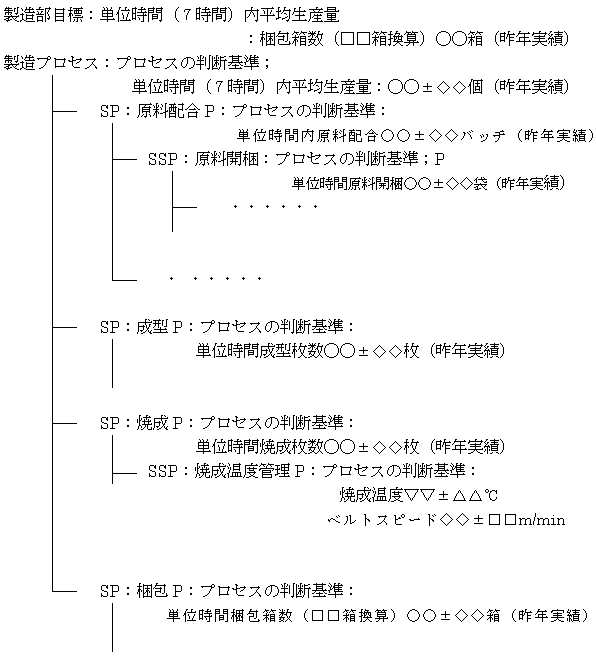|
食品業界を取り巻くISOマネジメントシステムの動向
その5: ISO9001とTQCとを合体する安定生産と改善活動両立の考え方 湘南ISO情報センター
代表 矢田富雄 1.はじめに前号で、認証を取得したISO9001が役に立たないと言っているのはISO9001の本来の目的をよく理解せず、本来の機能以上のものを求めているからであると記述した。 それではISO9001は改善ができないのかというとそうではない。改善を主目的にしてはいないけれども、「8.5.1」の継続的改善という要求事項がある。ただ、この要求事項は“安全で良質な製品を妥当なコストで安定供給をすること”という目的を達成できないような事態が発生したときにシステムを改善しなさいという要求事項である。また、「8.5.2」には是正処置という要求事項があり、目的を達成できていないような事態が発生したら再発防止をするために、その原因を改善しなさいとの要求事項である。さらに、目的が達成できないおそれがあると予測されたならば、あらかじめ手を打つことを求める「8.5.3」の予防処置がある。これらの要求事項を活用することで、“安全で良質な製品を妥当なコストで安定供給すること”を目指す中で、自組織のISO9001システムを改善できるのである。
2.プロセスアプローチの考え方今から25年以上前に、日本では、TQC(現在はTQMであるが、以降もTQCとして進める)とISOマネジメントシステム規格とを折り合いをつけながら活用していこうとして論議をしていた。日本における大変優れた改善の手法であるTQCの考え方を、ISO規格の中で活用していければ素晴らしいことである。このことは実現できるのである。本号ではこのことを述べていこうとしているのである。前号で“後ほど述べる”としたことであり、それはプロセスアプローチの考え方のことである。 プロセスアプローチの考え方の考え方は、ISO9001:1994から登場した。ISO9001;1994年版では本文に現れることはなかったが、解説などではその言葉がみられた。ISO9001:2000になると、序文は勿論のこと、本文にも工程と呼ばれていたものが“プロセス”と訳されるようになり、また業務そのものも、例えば購買プロセスと呼ばれるようになり、序文でも0.2にプロセスアプローチの呼称が登場してきた。さらに「8.2.3」にプロセスの監視測定という要求事項が導入されて、プロセスの管理のしかたも明確にされた。ISO9001:2008(以下、2008年版は特に必要な場合を除いてISO9000も含めて年号を省略する)になるとその序文に“望まれる成果を生み出す”ことに役立つと明記され、その有用性が強調された。
このことは何をいっているかというとISO9001の中の“プロセスアプローチを活用することにより望まれる成果、すなわち目的や目標が達成できる”ということである。このことからみて、“改善活動”をISO9001の目標に組み込めばプロセスアプローチを活用することにより、“改善”を達成できるということになる。しかしながら、意外に、このプロセスアプローチの意味が理解されてなく、目標達成に関してもプロセスアプローチと結びつけた管理は行われてないのである。 この重要な“プロセスアプローチ”に関しては、ISO9001及びISO9000の両規格において定義が明確ではないのである。まず、“プロセス”であるが、ISO9000では「インプットをアウトプットに変換する、相互に関連する又は相互に作用する一連の活動」と定義されている。一方、ISO9001の序文「0.2」では「インプットをアウトプットに変換することを可能にするために、経営資源を利用し、管理される活動は、プロセスとみなすことができる」と述べられている。この定義はよくわかる。
マネジメントシステムの世界では、“定義がなければオックスホードの英英辞典を見よ”という慣例がある。そこでプロセス及びアプローチに関してオックスホードの英英辞典を見ながら、プロセスアプローチを考察することにする。 processとは「a series of things that are done in order to achieve a particular result」(特定の結果を達成するためになされる一連の事柄;著者仮訳)である。 上記を総合して考えると、プロセスアプローチとは、『特定の成果を達成するための一連の業務(プロセス)を実施すること』であるといえる
3.望まれる成果と目標既に、前号で述べたように、組織というものは、基本的には財貨やサービスを提供して社会貢献をするためのものである。その中でISO9001に求められている役割は“安全で良質な製品を妥当なコストで安定供給すること”であり、このことを達成することが、まさに、望まれる成果である。この望まれる成果は、プロセスアプローチによって達成されるということは、望まれる成果を達成できるプロセス(一連の仕事)を明確にして、そのプロセスを監視測定していくことによって望まれる成果を達成できるようになるのである。このことは、実は、「8.2.3」のプロセスの監視及び測定によって管理することなのである。 目標というのは望まれる成果の最たるものである。従って目標を立てたらその達成に必要なプロセスすなわちその目標が達成される一連のプロセスを明確にして管理しなければいけないのである。目標は立てたが、その管理のためのプロセスを明らかにしていないこと、または、そのプロセスに沿って監視測定をしていないことは「8.2.3」の不適合なのである。
4.ISO9001の要求事項を活用した改善の進め方目標には2種類のものがある。一つは、現有のプロセスによって目標を達成していくという“現状維持を図る目標”であり、他は、現状より向上を目指そうとする “現状からの向上を図る目標”である。後者がいわゆる改善なのである。これらの目標は、ともに、その目標に相応しいプロセスを明確にして、ともに、「8.2.3」によって管理しなければならない。 ここで改善をどう進めていくかということを説明してみたい。例えば、生産量に関して現在の能力の10%増しを達成するという目標を設定したとする。この目標は数値を掲げただけで次の月から達成できるというようなものではない。現在の生産工程(プロセス)の改善を伴うのである。 生産量を10%向上するためには、新たに導入したそれぞれのプロセスが計画どおりに運用されて始めて達成できるのであり、それぞれのプロセスが計画どおりに運用され、管理されていることを判断できる基準が必要である。その判断基準と方法を明確にしなければいけないのである。すなわち、ISO9001の「4.1c)」である。続いてこれらのプロセスの運用及び監視を支援するための資源及び情報を用意する必要がある。「4.1d) 」である。さらに、これらのプロセスを監視あるいは測定し、分析をする(「4.1e) 」)。これらの結果が計画どおりの成果を得るために、必要であれば、修正や是正処置を実施し、継続的改善を図っていかねばなければならない(「4.1f」)。
5.プロセスアプローチの図解望まれる成果とは目標であり、前年の実績どおりの数値を達成する“現状維持を図る目標”と前年の実績を超えて改善を図る “現状からの向上を図る目標”とがあると述べた。それらの望まれる成果である目標は、それらのプロセスを確実に実施しなければ成果は期待できない。 図-1“現状からの向上を図る改善活動” における品質目標とプロセスの関係1) SP :Sub process の略 注1) 現場に視点で読み解くISO9001:2008の実践的解釈
6.まとめISO9001にはプロセスアプローチという考え方がある。望まれる成果を達成するために、このプロセスアプローチを活用するとよいと述べている。ただ、このことは特別のことではない。日々の安定生産であろうと、大改善であろうと、それぞれに、その成果を達成するためには、その道筋(プロセス)があるはずである。この道筋に沿って業務を実行しなくては目標の達成はできない。 ここで忘れてはいけないのは、確実な改善を目指すには、資源の裏付けが求められるということである。ISO9001の素晴らしいところは、6章に「資源の運用管理」という要求事項のあるところである。この資源には、知的資源、時間的資源、物的資源、環境資源などがあり、これらは全てが“資金”でサポートしなければ実現できるわけはないのである。精神論は大切であるが、精神論のみでは改善は実現できない。この資源の提供に関しては、経営者の考え方で大きく左右される。 ISO9001で改善推進の考え方も、定型業務の進め方も理路整然と進めていきたいものである。
サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |
| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |