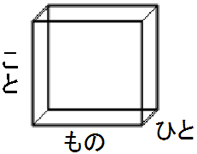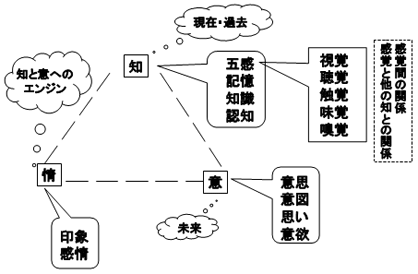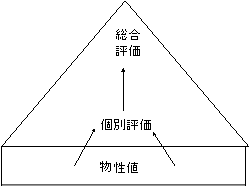|
官能評価の概論と実際
金沢工業大学情報フロンティア学部心理情報学科 教授
感動デザイン工学研究所 所長 神宮英夫 1.官能評価の実際新製品としてペットボトルの緑茶を開発した。もちろん、既存の緑茶よりもおいしいものをと、開発者は工夫を凝らした。特に風味にこだわったとのことである。既存品よりもおいしくなっているかどうかは、飲み比べて調べるしかない。この調べ方が、客観的でなければ、得られた結果は信用されない。これには、いくつかの方法が考えられる。他社品を例えば4品準備したとする。
2.官能評価の基礎官能評価(sensory evaluation)は、人がものと接したときに感じたことを言葉で表現することで、成り立っている。人が感じるのは、視聴触味嗅の五感を通してであり、ものから得られた五感情報が処理された結果である。この結果は言葉を介して表現されるが、評価実験としては、例えば良し悪しのように、良悪をわける基準に基づいて表現される。この基準は、人が心の中に持っている内的な基準(internal criterion)であり、種々の経験を通して形成された五感情報に基づいたものである。
もう一つの重要な側面は、接するという行為である。評価実験として、官能評価が実施されるので、どうしてもコントロールされた実験状況が設定されることになる。実験者が知りたいことが結果として得られるように、状況が設定されるため、消費者が日常ものとしての製品と接する接し方とは異なる状況になることが多々ある。例えば、複数の緑茶の苦みの違いを明らかにしたいと実験者が考えていれば、緑茶を口に含んで吐き出して、苦みの評価を行うことになる。これを何品も繰り返す。しかし、よく考えてみると、このように緑茶を飲んでいる人は、普通はいないであろう。一口二口飲んでおいしいというのであり、いちいち苦みの程度を意識しながら飲むことはない。つまり、通常の官能評価事態は、非日常的であると言わざるを得ない。しかし、必要な結果を得るためには致し方ないというジレンマが、常に官能評価にはつきまとっている。
3.ものがもたらす五感情報とひとの特性ものとしての製品からもたらされる五感情報は、その製品が持っている品質要素が基本となる。甘みの量からもたらされる甘みの強さ、室内灯からもたらされる光量による明るさの程度、などである。五感情報によって評価結果が左右される以上、品質要素の上手な組み合せが、よい評価をもたらす基本である。ここで問題となるのは、各五感情報が相互に独立で、それぞれの単純な組み合せで評価がもたらされるわけではないという点である。例えば、塩分の量によって甘みの評価が大きく変化することがある。味覚の中だけでも、複雑な関係性が存在しており、五感の間ではもっと複雑な関係性の下で、評価がもたらされる。
評価を行うためには基準が必要であり、五感という官能による評価には、過去の五感情報からもたらされた経験が、その基準を構成している。この内的な基準は、経験の違いによっているので、個人差が存在する。そして、性格や感情など、人の内的特性によっても異なる。高額な化粧品を買っている人と、毎月わずかな金額でしか化粧品を買わない人とでは、化粧品に関わる経験が異なる。このような違いを揃えるために、毎月化粧品に出費する金額で人を分類して、化粧品の評価結果を別々に分析することが行なわれる。これは、金額によるフェイス項目による分類である。また、ある化粧品会社に対する、あるいは化粧品に対する態度の違いによっても、評価結果は異なる。このような内的特性で、個人差を揃える必要がある。内的特性には、態度や性格そして経験などが考えられる。経験は記憶の違いをもたらし、態度や性格は情意の特性に影響している。
4.こととしての評価用語評価として使用する言葉の問題が、重要である。一般に官能評価を実施している人は、ほとんど意識せずに、図3のような評価の階層性を念頭において、評価用語を考えている。品質要素としての甘みの量の物理的属性が、甘さの評価をもたらし、甘さや苦さの評価が組み合わさって、おいしいという総合評価がもたらされるという、下から上の階層性である。
ところが、一般の消費者は、先にも述べたように、いちいち物理的属性を意識することはない。ビールを一気に飲み干し、おいしかったという。そして、喉越しのいいビールだと思う。つまり、官能評価を実施する専門家とは異なり、おいしさという総合評価を先に意識して、その原因として「どうして・なぜ」ということで、喉越しを意識することになる。このように、日常的には、上から下の階層性が基本である。
5.官能評価で統計がなぜ必要か官能評価手法(JIS Z 9080)は、評価者の何を知りたいのかということと、評価すべきものの数によって分類することができる。評価者の問題は、感覚上の感受性の問題とものの受け止め方の問題とに大別できる。感受性の問題は、ものの物理的側面についてどの程度までわずかな違いが識別できるかということである。受け止め方は、物理的属性につながる個別評価か好みなどの総合評価かということであり、評価用語の問題とも関係してくる。ものの数は、1つでの評価の場合と2つでの比較の場合と3つ以上の区別が必要な場合である。 官能評価実験によって正確な結果を出そうとすると、実験条件を厳格にする必要が出てくる。そうすればするだけ、日常生活で消費者が製品と接する状況とはかけ離れてしまうことになる。日常性をどこまで担保して、良い結果が出せるかが重要であり、このために、方法の工夫や分析の工夫したがって統計の工夫が必要である。
参考文献大越ひろ・神宮英夫 編著 2010 食の官能評価入門 光生館 略歴1977年 東京都立大学大学院人文科学研究科修士課程(心理学)修了
サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |
| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |