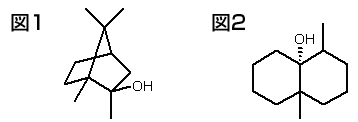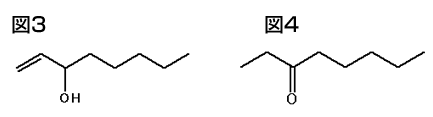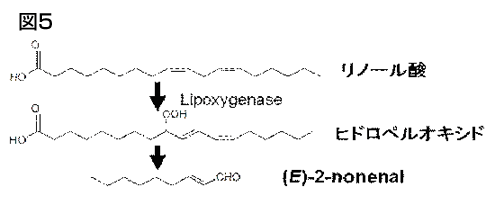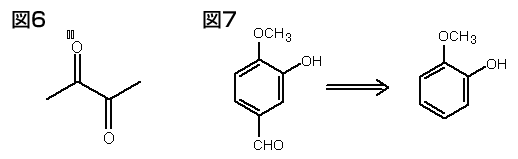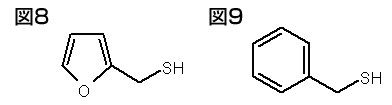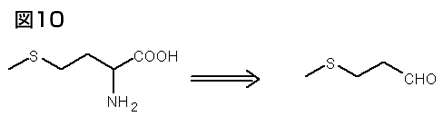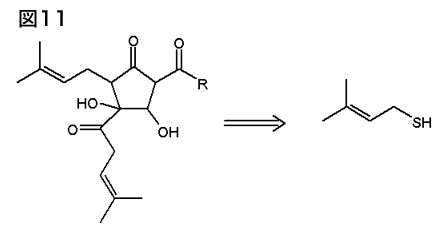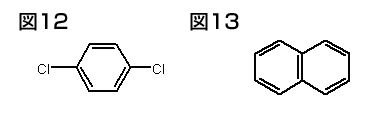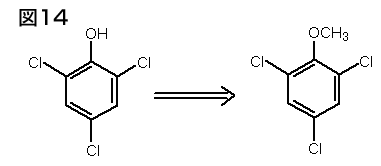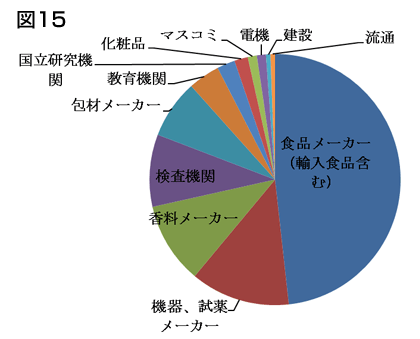|
�H�i�̃I�t�t���[�o�[���
�����Ɛ���w�Ɛ��w���h�{�w�ȋ���
�����g�N �ߔN�A�䂪���ł͐H�i���S��{�@�����肳��A���t�{�H�i���S�ψ���̐ݒu�A����ɏ���Ғ��̐ݗ��Ȃǂ̎Љ�ɂ��A����҂̐H�i�̈��S�ɑ���S�͍��܂����ł���B���̊S�̒��g���݂�ƁA������N�Ԃ͕��˔\�����Ɋւ��Ăł������B���ː��Z�V�E���������H�i����1kg�����聢���x�N�������o���ꂽ�Ƃ�����ɕs���������A�x�N�����A�V�[�x���g�Ƃ����A��ʏ���҂ɂƂ��ĕ����Ȃ�Ȃ����t���×������B�k�ЈȑO�ł͏���҂̊S�́A���Y���E���_��H�i�Ƃ������_�ɏW�����Ă���̂�����ł������B�������A�H�i�Y�����E�c���_��ɂ���ĐH���ł��N�����Ă����������邱�Ƃ͓���B���S�Ƃ����ʂɖڂ�������ƁA����҂ƐH�i�����Ǝ҂͈قȂ��Ă���A�H�i�����Ǝ҂ɂƂ��đ傫�Ȉʒu���߂�̂́A�i��������ُL�i�I�t�t���[�o�[�j�ɂ����ł���B���N�ɒ��ډe���͂Ȃ��Ƃ��A����҂��I�t�t���[�o�[���犴����H�i�ւ̃C���[�W�͑傫���A����҂ւ̑Ή��@���ɂ���ẮA���i�ւ̑傫�ȃ_���[�W�ƂȂ�ꍇ������B���̃I�t�t���[�o�[�ɂ��Đ������痬�ʁE�̔��ɂ����Đ��������ʂ̔F���������Ƃ͔��ɏd�v�ł���ƍl����B
�@�I�t�t���[�o�[�͂������ʂŌ��ʂ��������Ƃ�����A�����ɂ͒����o���Ƒ��z�̓�����K�v�Ƃ���B�l�ł̒Nj��ɂ͌��E������A�����̒m�����W�����ĒNj����邱�Ƃ��̗v�ł���B �@�܂��A�I�t�t���[�o�[�Ƃ͋�̓I�ɂǂ̂悤�ȏL�����w���Ă����̂����l���Ă݂����B�u���̐H�i�ɂ��Ƃ��Ƒ��݂��Ă��Ȃ��L�C�����̕t����A�H�i���L���Ă���ꕔ�̏L�C�����̑����⌸���A�Ȃ����͏L�C�����S�̂̃o�����X�̕ω��ɂ�芴������w�ɂ����x�ł���A�H�i�ɂ��Ă̊e�l�̌o������҂Ɋ�Â��e�l�́w���ݓI�Ȋ�x����A�L����Z�x����E���Ă���Ɣ��f���ꂽ�ꍇ�Ɍ��݉�����w�ɂ����x�v�̂悤�ɒ�`�ł���̂ł͂Ȃ����B �@���̂悤�ȃI�t�t���[�o�[���ȉ��̂悤�ɔ����v���y�ѕ��͖@�ɂ��čl���Ă݂�B �@�傫��2�̗v���ɕ����邱�Ƃ��ł���B �i1�j�H�i���̂��甭������ꍇ�@�@�H�i�̌����f�ނɋN����������@�A�H�i�����̍y�f�I�ϊ��ɂ����� �@�B�H�i�����̉��w�I�ϊ��ɂ����� �i2�j������̈ڍ��i�ڂ荁�j����ꍇ�܂��A�i1�j-�@�̏ꍇ����l���Ă݂�B�H�i�̌����Ƃ��čł��d�v�Ȃ��̂ɐ����������邪�A���̐��������ۂ◕�����Y������ُL�����A����2-���`���C�\�{���l�I�[��(2-MB)�F�@�}-1��W�I�X�~���F�}-2�ɂ���ĉ�������A�y�L��J�r�L�A�n�`�L�Ƃ������L�����������邱�Ƃ�����B�����́A�����r���邢�͒������A�������Ɍ����ۂ�ނ��ɐB���邱�Ƃɂ���ĎY�������킯�ł��邪�A�ŋߕ��y�����鋋����̓��Ƀp�b�L���O�����ɂ����������ۂ��ɐB���邱�Ƃɂ�艘���������Y����������U�������B�����ЂƂ̗�Ƃ��āA�����̃J�r�ɂ��J�r�L��������������B�����Penicillium��Aspergillus�Ȃǂ̃J�r���Y������ُL������1-�I�N�e��-3-�I�[���F�}-3��3-�I�N�^�m���F�}-4�ł���B�@�i1�j-�A�̏ꍇ�ɂ����āA�����̐����ɂ��čl���Ă݂�B�l�X�Ȉ����Ɋ܂܂����ʂ��ɰَ_�Ȃǂ̕s�O�a���b�_���������Ɋ܂܂�郊�|�L�V�Q�i�[�[�Ȃǂ̎_���y�f�̉e�����A���ԑ̂̃q�h���y���I�L�V�h���o�R����(E)-2-�m�l�i�[���F�}-5�����A���b�L������ꍇ�Ȃǂ�����B���̔��y�H�i�ɂ����Ă͗������f��W�A�Z�`��:�}-6�Ƃ����������������y���ɎY������邱�Ƃ͂悭�m���Ă���B �@�����ĉ��H�H�i�ɔ��������������邱�Ƃɂ���Ĕ�������ُL�̗���Љ��B���H�H�i�ɖ�i�L�������Ƃ�����ł��邪�A����͉��H�H�i�Ɋ܂܂�鍁�������̃o�j����:�}-7�������ۂł���D�M���D�_��Alicyclobacillus�Ȃǂɂ��ُL�����ł���O�A�C���R�[���ɕϊ�����A�����������̂Ɛ��@�����B �@���Ɂi1�j-�B�̏ꍇ�ł��邪�A�H�i�����H���̉��M�H�����ɂ����ĉ߉��M�ɂ�胍�[�X�g�l�A�ΑŐΗl�̏L�C��������������ꍇ�ł���B���������Ƃ��Ă�2-�t���t�����`�I�[��:�}-8�A�x���[�����^���`�I�[��:�}-9�Ȃǂ����肳��Ă���B�܂��A������r�[���Ȃǂ̈����������Ȃǂ̌��ɒ����������ƈُL�������Y�������B�������̃��`�I�j����3-���`���v���p�i�[��:�}-10�ɁA�r�[�����̋ꖡ�����C�\�t��������3-���`��-2-�u�e��-1-�`�I�[��:�}-11�ɕϊ�����ĈُL����B �@���ɁA�i2�j�̏ꍇ�ł��邪�A�����ΐH�i����i�L������Ƃ�������҂���̐\���o������B�ŋ߂ł͋L���ɐV�������̂Ƃ��āA�J�b�v�˂ւ̖h���܃p���W�N�����x���[���}-12�̈ڍ��̖�肪�������B���ɂ��A�i�t�^�����}-13�i���l�̖h���܁j�����o���ꂽ�B �@�܂��A��ނ̈���Ɏg�p����Ă���n�܂̊����s�Ǔ��ɂ��m-�N���]�[����t�F�m�L�V�G�^�m�[�������o���ꂽ�������B�������A�ڍ��Ƃ��Ă���܂ōő�̖��̓g���N�����A�j�\�[���ɂ�鉘���ƌ����Ă悢���낤�B�{�ɂ��͂��߂Ƃ����؍ނ��g�p����\�����ɖhꀍ܂Ƃ��ăg���N�����t�F�m�[�����g�p����Ă����B���l�ɁA�H�i���͂��߂Ƃ��������̗A�������̃t�H�[�N���t�g���ɂ��ړ��̍ۂɎg�p�����ؐ��p���b�g�ɂ��g���N�����t�F�m�[�����g�p���ꂽ�B���̖؍ނ�Trichoderma�AFusariumu�Ƃ������J�r���ɐB���A���̃g���N�����t�F�m�[�����ӂ��āA�ŋ��ُ̈L�����ł���2,4,6-�g���N�����A�j�\�[���������i�}-14�j�B�ؐ��p���b�g��Ő������ꂽ�g���N�����A�j�\�[���́A�H�i�����A��ށA���H�H�i�Ȃǂ̂����镨�������������B����臒l�͐�����1ppt�Ƃ������ɒ�Z�x�Ŋ�������L�C�̂��ߐH�i�ƊE�ł͑傫�ȑŌ������B�]���āA���ݎg�p����Ă���p���b�g�͂قƂ�ǂ��v���X�`�b�N���ł���B �@�����܂ŁA�I�t�t���[�o�[�̔����v���ɂ��ďq�ׂĂ������A�܂��܂����ɂ������̗v�����l�����邪�A�����ł͂����܂łɂƂǂ߂�B�܂��A�����������v����Nj����Ă����ɂ́A�H�i��ǂ��������A���\�]���Ƒg�ݍ��킹�邱�Ƃ��d�v�ł���B���\�]���ł��Ȃ����̂�Nj����Ă䂭���Ƃ͕s�\�ɋ߂��B�v���́A�H�i�̓��Ȃ̂��O�Ȃ̂���I�m�ɔ��f����B�H�i���̐����o�����X�ɕ肪���������߂ɏL�C�Ɗ�����ꍇ������̂ŁA�����O���ɒu�����Ƃ��K�v�ł���B�����܂��A�@�핪�͂ɂ���Č�����������肵�Ă䂭�B �@��X�́A�����������I�t�t���[�o�[����H�i�Ɍg���l�Ԃ̋��ʔF���Ƃ��A���ɍl���Ă䂭�����邱�Ƃ��l���A�I�t�t���[�o�[������𗧂��グ���B����ɁA��N7��22���ɃI�t�t���[�o�[�������Â̑�1�����𓌋��Ɛ���w�ɂ����ĊJ�Â����B�H�i��Ƃ𒆐S�ɁA�}-15�̂悤�ȕ��X�ɎQ���������B�Q���҂̕��X�̌��݂̃I�t�t���[�o�[�ɑ���S���́A�ȉ��̂悤�ȓ_�ł������B(1)�����̓���F�����A�o�H�@(2)���͖@�@(3)�ڍ��@(4)�J�r�L�A�����L�A���M�L�A�����L�A���g���g�L�@(5)�p�l���̋���F���\�]���@(6)�Z�x�Ƃɂ����F臒l�Ȃǂł���B �@���ۂɁA�Q�����ꂽ���X�ɂƂ��ĎQ�l�ɂȂ������́A(1)����҃N���[���̗�@(2)�����H���ɂ�������_�@(3) ���͎���@(4) �f�[�^�x�[�X�̏d�v���@(5)���\�]���̏d�v���@(6)臒l�̍l�����@(7)�g���N�����A�j�\�[���֘A�i����@�A��j�@(8)�I�t�t���[�o�[�ւ̎��g�݁@�Ȃǂ̓_�ł���B ���ǂ��̐ݗ��������܂����u�I�t�t���[�o�[������v�͊������e���z�[���y�[�W�ŏЉ�Ă���܂��B�I�t�t���[�o�[�̔����v���̌����ɂ��Ă��ڍׂ��������܂��B���Ј�x�A�N�Z�X�����Ă������������Ǝv���܂��B�A�h���X��http://www.fofsg.jp/�@�ł��B
�I�t�t���[�o�[�������2�����̂��ē��I�t�t���[�o�[�������2�������J�Â������܂��B�������̂�����͐��Q���������B
��������24�N7��20���i���j�@�ߑO10��30�����i��t10��00�����j��������Ɛ���w���L�����p�X�@�O�z�[�� �@�@�@�@ �����s�������P�|�P�W�|�P�@�i�i�q�鋞���\���w���ԓk��5���j ���200�� �@���e�i1�j�����������Ȃ����͖@ �@�@�@�@�@ ���v���c�@�l�@�T���g���[�����Ȋw���c�@�����[�� �@ �i2�j�ُL�H�i�̃T���v�����O�ƒ��ӓ_ �@�@�@ ���c�@�l�@���Ɍ��\�h��w����@�ɓ����j�� �@ �i3�j���͂�����O�Ɂ@�`���o�𗘗p���������ƒ��ӓ_�` �@�@�@�@ �@ �@�@�G�X�r�[�H�i������Ё@����x�l�� �@ �i4�j�ݖ��̃I�t�t���[�o�[�Ƃ��̖h�~�� �@�@�@�@ �@�@�@ ���c�@�l�@���{�ݖ��Z�p�Z���^�[�@���䒉�M�� �@ �i5�j�I�t�t���[�o�[���q�̓����ƍŋߋC�ɂȂ�I�t�t���[�o�[���� �@�@�@�@ �@�@�@ ��a��㣊�����Ё@�������V�� �@ �i6�j�p�l���f�B�X�J�b�V���� �@ �i7�j��������@�i�w���J�t�F�e���A�@���[�`�F�j �Q��������@4000�~�@��������@4000�~ �\�����ݐ�http://www.fofsg.jp/���� 1979�N3��������w�_�w���_�|���w�ȑ���
1981�N3��������w��w�@�_�w�n�����Ȕ_�|���w��U�C�m�ے��C�� 1984�N3��������w��w�@�_�w�n�����Ȕ_�|���w��U���m�ے��C�� 1984�N3���_�w���m�w�ʎ擾 1984�N4���������Ɗ�����Г��� 2010�N3���������Ɗ�����БސE 2010�N4�������Ɛ���w�Z����w���h�{�ȋ������C 2012�N4�������Ɛ���w�Ɛ��w���h�{�w�ȋ����i�����ύX�j �T�i�e�b�N���[���}�K�W���ւ̂��ӌ��E�����z���qe-magazine@mac.or.jp�r�܂ł����������B |
| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |