|
AOU研究会の活動と今後
AOU研究会 事務局
山﨑 光司 Antioxidant unit研究会(AOU研究会)は、適切な食品の抗酸化能指標を目指し、食品の抗酸化力に対する統一した指標「Antioxidant Unit(AOU)」の確立とその表示の検討を行い、食品における抗酸化物質の普及を通じて国民の健康に寄与することを目的として、2007年に発足した。当研究会は、産学官の連携により運営しており、理事長には大澤俊彦愛知学院大学教授(名古屋大学名誉教授)が選出されている。
抗酸化物質の反応機構
これまでAOU研究会では、AOUを得るための分析法確立に向けた活動を行ってきた。抗酸化物質による活性酸素種消去反応機構は、抗酸化物質の種類によって反応機構が大きく二つに分かれるため、AOU研究会では抗酸化物質を、ポリフェール系抗酸化物質とカロテノイド系抗酸化物質に分けて分析法の確立を目指している。
ポリフェール系抗酸化物質の反応機構はラジカル捕捉反応で、詳細にはHAT(Hydrogen Atom Transfer)とET(Electron Transfer)機構がある。HATは、抗酸化物質が活性酸素種へ水素原子を与えることで活性酸素種を消去する。ETは、抗酸化物質から活性酸素種へ先ず電子の移動を行い、次にプロトンを与えることで活性酸素種を消去する。
一方、カロテノイド系抗酸化物質の反応機構は一重項酸素消去反応で、この反応は物理的消去(Physical Quenching)と化学的消去(Chemical Quenching)の2つが存在する。しかし、主には物理的消去に基づいて発揮される。物理的消去反応では、一重項酸素(1O2)がその励起エネルギーを抗酸化物質へ移すことにより基底状態(通常の酸素:3O2)に戻る。励起エネルギーを受けた抗酸化物質はそのエネルギーを熱として放出し、基底状態に戻る。 以上のことから、それぞれのAOUをAOU-PとAOU-Cとして、これらに適した分析法の確立を行っている。 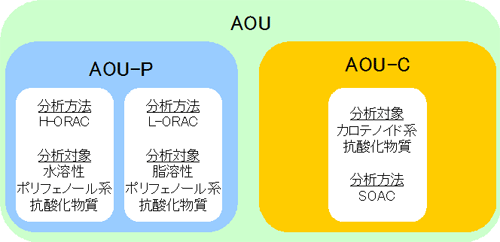 図1 AOU分析法とそれに応じた分析成分 これまでの検討から、AOU-P分析法としてORAC法を用い、ORAC分析法の標準化に向けた作業が行われている。ORAC分析法は、水溶性成分の分析法であるH-ORAC分析法と、脂溶性成分の分析法であるL-ORAC分析法に分けられる。H-ORAC分析法については、USDAのPriorらの測定方法に改良を加え、分析精度を高めた方法を確立し、論文発表(日本食科工学会誌, 57(12), 525-531, (2010)、Anal. Sci., 28(2), 159-165, (2012))が行われている。L-ORAC分析法については、標準化に向けた分析法の基礎研究は完了し、現在、多数の研究機関のご協力により、精度検証試験がなされている。
一方、AOU-C分析法としてはSOAC(Singlet Oxygen Absorption Capacity)法を用いている。この抗酸化能測定法は、AOU研究会理事の寺尾純二徳島大学教授、向井和男愛媛大学名誉教授、カゴメ株式会社が中心となり開発したものである。これまでに分析法の基礎研究がなされており、論文発表(J. Agric. Food Chem., 58(18), 9967-9978, (2010)、J. Agric. Food Chem., 59(8), 3717-3729, (2011))が行われている。今後、分析方法の標準化のため、多数の研究機関の協力による精度検証試験を予定している。 また、食品へのAOU表示については、一般社団法人食品機能表示協議会にてご検討を行っていただき、AOU研究会は、付随した情報提供を行い、AOU表示に向けた作業推進を行っている。 略歴京都大学大学院生命科学研究科修士課程修了。生命科学修士。2005年太陽化学株式会社へ入社。2007年3月AOU研究会事務局に所属し、主にAOU分析法確立に関わる。 特に、AOU-P分析法の中心となる、H-ORAC分析法の妥当性確認試験に参加、学会発表を行う。 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |
| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |

