|
栄養素と非栄養素、3次機能は非栄養素
神戸大学大学院農学研究科
金沢和樹 1.非栄養素とは
大学の講義で「栄養素という用語を定義してみてください」と質問します。不思議なことに「栄養素」の科学的定義はあいまいで、専門家でさえも十分な回答ができません。そして、多くの学生は「生命維持に役に立つもの」と答えます。役に立つものならば、水も酸素も栄養素ということになります。そこで、現在科学が理解できている範囲で定義すると、生命がもっとも必要するエネルギーの「ATPを産生できるもの」となります。そしてこの定義には大きな意味があります。ATPを産生するということは、その物質が体内で代謝分解、つまり異化を受けるということです。口から摂取した物質の化学形態が、体内では影も形もないほどに完全に分解されるということです。例えば栄養素のブドウ糖は、炭素6個の糖が解糖系で炭素3個のピルビン酸になり、TCA回路で炭酸ガスとNADHの水素イオンになります。この水素が電子伝達系でATPというリン酸結合の化学エネルギーに変換されるわけです。炭素6個の化合物が炭酸ガスと水素に分解されて化学エネルギーにかわるのです。もとの化合物の形は全く残っていません。
一方、反対語の「非栄養素」は「ATPを産生できないもの」です。つまり、非栄養素は体内でエネルギー代謝に関わる酵素に認識されず、異化という分解を受けないものです。生命維持に必要なATPをつくれない物質を生命は必要としません。そこで生命は非栄養素に次のいずれかの処理をします。「消化管上皮細胞内で非栄養素を処理する酵素や輸送担体で認識して糞便に排泄する」、あるいは、「体内に吸収して異化せずに食べたときの化学形態を維持したまま体内循環させてできるだけ速やかに排泄する」。後者の非栄養素は、影も形もないどころか形をほぼ完全に維持したまま私たちのからだの中を巡ります。そして体内の酵素などに認識されるのではなく、無作為に、その非栄養素の化学構造と物性に合ったタンパク質のポケットなどに作用します。ごく微量でも、酵素や受容体タンパク質のポケットに入り込んでその機能を変えたり、電子の授受を阻害したり促進したりします。これを、現代の食品化学や栄養化学では「機能性」(正しくは3次機能。1次機能は栄養機能、2次機能は味覚など)といっています。つまり、機能性食品の開発とは、非栄養素の探索です。 2.機能性探索のポイント
筆者は食品・栄養化学を専門としていますが、学生たちが研究を始める前に釘を刺すように話すことがもう一つあります。食品や栄養はもっとも身近な課題だからといって、毎日の食事のように安易に考えて研究してはならない。食物は単なる物ではない、生命がつくったものだから生命維持に必要な成分をまんべんなく含んでいる。そして、それを食べるヒトも生命体である。生命が生命を食べる。これを研究するためには、生命が十分に理解できていなければならない。おそらく学問の中でもっとも難しい学問だ。では、どのように生命を理解すれば食品・栄養化学の研究ができるのか。食事とは、生命が異なる生命を食べることである。そして、食べた生命は、食べられた側の生命を、自分のからだの中に決してそのまま取り込まない。もしそのまま取り込めば、食べられた生命体の機能が食べた生命体のからだの中で機能することになる。つまり、食物を食べることで別の生命体になってしまうことを意味する。そんなことはありえない。ならば、「他の生命体の成分をそのまま取り込まない」という選別はどこで行われるのか。消化管や皮膚などの消化吸収を担う上皮である。この消化吸収システムを理解することが、生命が生命を食べるということを理解する第一歩になる。つまり、機能性成分の探索は、消化吸収システムを理解することだ。
非栄養素は生命に必要なエネルギーをつくり出しません。ですから生体にとって非栄養素は不要です。「健康維持に貢献するではないか」というのは人の勝手な解釈で、生体は代謝の弊害になる非栄養素をできるだけ体内に取り込まないように、あるいは取り込んでも速やかに排泄しようとします。ならば逆に、体が少しでも多く取り込むような成分、あるいは速やかに排泄しないような成分を選び出せばそれは間違いなく機能性食品(健康食品、サプリメント)になります。ではどのようにすればいいか。からだが非栄養素を処理するのは、その吸収段階の腸の上皮細胞です。摂取した非栄養素はほぼすべてが腸上皮細胞に取り込まれます。しかし、細胞内で速やかに「抱合」という物質を不活性化する代謝を受けます。非栄養素の水酸基やアミノ基などの生理活性を示す官能基をウロン酸あるいは硫酸でマスクするのです。官能基がマスクされるとその非栄養素は機能性を発揮できなくなります。また硫酸やウロン酸が付くと、その物質の水溶性が著しく増します。細胞は、水溶性が高い物質は容易に細胞外に、腸上皮細胞の場合は管腔側、つまり糞便側に排泄します。ウロン酸や硫酸で抱合するUDPグルクロン酸転移酵素や硫酸転移酵素の活性はきわめて高く、抱合物を細胞外に排泄する輸送担体も高い活性を示します。そして非栄養素は、これらの酵素や輸送担体が認識できない低濃度(Km 値以下の濃度)しか、ヒトの血中には取り込まれません。したがって、いくらたくさん食べても、ごく微量しか食べなくても、食べた量と関係なく、体内を循環する非栄養素の濃度は同じで、ごく微量です。ところが、その微量でも、非栄養素は異化を受けない物質で、体内に存在する物質とは異なる物質ですから、たいへん顕著な生理活性を示します。 そして、腸上皮細胞が非栄養素を処理するのを逃れる食品成分を探し出せば、その成分は私たちの体内を食べた時のそのままの化学形態で循環して何らかの作用を示しますから、その成分は機能性成分ということになります。では、上皮細胞の処理を逃れるとはどのようなものがあるのでしょうか。これまでに機能性が認められている成分を、上皮細胞の処理を逃れている機序で、表1に分類してみました。 表1 腸上皮細胞内での挙動で機能性成分を分類
3.機能性成分発掘戦略
表1の分類のいずれかに当てはまる新規の成分を、食経験がある植物の中から探し出せば、それは機能性食品になります。そこで表1の分類のそれぞれを、例をあげながら説明してみます。
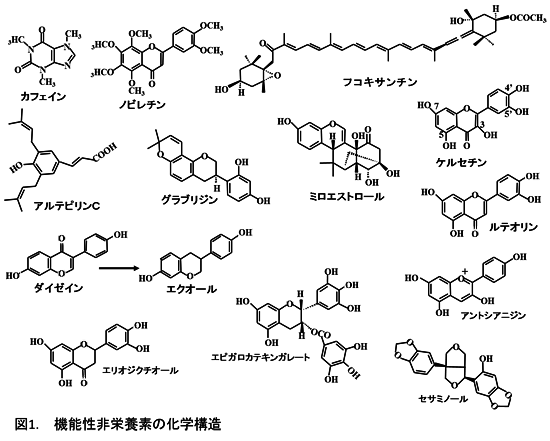 もう一つは、テルペノイド類です。とくに、テトラテルペノイドのカロテノイド類は、栄養素の脂肪酸と同様に、その化学構造がほとんど変化を受けずに単純拡散で体内に吸収されます。カロテノイドの中で、β-カロテンやα-カロテンは体内でその一部がビタミンAに代謝されるので、過剰摂取になる可能性があり、安全性に留意しなければなりません。しかし、キサントフィルとよばれる化学構造に酸素を含むカロテノイドはプロビタミンA活性を持たないので過剰摂取による毒性の懸念はありません。例えば、アスタキサンチンやフコキサンチン(図1)を動物に多量に与え続けると、皮膚や体毛がそのキサントフィルの色、ピンクや橙色に染まりますが、全く異常は認められません。そして、いずれも顕著な生理活性を示します。他のテルペノイドも、比較的吸収率が高く、多くのものが抱合を受けません。そして、セルンボンなどのテルペノイドに機能性が認められています。 (2)抱合酵素が接近しにくい化学構造とは、抱合酵素が抱合の標的とする官能基が疎水基で隠されているような成分です。例えば、アルテピリンCは抱合酵素が標的とする水酸基の左右に疎水性のプレニル基が付いています(図1)。抱合酵素は水溶性残基を付加する酵素ですから、当然その基質認識部位は親水性アミノ酸で構成されています。疎水性のプレニル基はその認識部位に接近できないために、抱合反応を受けにくいと思われます。実際に経口投与でアルテピリンCを与えると、血中から与えたときの化学形態、つまりアグリコン形態で検出されます。そして、顕著な機能性を示します。同じように、顕著な機能性があるので、昔から重宝されている成分に、甘草のグラブリジン、東南アジア産のクズのミロエステロールがあります(図1)。いずれも、抱合酵素の標的となる水酸基の一部がプレニル基で覆われています。そして、経口摂取した場合に、血中から比較的高濃度で検出されます。 (3) 抱合後も機能性を残している成分とは、抱合を受ける標的となる官能基を多数持っている化合物です。抱合はすべての官能基に行われるのではなく、通常一ヶ所だけが抱合を受けます。一ヶ所でも抱合を受ければ親水性が高まりますので、酵素などのタンパク質に作用してその活性を調節するという機能性はなくなります。しかし、抗酸化活性は残っている場合があります。例えばケルセチンは5つ水酸基を持っていますが(図1)、このうち5位の水酸基の水素は隣のキノンと水素結合をしていますから抱合を受けにくく、残りの4つが抱合酵素の標的になります。もし3か7位が抱合を受ければ3‘と4’は水酸基のまま残ります。水酸基が隣接した構造をカテコールといいますが、カテコール構造は顕著な抗酸化活性を示します。ケルセチンのようなカテコール構造を持つポリフェノールは、カテコール以外の水酸基が抱合されて体内に取り込まれた場合、その量が少量であっても顕著な抗酸化能を示します。他にも、緑茶のエピガロカテキンガレート、ナスなどのアントシアニジン、レモンのエリオジクチオール、ゴマ油のセサミノールなどがあります(図1)。 (4)は主に腸内細菌の役割によります。代表的な例が大豆イソフラボンのダイゼインです。ダイゼインそのものにも機能性はあるのですが、それが腸内細菌によって代謝された産物のエクオールは(図1)、より吸収率が高く、抱合を受けにくく、エストロジェン様活性が顕著です。他のフラボノイドも、摂取した一部は腸内細菌によって桂皮酸類や安息香酸類まで分解を受けます。桂皮酸や安息香酸のような単環のフェノールの体内動態と機能性は、まだ十分に研究されていませんが、体内吸収されやすくて抱合も受けにくいという報告が多くあります。そして、カテコール構造をもっていれば、それほど顕著ではないが、抗酸化活性などの機能性が期待できます。 (5)は、抱合を受けて非活性型となって体内に吸収されるが、必要に応じて体内で活性型に変えられて機能性を示すという非栄養素です。たいへん都合がいい非栄養素ですが、これは食品による疾病予防の意味では、きわめて重要です。繰り返しの説明になりますが、生体はエネルギー源にならないものは不要で、異物として認識し、抱合してできるだけ速やかに体外に排泄しようとします。もし仮に抱合を受けていない化学形態、アグリコン形態で非栄養素が体内を循環すると、その非栄養素は体内のタンパク質の疎水ポケットに入り込み、タンパク質の機能を変えてしまいます。すると、生体はそのタンパク質をつくり直さなければなりません。そのためには生合成のエネルギーを多量に消費しなければなりません。一方、抱合を受けた非栄養素ならば水溶性が高い化学形態ですから、タンパク質の疎水ポケットに入り込まず、血流に混ざって腎臓に運ばれ、速やかに尿に捨てられます。つまり、抱合を受けた非栄養素は通常はからだに何も作用せずに尿へ捨てられるのです。しかし、それでは病気予防にはなりません。ところが、からだのどこかに異常が発生すると、それが炎症のような異常である場合は、炎症がおこった組織からβ-グルクロニダーゼという酵素が血中に漏出します。β-グルクロニダーゼは抱合基を外す酵素です。つまり、抱合体をアグリコンに戻す、非活性型の成分を活性型に戻します。もし、抱合を受けていた非栄養素が顕著な機能性を持っている成分であれば、炎症細胞はβ-グルクロニダーゼでそれを炎症が修復できる化学形態に活性化したことになります。この例として報告されているのはケルセチンとルテオリンです(図1)。他にもあると思えますが、まだ十分に研究されていません。このような非栄養素は生体が健常な時は生体に全く負担を与えることなく速やかに排泄され、異常が生じたときだけ顕著な機能性を発揮することになります。正に、食による疾患予防です。 (6) は、複数の非栄養素を組み合わせると、そのいずれかの非栄養素の体内有効性が増し、それが体内で機能性を発揮するという意味です。これも、日常食生活を指しています。研究者が機能性を解析するときは、一種類の物質をできるだけ純粋にして用います。また、そうしなければ何が効いているか判らないので、学術論文としても受理してもらえません。しかし、単一の物質で試験すると機能性が検出できないことが多くあります。一方、ヒトが実際に毎日食べているのは、単一な一種類の物質でなく、複数の物質です。そして、「何々のハーブは何々に効く」「何々の食品は病気を予防する」、という伝承が多くあります。実はこれは、複数の非栄養素を同時に摂ると、腸上皮細胞内での抱合反応が変わり、それによっていくつかの非栄養素の体内濃度が顕著に上がるからです。どのように変わるのかはまだ研究の途上ですが、いくつかの非栄養素を組み合わせると、その中の一つの非栄養素の体内濃度が、それを単独で摂取した場合に比べて数十倍に上がることがあります。そこで、この組み合わせを、機能性が顕著な非栄養素を主体にしてデザインすれば、有効なサプリメントを創出することができます。もちろん、組み合わせの種類はたくさんあります。そして、組み合わせはそれをデザインする人のアイデアによりますから、この(6)は、多様な発展が期待できる機能性食品開発戦略です。 (7)最後の一つが、現在世界的に研究が盛んになっている食物繊維です。食物繊維の定義は「人の消化官で消化吸収されない多糖」です。腸内細菌によって分解され、体内に吸収されるという報告もありますが、それは部分的に分解されるという意味です。消化吸収されないことに食物繊維の意味があります。とくに水溶性が高い、硫酸基やウロン酸基を持っている食物繊維、シイタケのレンチナン、姫マツタケのアガリクス、褐藻のフコイダンは、全くあるいはごく一部しか消化吸収されません。体内に入り込まないので、体内蓄積もせず、副作用がありません。これが重要な点です。体内に入り込まないのに、どのようにして機能性を発揮するのか。人は従属栄養生物ですから、食べたものが栄養素か非栄養素であるのかを認識して区別するシステムをもっています。栄養素でない多糖を認識する受容体を消化管上皮細胞に持っており、それを排泄するように応答します。上皮細胞のインターロイキンIL-8のmRNA発現を調節したり、NADPH酸化酵素1の発現を促したりします。さらに、血球の炎症性サイトカイン分泌を調節します。上皮細胞と血球がどのようにクロストークしているのかはまだ研究中ですが、これら応答が、ヒトにとっては好ましい免疫調節につながっていることは明らかです。典型的な例が、乳酸菌などの菌の細胞壁を構成する多糖にヒトの消化管上皮細胞が応答して、アレルギー軽減などの免疫寛容を示すことです。食物繊維と免疫応答システムの解明はこの数年のトピックス研究課題になると思います。以上のように、食品成分の機能性の機序を、消化管の役割から観て7つに分けましたが、このいずれか一つに当てはまる新規物質を見つけ出せば、それは機能性成分になります。この研究は、まず、対象とする試料を分析し、含まれる成分を同定することから始めます。そして、その化学構造を見て、上記(1)から(7)のいずれかに当てはまれるか否かを検討します。そのいずれか、例えば(2)に当てはまれば、(2)にみあった研究、動物で体内動態を測定するなどの試験をします。その時同時に、予測する機能性の試験も同じ動物で行います。次にヒトで数点の血中濃度測定をします。最終的に、細胞で作用機序を解明します。機能性食品の開発の一つのストーリーです。 略歴
金沢 和樹(かなざわ かずき)
神戸大学大学院農学研究科 教授 京都大学博士(農学) 京都大学大学院農学研究科食品工学専攻修了後神戸大学農学部助手、米国ブランダイス大学大学院生化学部研究員、神戸大学農学部助教授を経て現職。 農学教育部会監事、アスタキサンチン研究会理事、日本酸化ストレス学会理事兵庫県丹波黒振興協議会理事、AOU(農産生鮮物抗酸化表示推進員会)理事などを務める。 主要著書間違いだらけのサプリメント選び(双葉社)、健康食品・サプリメントを科学するウソ・ホント(日本生活協同組合連合会)栄養機能化学(朝倉書店)何を食べるべきか(コープ出版)その他分担執筆多数。サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |
| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |

