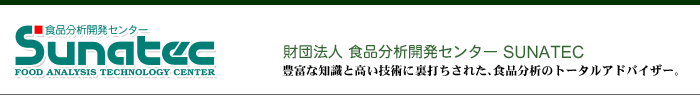|
食品工場の微生物制御への紫外線の利用技術
食品・微生物研究所 所長 内藤茂三
1.はじめに 光は通常、紫外線、可視光線及び赤外線を含めた波長1nmから1mmまでの範囲の電磁放射線のことのことをいう。ここで放射線とは空間を伝わるエネルギーの流れのことであり、そのうちエネルギーの実体が光子であるものを電磁放射線という。紫外線の殺菌効果は、光子が菌体構成分子に直接作用した結果の直接効果と、菌体をとりまく分子、例えば酸素、光増感分子などが関与する間接効果がある。紫外線が殺菌効果を持つためには、そのエネルギーが菌体成分に吸収されなければならない。紫外線の殺菌効果の波長依存性を検討すると微生物の菌体の核酸成分であるチミンの吸収曲線に一致する。即ち、254nmを中心とする紫外線は微生物菌体ゲノムに吸収され、作用することによって殺菌作用を発揮する。このような理由から食品工場での食品や環境殺菌に紫外線を利用して効果を十分に発揮するためには、種々の注意が必要である。表面殺菌であるので紫外線の有効利用と処理後の再汚染防止が重要となる。
2.紫外線発生装置の種類
紫外線発生装置の種類を表1に示した。光ファイバー式紫外線殺菌装置は従来のランプでは光が到達しなかった場所でも殺菌できる装置である。
表1 紫外線発生装置の種類
3.紫外線の一般的性質 紫外線は波長領域によってUV-A(380〜315nm)、UV-B(315〜280nm)、UV-C(280〜100nm)に分類され、種々の光化学反応に用いられている。食品工業でよく用いられるランプは合成石英ガラスで構成される低圧水銀ランプであり、その主波長は184.9nmと253.7nmでUV-Cに属する。これらの波長の有する光エネルギーは大部分の有機化合物の原子間結合のエネルギーよりも大きく、その結合を切断し揮発性物質に分解することが可能である。即ち、184.9nmの光と酸素の反応によりオゾン発生を伴うと同時に253.7nmの光とオゾンの反応によってラジカル酸素が生成され、UV 光とラジカル酸素の複合的な化学反応により有機物の分解が促進される。この反応は UV/O3 ドライ洗浄として液晶基板ガラスやシリコンウエハーの精密洗浄、ポリエチレンフィルムの親水化処理に用いられている。
紫外線の食品工業への利用における利点を以下に示す。
4.紫外線の殺菌機構 紫外線が殺菌効果を有するためには、そのエネルギーが菌体成分に吸収されなくてはならない。紫外線領域では菌体の核酸成分(チミン)の吸収量線とほとんど一致する。即ち253.7nmを中心とする紫外線は菌体ゲノムに吸収され、作用することにより殺菌される。紫外線照射による菌体ゲノムの変化のうち殺菌に関与するのはピリミジン二量体の形成である。つまりチミン二量体の形成である。230、250、280各nm波長のDNA不活化の原因は、それぞれ60%、90%、80%がチミン二量体のよるとされている。チミン二量体が一つできるとDNAの水素結合は前後4塩基にわたって切れるとされ、コード不能領域となり死滅する。
このように紫外線は光子のもつエネルギーにより、生体高分子を直接励起して変化させるか、増感分子を励起して活性酸素を発生することによって殺菌作用を持つことができる。紫外線はDNAに吸収され、栄養細胞ではシクロブタン型チミン二量体をつくり、この傷が修復できない時に死となる。この修復能によって紫外線耐性が決まる。芽胞は修復しやすいチミン負荷体をつくり、したがって紫外線耐性である。 従来の紫外線殺菌灯は、単位長さ当たりの入力(ランプ負荷)が約0.4W/cm程度であったが、ランプの表面温度を制御することにより約5W/cmまでに負荷を高め、紫外線照度を100mW/cm2前後までにすることが可能となった。通常、低圧水銀ランプの紫外線出力は内部の水銀蒸気圧によって変化し、雰囲気温度が40℃で最も紫外線出力が高くなる。この条件を満たす場合には高負荷に耐え、寿命特性が得られるような電極の開発、最適水銀蒸気圧が得られるような発光管壁温度制御法の開発、寿命に耐える封入ガスや石英ガラスの開発が行われた結果、照射器窓面で100mW/cm2の紫外線出力を得ることが可能となった(高出力紫外線ランプ)。 5.紫外線の殺菌作用とその効果
微生物には種々の種類があり、それぞれの形態が異なっているため、これらを殺菌するのに紫外線照射量は一定ではなく大きく異なっている。紫外線の照射量(mW・sec/cm2)は紫外線の照度(mW・cm2)と照射時間(sec)の積で表され、微生物の生残率は次の式で表される。
S=P/Po=exp(-Et/Q) S=生残率 Po=紫外線照射前の微生物菌数 P=紫外線照射後の微生物菌数 E=照度 t=照射時間 Q=Sを1/e=36.8%にするのに必要な照射量(照度×照射時間) 紫外線抵抗性の微生物を殺菌するためには照度と照射時間を大きくする必要がある。 微生物の紫外線感受性は微生物の種類により異なり、一般に、グラム陰性細菌が最も感受性が高く、グラム陽性菌、酵母、カビの順に紫外線抵抗性となる。また細菌の芽胞は栄養細胞に比べて紫外線抵抗性が高い。従来15W紫外線ランブ(殺菌灯)では大腸菌を99.9%殺菌するのに50秒、黒カビでは約40分間照射が必要であった。高出力紫外線ランプでは大腸菌が0.05秒、黒カビが2.2秒で死滅する。 11〜95%RHに調整したBacillus 属芽胞及びClostridium 属芽胞を紫外線照度80mW/cm2、5秒間、20℃で処理を行った結果、芽胞の殺菌効率は11〜13%RHの低水分領域で低く、80〜95%RHの高水分領域で高いことを認めた。 80%RHに調整したBacillus 属芽胞及びClostridium 属芽胞を紫外線照度80mW/cm2、5〜20秒間、20℃で処理を行った結果、いずれの菌株も紫外線照射時間の延長に伴い、著しく殺菌効果が高まった。 表2に紫外線の波長別殺菌効果を示した。 表2 紫外線の波長別殺菌効果
6. 紫外線の食品工業への利用と課題
食品工業では二次汚染菌により食品が変敗及び腐敗する例が多いので、二次汚染防止に工場空気殺菌に紫外線が利用される場合が最も多い。また直接食品に照射する方法もとられている。紫外線の照射方法は、包装直前にする方法と、紫外線透過フィルムで包装した後にする方法とがある。いずれにしても紫外線殺菌は表面のみの殺菌であるため、非照射物の表面の形態が殺菌効率を決定する。食品工業では次に示すように環境の殺菌に最も多く用いられている。
環境の殺菌
食品の殺菌
表4に包装材料の紫外線(253.7nm)の透過率を示した。 表4 包装材料の紫外線(253.7nm)の透過率
紫外線は電離放射線に比べるとそのエネルギーは少なく、約49eVである。従って殺菌力も物質透過力も電離放射線に比べて弱い。微生物の紫外線感受性はグラム陰性菌(Esheirichia coli,Neisseria catarrhalis,Proteus vulgaris,Salmonella ,Serratia, Shigella,Pseudomonas ) が最も大きく、カビが最も抵抗力が大であって、グラム陰性細菌、酵母、細菌芽胞がこの中間に位置している。 紫外線の食品への利用例としては、リンゴ果汁、ランチ用肉、牛肉片、ウインナーソーセージ、生魚、食肉、はんぺん、かまぼこ、ゆば、生麺、餃子の皮、シュウマイの皮、半生麺、饅頭の皮、サイダー、ラムネ、ミネラルウオーター、大豆タンパク、輸入エビがある。形態及び付着菌数及び菌叢の相違により又、処理方法によりその効果が大きく変化する。目的を明確にして行う必要がある。更に個々の食品についてそれぞれの処理方法を工夫することも必要である。紫外線は短波長であるため、ある程度のエネルギーを持っており、酸化力は強い。食品の脂質の酸化の影響を考えることも大事である。 紫外線による果実及び野菜の表面殺菌に関する報告は極めて少ない。しかしトマト、キュウリ、リンゴ、ミカン、レタス、パセリ、セロリに関しては一部行われている。果実や野菜は表面形態が大きく異なり、付着する微生物の数も多い。特定の微生物をターゲットとして処理することは有効である。 製品に直接紫外線を照射する場合には、紫外線のもつエネルギーによって照射物が劣化する場合があるため、予め劣化テストを行い、適切な紫外線照射量を検討する必要がある。 紫外線処理後の二次汚染を考慮すると、包装された食品を包装材料の上から紫外線処理を行いトタールサニテーションの確立を目指すべきである。 従来の化学的殺菌剤に比較して残留せず、異臭もしない殺菌剤として有効であり、合成保存料に代わる保存性向上の手段の一つとしての応用が考えられる。 7.紫外線の安全性紫外線は光であるため人体に対しては、眼と皮膚が影響を受ける。眼の場合、角膜が侵され充血、眼痛が起こるが、一時的な症状であり軽度の場合は1日程度で回復する。
また角膜の組織破壊も2週間程度で回復される。角膜の場合は数時間後に皮膚が赤くなり痛みを感じ、日焼けと同じ症状がでる。ひどい場合は浮腫を伴う 1.眼
紫外線の過度の照射により眼の表層が侵される。紫外線の照射を受けて約5時間後に眼が充血しはじめ、12時間後に眼がごろごろし、ひどく眼痛が起こり、眼をあけて物を見ることができなくなる。ひどい場合は一時的に視力が低下する。多くの場合は一時的症状でそのまま安静にしていれば24時間程度で自覚症状がなくなり角膜の組織破壊も2週間程度で修復される。眼の黒い部分が一時的に白くなるが、時間とともに回復する。
2.皮膚
紫外線照射後、6〜8時間で皮膚が赤くなり(紅班が始まり)痛みを感じるようになり、過度の場合は浮腫を伴う。ACGHI (アメリカ労働衛生専門官会議)では、眼及び皮膚に対する光放射の有害性に対する作業環境上の閾値として光照射のTLV (Threshold Limit Values ) を勧告している。このTLVはほとんど全ての労働者が悪影響を被ることなく眼及び皮膚に繰り返し被照射しても差し支えない条件であり8時間を1期として所定の値を超えてはならないとしている。紫外線の照射を繰り返し受ける可能性のある場合には、安全性に十分注意する必要がある。
眼又は皮膚に対する紫外線(210〜315nm)照射の被曝許容量(TLV)を表5に示した。 表5 眼又は皮膚に対する紫外線(210〜315nm)照射の被曝許容量(TLV)
サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |
| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |