| ◆ HOME >魚介類に含まれるヒ素化合物の毒性および生体内代謝 |
 |
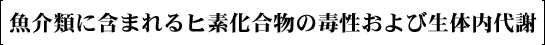
東京海洋大学食品生産科学科
塩見一雄
1. はじめに
ヒ素(As)は代表的な有害元素で、古くから自殺や他殺に用いられてきただけではなく、鉱山労働者における健康被害や鉱山周辺の環境汚染の点でも問題にされてきた。さらに中国やバングラデシュ、インドなどの東南アジアでは井戸水のヒ素汚染が長年にわたって進行し、1990年頃から大勢の住民に皮膚がんなどの健康障害が顕著にみられるようになっている。わが国では1955年に発生したヒ素ミルク中毒事件という大規模な食中毒(患者12000人以上、死者130人)により、ヒ素の毒性が広く知れわたっている。ヒ素はあらゆる生物に含まれているが、その含量(湿重量換算)は陸上生物(<1 mg/kg)と比べると海洋生物(1-100 mg/kg)は非常に高く、ヒ素ミルク中毒事件の原因となった粉ミルク中のヒ素含量(20-30 mg/kg)を超えるものも多い。そのため日常生活におけるヒ素暴露の最大の源は魚介類であり、魚介類に含まれるヒ素の食品衛生上の安全性が古くから懸念されてきた。本稿では食品衛生の観点から、魚介類に含まれるヒ素化合物の構造と毒性・生体内代謝に関するこれまでの知見を概説する。
2.魚介類に含まれるヒ素化合物の化学構造
2.1. 存在状態
魚介類に含まれるヒ素化合物については、化学構造の解明に先立って無機態か有機態か、水溶性か脂溶性かという存在状態がまず検討された。 図1には、魚類6種(マイワシ、サンマ、マアジ、マサバ、ブリ、マガレイ)、原索動物1種(マボヤ)、棘皮動物2種(マナマコ、ムラサキウニ)、甲殻類2種(タイショウエビ、サクラエビ)、軟体動物5種(サザエ、アサリ、ミズダコ、スルメイカ、アルゼンチンイレックス)、環形動物1種(ゴカイ類)、海藻(褐藻)3種(ヒジキ、マコンブ、ワカメ)の合計20種魚介類について筆者らが無機態ヒ素と有機態ヒ素を分別定量した結果を示す。20種魚介類の中でヒジキのみは無機ヒ素が総ヒ素の約70%を占めていたが(ヒジキについては無機ヒ素が総ヒ素の半分あるいはそれ以上を占めることはほかの多くの研究者も報告している)、その他の魚介類においては含まれるヒ素の大部分は有機態であった。ヒ素化合物の毒性は一般に3価無機態(亜ヒ酸)>5価無機態(ヒ酸)>有機態とされているので、ヒジキを除くと食品衛生上好ましい結果であったといえる。一方、ヒ素化合物は水溶性か脂溶性かという点に関しては、筆者らは上記魚介類のうち海藻3種を除く17種で検討したが、いずれの魚介類においても大部分は水溶性であった( 図2)。以上の筆者らの結果と他の研究者の報告とを含めて、魚介類に含まれるヒ素化合物は主として水溶性の有機態であると結論することができる。 2.2. 水溶性ヒ素化合物の構造
1977年にEdmondsらは、オーストラリアイセエビ Panulirus cygnusの筋肉から水溶性ヒ素化合物を単離し、機器分析によりトリメチル態のアルセノベタインであることを証明した。この研究が魚介類に含まれるヒ素化合物の構造を解明した最初の例で、その後の精力的な研究により魚介類から各種水溶性有機ヒ素化合物が見いだされている。魚介類に含まれる主要な水溶性ヒ素化合物(無機ヒ素化合物も含む)の構造を 図3に示すが、水溶性有機ヒ素化合物はすべてメチル化態である。海水中のヒ素化合物は無機態(主としてヒ酸)であるので、魚介類は(少なくとも海水から直接ヒ素を吸収している海藻は)取り込んだ無機ヒ素をメチル化していることになる。魚介類における無機ヒ素から各種メチル化ヒ素化合物に至る代謝経路は十分にはわかっていないが、毒性の高い無機ヒ素に対する生体防御として魚介類は無機ヒ素をメチル化していると推測される。 海洋動物に広く分布している水溶性有機ヒ素化合物は、トリメチルアルシンオキサイド、アルセノベタイン、アルセノコリン、テトラメチルアルソニウムイオンである。このうちもっとも主要なヒ素化合物はアルセノベタインで、多くの海洋動物においてアルセノベタインがヒ素化合物の大半を占めている。しかし、一部ゴカイ類では無機ヒ素が、イソギンチャク類ではアルセノコリンやテトラメチルアルソニウムイオンが、一部カイメン類ではアルセノシュガーが主成分である(カイメン類には褐虫藻と呼ばれる単細胞藻類が共生しており、アルセノシュガーは褐虫藻が合成している可能性がある)というように例外も認められている。また、ハマグリは特殊で、鰓以外の部位の主成分はアルセノベタインであるのに対し、鰓ではなぜかテトラメチルアルソニウムイオンが主成分となっている。なお、トリメチルアルシンオキサイド、アルセノベタイン、アルセノコリン、テトラメチルアルソニウムイオンのヒ素(As)を窒素(N)に置き換えた化合物は、それぞれトリメチルアミンオキサイド、グリシンベタイン、コリン、テトラメチルアンモニウムイオン(テトラミン)で、生体成分としてよく知られている。トリメチルアミンオキサイドは特に魚介類に多く、浸透圧調節物質として機能している。グリシンベタインは水産無脊椎動物での含量が高く、これら動物を食品として摂取したときの甘味やうま味に関わっていると考えられている。コリンは神経伝達物質アセチルコリンの前駆体で、遊離またはリン脂質の構成成分として生物に広く分布している。テトラミンはヒメエゾボラやエゾボラモドキなどのエゾバイ科巻貝(ツブとかツブ貝として流通している)の唾液腺に高濃度に含まれており、しばしば食中毒の原因毒となっている。
一方、海藻の水溶性有機ヒ素化合物は5-デオキシリボフラノースを基本骨格とするやや複雑な構造をとっており、アルセノシュガー(ヒ素含有糖)と総称されている。主要なアルセノシュガーは、5-デオキシリボフラノースのC5位にオキソジメチルアルセノ基(CH3)2As=Oが結合したオキソ型である。5-デオキシリボフラノースのC1位に結合しているアグリコン中の特徴的な官能基によって、オキソ型アルセノシュガーはさらにグリセロールタイプ、リン酸タイプ、スルホン酸タイプ、硫酸タイプの4つにわけられている。オキソ型アルセノシュガーのほかに、5-デオキシリボフラノースのC5位に(CH3)2As=S基が結合したチオ型や(CH3)3As+基が結合したトリメチル型も微量成分として検出されている。海藻のうち非常に特殊な例は前述したヒジキで、含まれるヒ素の約半分はアルセノシュガーであるが残りの半分は無機ヒ素(ヒ酸であることが証明されている)である。
2.3. 脂溶性ヒ素化合物の構造
これまでに報告されている魚介類の脂溶性ヒ素化合物を 図4に示すが、水溶性ヒ素化合物と比べると含量が低いため単離が困難で、化学構造は推定の域を出ないものも多い。1988年にワカメから脂溶性ヒ素化合物が単離され、各種機器分析によりホスファチジルアルセノシュガーであることが明らかにされた。その後、脂溶性ヒ素画分の化学分解や酵素(ホスホリパーゼD)分解によって生成する水溶性ヒ素化合物の分析結果に基づき、ホシザメの肝臓にはジメチルアルシン酸含有リン脂質およびアルセノコリン含有リン脂質が、オーストラリアイセエビの肝膵臓にはホスファチジルアルセノシュガーとホスファチジルアルセノコリンが、スルメイカの肝臓にはホスファチジルジメチルアルシン酸およびジメチルアルシン酸含有スフィンゴミエリンが、コンブ類にはホスファチジルアルセノシュガーが存在すると報告されている。これらの結果から、魚介類に含まれる主要な脂溶性ヒ素化合物はリン脂質(グリセロリン脂質およびスフィンゴ脂質)であると考えられる。比較的最近、必ずしも主成分ではないがリン脂質以外の脂溶性ヒ素化合物として、タラの肝油に6種類のジメチルアルシン酸含有脂肪酸が、カペリン(シシャモの仲間)の油に3種類のジメチルアルシン酸含有炭化水素が検出されている。 3. 魚介類に含まれるヒ素化合物の哺乳類に対する毒性
各種水溶性ヒ素化合物のマウスに対する急性毒性(経口投与)およびマウス由来の各種細胞に対する毒性を 表1にまとめた。脂溶性ヒ素化合物の毒性に関するデータはまだ得られていない。魚介類に含まれる水溶性ヒ素化合物の急性毒性に関しては、アルセノベタイン、アルセノコリンおよびトリメチルアルシンオキシドは亜ヒ酸の約1/200あるいはそれ以下ときわめて弱く、実質的に無毒である。テトラメチルアルソニウムの急性毒性はやや高いが(食中毒原因毒である窒素同族体のテトラミンの急性毒性よりは弱い)、亜ヒ酸の約1/25でジメチルアルシン酸と同程度である。一方、海藻の主要なヒ素化合物であるアルセノシュガーについては、実験に必要なだけの十分量の精製品(または合成品)を調製することが困難なため急性毒性は調べられていない。しかし、オキソ型グリセロールタイプの合成アルセノシュガーを用いた細胞増殖阻害実験により、アルセノシュガーの繊維芽細胞に対する毒性は亜ヒ酸の1/1200、肺胞マクロファージに対する毒性は亜ヒ酸の1/1600とわずかで、腹腔マクロファージに対しては増殖阻害ではなく増殖促進効果を示すという興味深い事実も明らかにされている。さらに、ヒト繊維芽細胞を用いた染色体異常誘発試験においても、オキソ型グリセロールタイプのアルセノシュガーの毒性はヒ酸や亜ヒ酸より著しく低いことが明らかにされている。これらのデータから、アルセノシュガーの哺乳類に対する毒性は無視できるレベルであると考えられるが、オキソ型グリセロールタイプ以外のアルセノシュガーでの検討も望まれる。 4. 魚介類に含まれるヒ素化合物の哺乳類における代謝
4.1. 水溶性ヒ素化合物の代謝
海洋動物に広く含まれている水溶性有機ヒ素化合物であるアルセノベタイン、アルセノコリン、トリメチルアルシンオキシドおよびテトラメチルアルソニウムイオンについては各種実験動物における代謝が調べられ、いずれも腸管から吸収されるが非常に短時間(48-72時間)でほとんどすべてが主として尿中に排泄されることが明らかにされている(図5のアルセノコリンの例を参照のこと)。排泄速度は無機ヒ素と比べると明らかに早い。アルセノベタインとテトラメチルアルソニウムイオンは体内代謝を受けることなくそのまま、アルセノコリンは大部分がアルセノベタインに酸化されて排泄される。トリメチルアルシンオキシドの場合、大部分はそのまま尿中に排泄されるが、ごく一部はトリメチルアルシンに還元されて呼気中に排泄される。
海藻の水溶性有機ヒ素化合物であるアルセノシュガーの哺乳類における代謝に関しては、海藻抽出物、海藻粉末あるいはアルセノシュガーの部分精製品を用いた初期の研究において、摂取ヒ素は主としてジメチルアルシン酸に代謝され、大部分が短時間で尿中に排泄されることが示唆された。その後オキソ型グリセロールタイプの合成アルセノシュガーを用いたヒトでの代謝実験が行われ、主要な代謝産物はジメチルアルシン酸であること、主要な排泄経路は尿であることが再確認された。しかし、摂取ヒ素の4日間での排泄率は4-95%(被験者6人)であったというように、排泄については個人差が著しいことを指摘する報告もある。また近年、ジメチルアルシン酸については発がんプロモーター作用が報告されているし、膀胱がんにおいては発がんイニシエーター(=発がん物質)として働くことも示唆されているので、アルセノシュガー由来のジメチルアルシン酸による生体影響については今後の検討が望まれる。
4.2. 脂溶性ヒ素化合物の代謝
脂溶性ヒ素化合物の代謝に関しては、タラ肝油を摂取したヒトの尿中にジメチルアルシン酸およびジメチルアルシン酸含有脂肪酸を検出したという報告が唯一であった。用いたタラ肝油中のヒ素化合物は不明であるが、代謝産物を考慮するとジメチルアルシン酸含有脂肪酸が主であったと考えられる。いずれにしても魚介類に含まれる主要な脂溶性有機ヒ素化合物であるリン脂質の代謝に関してはまったく知見が得られていなかったので、筆者らはごく最近、ホスファチジルアルセノコリンを合成してマウスにおける代謝を検討した。その結果、マウスに経口投与したホスファチジルアルセノコリンの大部分は腸管から吸収されること、体内のホスホリパーゼDによる作用を受けてアルセノコリンが遊離され次いでアルセノベタインに代謝されること、水溶性ヒ素化合物と比べるとかなりゆっくりではあるが144時間で約90%は尿中に排泄されることが判明した( 図5)。アルセノコリンを経口投与した場合はすぐにアルセノベタインに酸化されて早い時間で排泄されることを考慮すると、ホスファチジルアルセノコリンからのアルセノコリンの遊離反応が律速になって全体的に排泄が遅くなると推定される。 5. おわりに
魚介類に含まれるヒ素化合物については、その存在状態は、化学構造は、毒性は、代謝は、と順を追って系統的に研究が行われ、食品衛生上の安全性をある程度科学的に議論できる成果が得られてきたといえる。特に水溶性ヒ素化合物に関する知見は豊富で、少なくとも海洋動物に広く分布しているアルセノベタイン、アルセノコリン、トリメチルアルシンオキサイドおよびテトラメチルアルソニウムイオンについては健康危害の心配はないと判断される。海藻の主要なヒ素化合物であるアルセノシュガーについては、急性毒性は問題ないと思われるが、代謝産物のジメチルアルシン酸の発がん性に関してはさらに検討が必要である。一方、脂溶性ヒ素化合物に関しては知見が非常に乏しいので、化学構造・毒性・代謝の解明を目指した研究が進展することを期待したい。
|