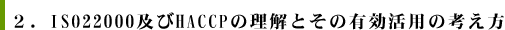 |
|
| 2−1.HACCPとはどのようなものか |
|
| 筆者はHACCPを説明する時に、“それは、今夜、牛肉を安全に食べるようなものである”と話している。牛生肉は、数パーセントの割合でO-157に汚染されているものがあると言われている。牛肉そのものは、本来は、O-157に汚染されてはいないのであるが、と畜場での内臓分離の際にその内臓に傷がつき、肉が汚染されることがあるのである。O-157は、牛肉グラム(g)あたり100個程度の汚染でも食中毒を発症すると言われており、毒性が強く、大変怖い危害要因である。
しかしながら、O-157は熱に弱く、厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル」では75℃1分以上の加熱で死滅すると言われている病原菌である。そこで、今夜は焼肉を食べようということになった。買ってきた牛肉の表示を見ると結着肉などの加工を施された肉であるという表示はなかったので、O-157は肉の表面にしかいないと確信できた。そこで、肉の表面からピンク色が消えるまで焼いて、牛肉を美味しく食べたのである。 |
|
| 上述の台所でのストーリーの中にはHACCPの必要要素がすべて含まれている。HACCPとはHazard Analysis and Critical Control Point systemの略であり、一言でいえば,食品中の危害要因を取り除いて、安全な食品を確保するための仕組である。その危害要因が安全なレベルであることの保証の仕方は検査・分析によって実行するものではなく,食品の調理過程で、あるいは作り込む過程で,予め定めた,安全な食品を作り込む管理手段(危害要因を除く方法)を用いて実行しようとするところに特徴がある。 |
|
| ここでのHACCPシステムでは、検査・分析は、システム運用時に常時活用することはないが、そのシステムの正しさを検証するときに非常に重要な役割をなしている。HACCPは、実際の製品中の危害要因数値を検査・分析することなく、工程の管理値を監視・測定して、製品中の危害要因を保証しているのであり、その関係の正しさは、システム構築時及びシステム構築後に、適切な間隔で、製品中の危害要因数値を検査・分析することでしか確認できないのであり、検査・分析が重要な役割を担うのである。 |
|
| 2−2.HACCPの起源 |
|
HACCPは1960年代に米国のNASA(航空宇宙局)で、宇宙飛行士に安全な食品を提供するために開発されたと伝えられている。しかしながら、実は、Codexやカナダでは、その誕生の背景を次のように述べているのである。
HACCPシステムの起源は,大きくわけて以下の二つの流れがある。一つは,1950年代に,日本での製品品質を一変させたデミング博士の品質管理理論にある。この理論の中心をなしている のは、“品質は工程で作りこむ”というものであり,品質は検査によって保証するものでなく、その品質が作り込まれる過程を管理することによって,品質が保証できるとするものである。この考え方が、HACCPの考え方の根源である安全は工程で作りこむとの考え方のもとをなしている。
もう一つは、HACCP概念そのものを生み出した1960年代のNASA航空宇宙局における安全な宇宙食供給の仕組みの開発にある。この成果は,Pillsbury社,アメリカ陸軍ナティック研究所及びNASA(National Aearo-nautics and Space Administration)の協同研究から生まれた。
NASAは欠陥ゼロの食品を求めていた。すなわち,宇宙飛行士が,食中毒にかかっても,飛行船内では対応の取りようがない。そのため,食品安全性確保は大変重要な課題となる。食品安全の重要項目である病原微生物を考えてみると,食品中の微生物の分布は極めて不均一であって,ましてや,加工処理をした食品中の病原微生物汚染の頻度や菌量は極めて低いものである。したがって,ランダムサンプリングをして微生物の検査をしただけでは,宇宙食における病原微生物の安全保証は到底達成できないという結論になってしまう。
そこで,Pillsbury 社のバウマン博士らは発想の転換をして,原料の成育・飼育の段階から始まって,加工処理を経て最終製品に至る各段階や工程において,どのような微生物が付着し,混入して,それが何処で,どのような経過をたどって増殖し,あるいは死滅するかを調べてみた。すなわち,これが微生物危害要因を明らかにする危害要因分析(HA)である。次に,この分析結果に基づいて,どの段階で,どのような処理・処置をすれば安全な製品を得ることができるかという必須管理点(CCP)と管理手段とを決めて,日常的,計画的に管理・監視をしていこうとしたのである。
筆者は、第3のHACCP誕生のルーツがあると主張している。人類の知恵説である。すなわち、人類がここまで発展してきたのは、実は、経験則によってHACCPの原理を習得してきたことにあると考えている。すなわち、自然に存在する食品はほとんどのものに毒(危害要因)があり、安全な食品はあまりなかったのではないかと考えられるが、人類は、先人が食べて死亡したり、病気にかかったりした食品を覚えており、次世代に引き継いできたのであろう。例えば、茸は、先人が食べて死亡したり、中毒にかかったりしたものをみて、そのような茸は自からは食べることを避けて、子孫にも伝えて、安全な食品を確保してきたのであろうし、フグは内臓に毒があることを知り、その毒のある部分を取り除いて食べ、そのことを次世代に引き継いでいったと考えられる。
すなわち、人類は食生活の中で危害要因分析(HA)を実施して、その危害要因の管理手段と許容限界(CL:Critical Limit)を発見し、管理手段を展開する必須管理点(CCP)を見出して、安全な食品を手に入れて、生き延びてきたのであろう。食品を加熱すことも、食べやすくするということもあったと思われるが、付着する病原菌を殺して安全に食べる手段でもあることを知り子孫に引き継いできた可能性が強い。したがって、現在のHACCPの安全性確保の手段の中には、実は、人類が、美味しく食品を食べるために発見した方法で、結果としては食品安全を確保されるようなものが多くあり、それらの歴史の中で発見してきた管理手段が現在でも活用されているのである。後述のISO22000におけるOPRPはその例である。 |
|
| 2−3.HACCPシステムの展開 |
|
1960年代のNASA航空宇宙局でシステム化されたHACCPは、その後、米国FDAで「低酸性缶詰」の製造工程におけるボツリヌス菌の管理に適用され、大きな成果を上げた。そこで米国ではHACCPの標準化を実施して、広く食品の安全性管理に適用しようと考えてシステム構築の考え方を7原則にまとめた。
このHACCPシステムの素晴らしさを認めた食品規格委員会では1993年に12の手順、7原則からなるHACCPのガイドラインを構築した。そのガイドラインは、1997年には、「食品衛生の一般原則」に組み込まれ、各国に示されて、世界各国で活用されるようになった。なお、この「食品衛生の一般原則」の最新版は2003年版である。
わが国では、1989年頃からHACCPの研究が始まり、1992年には厚生省(現厚生労働省)が「、食鳥処理場におけるHACCP方式による衛生指針」を提示し、HACCP活用の口火を切った。その後、1995年には食品衛生法の中に「総合衛生管理製造過程」の要求事項を組み込んで、HACCPの認証制度を開始した。この認証数は、2010年6月現在で558施設、819件の製品にのぼる。 |
|
| 2−4.CodexのHACCPガイドラインの特徴とその基本的な考え方 |
|
HACCPには素晴らしい考え方や手法がある。食品安全というと、とかくあれも心配だ、これも心配だとなりがちであるが、「危害要因分析」を活用して、その要因の危害の大きさを分析し、評価して、必要とされる程度の管理手段を見出すのである。
その他の考え方や手法をまとめると以下のようになる。
(1)重点指向である
危害要因をその危害の大きさで評価し(リスクアセスメント)、適切な管理手段を見出して、管理箇所も
必要最小限に絞り、重点的に管理する。
(2)ゼロデフェクトを求めない
危害要因はゼロであることを求めない。消費者に危害を与えない範囲であれば、その危害要因物質は、
仮に含まれていても管理の対象とはしない。
(3)From Farm to Tableの思想がある
危害要因は、農場から台所までの、最も適切な場所で管理をすれば良いとされている。
例えば、O-157は、台所かレストランで管理するのが最も経済的である。一方、農薬や動物用医薬品の
管理は農場で行うのが最も効果的である。
(4)食品安全は工程で保証する
危害要因は、最終製品の検査で保証するのではなく、食品製造加工の工程で、その手法の管理で
保証をする。すなわち、“安全は工程で作り込む”のである。
(5)HACCPはシステムの構築であり、施設、設備の新設、増強を求めてはいない
HACCPシステムにおける危害要因の管理は、危害要因分析で最適な管理手段を明確にして行うので
あって、どうしても施設、設備の導入がないと管理できない場合を除いて、施設、設備の導入の
必要性はない。施設、設備の導入が必要な場合は、経済的合理性に基づいてその製品を作るために
施設、設備の導入をするのか、製造を中止するのか選択が求められるのである。 |
|
| 2−5.マネジメントシステムであるISO22000とISO9001の差異 |
|
ISO22000とISO9001は共にマネジメントシステムである。マネジメントシステム規格とは、会社全体の経営の中で該当する規格の内容を最適な状態で運営する仕組みのことである。したがって、ISO22000規格は、会社全体の運営の中で、安全な食品の作り込みを最適な状態で実施していくための仕組みを示しているものである。一方、ISO9001もマネジメントシステムである。ISO22000の序文によると、ISO22000はISO9001と両立性を高めるように構成されていると言っている。
実は、ISO9001とISO22000とでは、そのマネジメントシステムがまったく異なっているのである。ISO9001は会社全体のマネジメントを運用するための仕組であるが、ISO22000は、食品の危害要因を会社全体のマネジメントの中で最適に管理するためのものであり、リスクを管理するためのものである。したがって、ISO22000はISO14001やISO27001と同じ性格を持っている。
よく、ISO22000はISO9001と両立性を高めるように構成されているという表現から、ISO22000を実施すればISO9001の要求事項もカバーできるように考える人もいるが、それはまったくの誤解である。ISO9001の7章の要求事項である「顧客関連のプロセス」、「設計・開発」、「購買」及び「製造及びサービスの提供」の要求事項はISO22000にはない。すなわち、ISO22000には、食品安全の管理の仕組はあっても、良品提供の仕組はないということである。その点をよく考慮して、ISO22000の導入を図っていく必要がある。 |
|
| 2−6.他のHACCP系システムに見られないISO22000の特徴 |
|
| ISO22000は他のHACCP系システムにない特徴がある。それは、その認証対象が、いわゆる食品のみではなく、食品を取り巻くあらゆる産業におかれているということである。ISO/TS22003(食品安全マネジメントシステムの審査及び認証を行い機関に対する要求事項)によると、食品安全マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関は自らの認証範囲を下記のフードチェーンカテゴリから明確に定めることが求められており、そのことは、すなわち、下記のフードチェーンカテゴリの属する業態はISO22000の認証対象であると言うことを示しているのである。 |
|
| 表‐1フードカテゴリーコード |
|
| カテゴリコード |
カテゴリ |
分野の例 |
| A |
畜産・水産業(動物) |
動物;魚;卵生産、乳生産;養峰;漁業;狩猟;捕獲 |
| B |
農業(植物) |
果実;野菜;穀物;香辛料;園芸作物 |
| C |
加工1(腐敗しやすい動物性製品)農業生産後のすべ手の活動。例えばと殺を含む |
獣肉;家禽;卵;酪農及び園芸作物 |
| D |
加工2(腐敗しやすい植物性製品) |
青果及び生ジュース;保存加工された果実;生野菜;保存加工された野菜 |
| E |
加工3(常温での長期保存品) |
缶詰;ビスケット;スナック;油;飲料水;飲料;バスタ;穀粉;砂糖;塩 |
| F |
飼料生産 |
動物飼料;水産飼料 |
| G |
ケータリング |
ホテル;レストラン |
| H |
流通 |
直売店;小売店;卸業者 |
| I |
サービス |
給水;洗浄;排水;廃棄物処理;製品、プロセス及び装置の開発;獣医サービス |
| J |
輸送及び保管 |
輸送及び保管 |
| K |
装置の製造 |
工程用装置;自動販売機 |
| L |
(生化学)化学製品製造 |
添加物;ビタミン;農薬;薬品;肥料;洗浄剤;培養物 |
| M |
包装材料製造 |
包装材料 |
|
|
| 2−7.危害要因分析 |
|
ISO22000での「7.4」の要求事項を見ると「危害要因分析」では下記の要素が必要なことがわかる。
(1)製品の種類、工程の種類及び実際の加工施設に関連して発生することが当然予測される全ての食品安全ハザードを明確にして記録すること(「7.4.2」)
(2)最終製品での食品安全ハザードの許容水準を可能な限り明確にすること。その決定の正当性及びその結果を記録すること(「7.4.2.3」)
(3)明確にした食品安全ハザードのうち、除去又は規定の許容水準まで低減することが安全な食品を生産する際に不可欠なものを明確にするハザード評価を実施すること。ハザード評価は、健康への悪影響の大きさ及び起こりやすさにしたがって評価し、評価の方法を記述し、その結果は記録すること(「7.4.3」)
(4)健康への悪影響の大きいもの及び起こりやすいハザードの管理手段又は管理手段の組み合わせを選択し、その管理手段はOPRP又はHACCPプランのどちらかの手順を活用するかに分類すること。選択及び分類は論理的手法で実施し、その方法及び判断基準は、文書に記述し、判定結果を記録すること(「7.4.4」)
上記の要求事項を満足する帳票を考慮すると表−2のようなものになる。 |
|
| 表−2 危害要因分析ワークシート例 |
|
| 2−8.CodexのHACCPとISO22000の管理手段の差異 |
|
HACCPの管理手段は前提条件プログラムPRP(一般衛生規範:p.p.とも呼ばれている)とCCPの2種類の手順に分類されていたが、ISO22000はその管理手段を3種類の手順に分類している。前提条件プログラムPRP、OPRP(CCPの設定が必要ない管理手段をISO22000ではこう呼んでいる)及びHACCPプラン(CCPが設定される管理手段をISO22000ではこう呼んでいる)である。
ISO22000の適用の手引きとして制定されているISO/TS22004のおけるPRP、OPRP及びHACCPプランの記述内容は下記のとおりである。
a)前提条件計画、PRPsは特に明確にされた危害因子の管理の目的には選択されることはなく、衛生的な生産を維持する目的や周辺環境の処理や取り扱いの目的で使用される。
b)OPRPは危害因子分析で明確にされた危害因子を受容可能なレベルまで管理するために必要とされ、HACCP計画では管理されることがないような管理手段を管理するものである。
c)HACCP計画は、重要管理点(CCPs)で適用される管理手段で、危害因子分析で明確にされた危害因子を受容可能なレベルまで管理するために必要とされた管理手段である。
ISO22000は、同じCodexのHACCPを活用しながら3種類の管理手段に分けた理由をISO/TS22004の中に示している。その内容は大きく以下の2点に分けられている。
(1)食品安全マネジメントシステムの構築、実施及び管理のための必然的な順序にもとづくと、この3グループになる。
この必然的な順序とは、ハザードの管理を筋道に沿って考えてみると、まず前提条件プログラムで管理できるものは、この前提条件プログラムで管理し、次に、該当する危害要因は確実に除去できるが、厳しい許容限界を設定しなくても管理できる管理手段はOPRPの手順を活用し、最後に、厳しい許容限界を設定しなければならない管理手段はHACCPプランの手順を活用していくのがよいということである。
(2)それぞれのグループごとの管理手段の妥当性確認、監視、さらには、製造された製品の取り扱いをも含めた不適合の管理の正しさを容易に判段するにはこの3グループに分けるとよい。
すなわち、PRPで管理する危害要因は少々管理手段に不適合があっても食品安全に重大な影響を持つようなものではないのであり、例えば、手洗いを1回忘れても、即座に製品安全に影響するというようなものではなく、その管理手段は妥当性確認をしなければいけないというようなものではない。
一方、OPRP及びHACCPプランに属する管理手段はその管理手段を失敗すれば、食品安全の確保ができなくなる可能性が高く、確実な実行が求められるものである。しかしながら、OPRPに属する管理手段は食品安全管理を主目的にしているものではなく、製品そのものを製造する過程で食品安全ハザードを管理するものであるから、管理手段の失敗が、人の安全に直接は結びつかない場合が多い。したがって、その管理手段の妥当性確認は、HACCPプランと比較したら、大幅にゆとりのある条件下にあり、その確認は容易に達成できる。
また、OPRPでの不適合は、食品安全の不適合の観点から取り扱う必要性はない場合が多い。そこで、「7.10.1」ではOPRPが適合していない条件下で製造された製品は、まず不適合の原因の評価が求められており、基本的には、製品そのものは食用には供すことはないとの考え方での取り扱いを求めている。しかしながら、もし食用に供すような場合は、食品安全という観点で評価することをと求めており、その上で、もし必要なら、「7.10.3」にしたがって食品安全の観点からの判断がが求められている。
これに比べて、CCPが許容限界を超えた条件下で製造された製品は、安全でない可能性が高いので「7.10.3」にしたがって取り扱うことと求められている。このように、OPRPとHACCPプランでは不適合の場合にも差異があり、OPRPで管理できるのであれば管理が容易である。
このOPRPの考え方には、人類の知恵である先祖伝来の安全確保の手法が含まれているのである。
Codex HACCPでも、実は、GMP(良品作りの規範)及びGH P(衛生管理の規範)と言う考え方を取り入れており、GMPをOPRPと同じ位置づけにしているが、その考え方は教育訓練資料にはあるが、Codex HACCPそのものには明記されてはいないのである。
|
|
| 2−9.マネジメントシステムとしてのISO22000の特徴である経営者の関与 |
|
日本における国家のHACCPシステムである「総合衛生管理製造過程」は国家の規格であり、さすがに素晴らしいものである。しかしながら、経営者の関与が十分とはいえないものである。これは、「総合衛生管理製造過程」が悪いのではなく、CodexのHACCPガイドラインそのものが、経営者の関与の重要性を強調しているものの、その具体論がないのである。したがって、CodexのHACCPガイドラインを受けた「総合衛生管理製造過程」には経営者の責任に関する具体論がない。
そのために、技術的な要求事項に偏ってしまっており、担当者は一生懸命システムを運用しているのであるが、大局的な立場でシステムが管理されてなく、経営者は自らの意志として「総合衛生管理製造過程」を実施しているとの意識が弱かったので、大きな食中毒を発生させた。その後、ISO9001の関係者も「総合衛生管理製造過程」の検討に加えたが、システムそのものは大きく変更されたわけではなく、経営者の関与に関しては大きく改善されてはいない。
一方、ISO22000は当初からマネジメントシステムとして構築されたのであり、その5章に「経営者の責任」というう要求事項があり、具体論が定められている。したがって、この要求事項に適合しなければ認証が得られない。また、認証取得後も、定期的に「経営者の責任」が審査され、適合しなければ改善が求められ、その状況によっては認証が取り消されることにもなる。これは、ISO22000、すなわちマネジメントシステムの大きな特徴である。 |
|