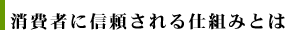 |
|
| まず、食品の安全・安心に関するスライドを見ていただきたい。このスライドは、平成14年から始めた食肉衛生検査所と食肉センターの見学者に対して、消費者から信頼されるためにこのように検査所は考えていると説明したものである。安全は科学的根拠(基準)による客観的評価、安心は個々の消費者の信頼に基づく主観的評価であり、これは全てのプロセスで評価されることを前提として、次の三つを上げた。 |
|
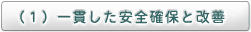 |
|
| 事業者の自主管理と行政の監視指導によって、生産から消費まで全ての工程で、関係機関が協働して高品質で安全な食品が提供される仕組みとそれを絶えず改善する取組が必要である。 |
|
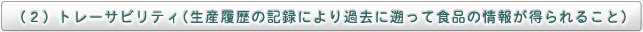 |
|
| トレーサビリティは、本来関係業者が高品質で安全な食品を提供するための生産や改善活動に関する記録であるが、消費者にとっては、生産履歴を遡って情報を知ることできると同時に業界の誠実・正直な姿勢を確認でき、信頼できる相手かどうかを判断する重要な仕組みの一つである。トレーサビリティは「安心の社会システム」といわれるが、逆にそれは不正を許さない(嘘がばれる)仕組みでもある。 |
|
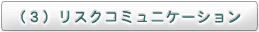 |
|
| 消費者のために、関係者が協働してさらに安全な食品を確保するために活動するネットワークの仕組みが必要である。 |
|
そして(1)~(3)が、情報公開できる、さらに積極的に公表することで、関係者は自らを厳しく律することができるし、消費者にとってもシステムが見えることにより疑いを払拭できると説明した。松阪牛に当てはめればどうなるかが次のスライドである。
(1)の安全に関しては、法律に基づく厳正公正な検査、と畜関係者が協働して衛生的なと畜解体に取り組むことにより高い安全性を確保できる。検査所はISO9001(品質保証システム)の認証機関として、定期的な内部監査と外部審査によって検証と改善を行っている(2)のトレーサビリティは松阪牛個体識別管理システムが稼動している。(3)は検査所のリーダーシップで関係者会議を定期的に開催した。また、松阪食肉衛生検査所だけでなく食肉センターの見学も積極的に受け入れ、消費者に詳しく説明した。松阪牛は、地元では小学校の給食でも出されているが、と畜解体工程も見学できることで、小学生にとって松阪牛の生産から食肉処理、消費まで一貫した総合学習ができるようになったのである。 |
| スライド松阪牛安全安心 |
|