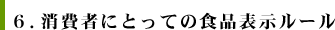 |
|
�@��L�̂悤�ɔN�X���G�����Ă���H�i�\�����x�ł��邪�A����҂͓���̐H�����ɂ����ĕ\���ɑ��ǂ̒��x�S�����芈�p���Ă���ł��낤���B�܂��A���̑O��ƂȂ郋�[���ɂ��Ă̗���x�͂ǂ̒��x���낤���B
�@�H�i�̕\�����[���́A����̐H�����ɂ����Ċ��p���邱�Ƃ���A�o���邾����N�w�ɂ����ĕ��y�E�[�����邱�Ƃ��]�܂������A���݁A���Y����ɂ��ẮA���w�Z�̍��w�N�y�ђ��w�Z�̉ƒ�Ȃɂ����Ċw�K����@�����B
�@���̂��Ƃ܂��A���w�Z�U�N���ƒ��w�Z�Q�N����ΏۂɃA���P�[�g�������s�����B���̒��ŁA�u�H�i�����ɕ\�������邩�H�v�ɂ��Ă̖₢�ɑ��ẮA���w�N�Ƃ���U�����u�������K�v�ȕ���������v�Ɠ�����(�}�|5)�B
�@�܂��A�ł����鍀�ڂƂ��ẮA�u���i�v����X���A�u�����v����W���A�u���Y�n�v����T���ł������B���ō����u�h�{�v�\���ɂ��ẮA�_�C�G�b�g���C�ɂ���ϓ_�ŁA���ɒ��w�����q�̖������Ă���(�}�|6)�B
�@�܂��A����������N����ɑ��āA�\�����[�������ʓI�ɗ�����������@�Ƃ��ăN�C�Y���������݂��B�u�����\���v�A�u�L�@�_�Y���v�A�u��`�q�g�����v�ȂNJe����̕\�����[���ɂ��āA�N�C�Y���o���A���̐��𗦂ɂ�藝��x��c������ƂƂ��ɁA�ނ炽���ɋ����������ė������Ă��炤���Ƃ��˂炢�ł���B���̌��ʁA���ς̐��𗦂͂R�R���ŁA���ɐH�i�}�[�N�Ɋւ��闝���͒Ⴉ����(�}�|7)�B
�@���������N�C�Y�����ɂ��w�K���@�ɑ��āA���w��(��R���̂Q)�A���w��(��S���̂R)�Ƃ��ɊS�����Ƃ������ʂ�����ꂽ�B
�@����A�����(65�Έȏ�)�Ƒ�w���ɂ��Ă̔�r�A���P�[�g���ʂɂ��A���ɏ������\���ɊS�������A���s�����傫�����Ƃ����炩�ƂȂ���(�}�|�W,�X)�B�܂��A����҂͒j���Ƃ��ɁA�u�ׂ����Č��ɂ����E�傫�����ė~�����v�Ƃ����s���̈ӌ������������B���݂i�`�r�@�ł́A�u8�{�C���g�ȏ�v�̑傫�����K�肵�Ă��邪�A�\���\�ʐς��u150���u�ȉ��̏ꍇ��5.5�{�C���g�ȏ�v�ł��悢���ƂɂȂ��Ă���B
�@�����ŁA���ۂɔ̔�����Ă��铤���A�[���A�ݖ��ȂǍ���҂�����悭�w������H�i�T��މ��ׂU�O���̂ɂ��āA�\���̑傫���������Ƃ���A5.5�`10.5�|�C���g�͈̔͂ŕ\������Ă����B
�@����A����҂�ΏۂɁu���m�ɔF���ł���傫���v�������Ƃ���A�u14�|�C���g�ȏ�v��]��ł���A���炩�Ɏ��ԂƂ̍���������(�}�|10)�B
�@�\�����[�������i�����A���s���������p�����钆�ŁA�H�i�̋����T�C�h�Ƃ��ẮA�@�ߏ���ɌX��������Ȃ��ł͂��邪�A�\���͖@�߂̂��߂ł͂Ȃ��A�{������҂̂��߂Ƃ������_�ɗ������Ή����]�܂��B |
|
| (�}�|�T)�@�����w���̐H�i�\���ɑ���S�x�m�Q�U�U���Ώہn |
|
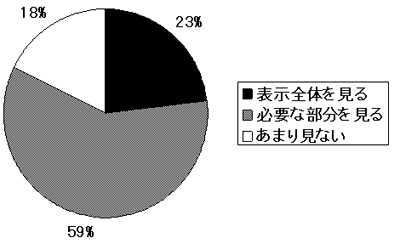 |
|
| (�}�|�U)�@�ł��悭����\���Ƃ��ẮA�u���i�v����9���A�u�����\���v����8���u���Y�n�v�͖�5�����߂Ă��� |
|
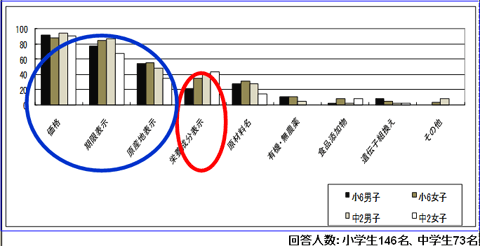 |
|
�i�}�|�V�j�N�C�Y�ɂ�闝��x�̏�
10��̕��ϐ��𗦁F33��
���ɐ��𗦂̒Ⴂ����F�H�i�}�[�N |
|
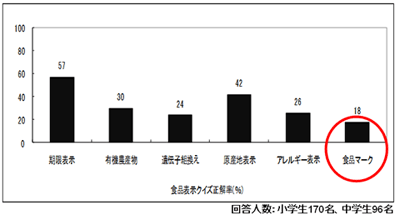 |
|
| (�}�[�W)������͕\���ɊS������ |
|
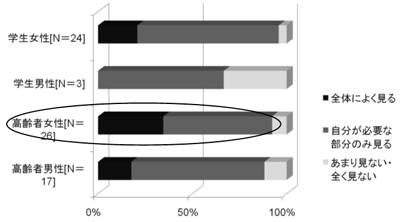 |
|
| (�}�[�X)����҂͕\���ɑ���s����@ |
|
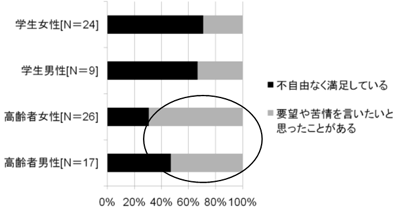 |
|
|
|
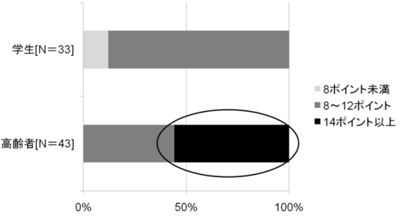 |
|