| ◆ HOME >においの豆知識 官能的な側面から見た「におい」 |
 |
|
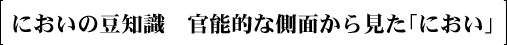 |
|
これまで、「においの豆知識」として幾つかお話をさせて頂きましたが、そもそも「におい」とは何なのでしょうか。「におい」は我々の生活と、どのような形で関係しているのでしょうか。 |
|
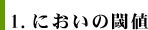 |
|
私達は、毎日の生活の中で、意識する/しないは別として、まずにおいを嗅いでから食べ物を口に入れます。これは、においと味が密接に関連していることもありますが、その食べ物は食べても良いものか否かのチェックをしている意味もあります。これまで感じたことのないようなにおいを持つ食べ物と出合った時、それが魅力的な「美味しそうなにおい」であれば進んで口へ運び食べる幸せを噛み締めますが、「何かおかしい」と思えるようなにおいであった場合、それを口に入れることを躊躇ってしまうのではないでしょうか。腐敗した食べ物を食べると、最悪の場合生命の危機に瀕します。においで食べるか否かのある程度の判断をするという技は、危険回避の一手段として我々の先祖が進化の過程で身に付けてきた生き残るための術とも言えるのではないでしょうか。
この危険を回避する能力と直接関係するか否かは不明ですが、我々ヒトの嗅覚は全般的に心地良いにおいと、腐敗臭など不快なにおいの閾値(においを感じることのできる最小量)を比較すると、不快なにおいの方が心地よいにおいの閾値より小さい化合物が多くあります(表-1)。つまり、不快なにおいの方を、より感度良く捉えている傾向にあるのです。 |
|
|
表. 不快なにおいと良いにおいの閾値の比較1)
|
|
| I.腐敗に伴って生じるにおい物質とその閾値 |
|
| 化合物 |
におい |
閾値(ppm) |
| 1.硫黄化合物 |
| メチルメルカプタン |
腐ったタマネギ |
0.00007 |
| エチルメルカプタン |
腐ったキャベツ |
0.0000087 |
| n-プロピルメルカプタン |
不快 |
0.000013 |
| 硫化水素 |
エーテル様・不快 |
0.00041 |
| 2.窒素化合物 |
| メチルアミン |
生魚臭 |
0.035 |
| ジメチルアミン |
腐魚臭 |
0.033 |
| トリメチルアミン |
刺激ある魚臭 |
0.000032 |
| アンモニア |
刺激臭 |
1.5 |
| スカトール |
糞便臭 |
0.0000056 |
| 3.脂肪酸 |
| 酢酸 |
刺激臭 |
0.006 |
| プロピオン酸 |
不快臭 |
0.0057 |
| 酪酸 |
汗臭 |
0.00019 |
| イソ吉草酸 |
ワキガ臭 |
0.000078 |
| 4.ケトン、アルデヒド |
アセトアルデヒド
|
刺激臭 |
0.0015 |
| プロピオンアルデヒド |
刺激臭 |
0.001 |
| アクロレイン |
刺激臭 |
0.0036 |
|
|
|
| II.香料などに用いられる、良いにおいの物質の閾値 |
|
| 化合物 |
におい |
閾値(ppm) |
エチルアルコール
|
酒類 |
0.52 |
| イソプロピルアルコール |
フーゼル臭 |
26 |
| アセトン |
溶剤臭 |
42 |
| 酢酸エチル |
フルーティー |
2.7 |
| イソ吉草酸-n-プロピル |
アップル臭 |
0.000066 |
| α-ピネン |
森の香り |
0.018 |
| リモネン |
柑橘香 |
0.038 |
| 酢酸ブチル |
フルーティー |
0.016 |
|
|
|
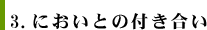 |
|
においは心理・生理に少なからず影響を与えることが知られています。アロマテラピーなどで行われる精油による覚醒・鎮静作用や疲労軽減、作業効率向上、ストレス緩和、免疫向上など、においの齎す効能の利用は古の時代から取り入れられており、最近ではその科学的検証や作用機序の解明が次々と行われています。
においは、我々に良い方向にも影響を与えますが、それが悪臭となると逆に負の影響を与えます。においは、嗅覚により感知されたにおいを大脳で識別することにより、良いにおいか否かの判断がなされます。そのため、あるにおいが「悪いにおいだ」と判断されれば、その人にとっての「悪臭」となるため、悪臭か否かの判断は個人の経験や嗜好などにも左右される存在ではあります。上述したように、悪臭は低濃度でも感知できるものが多くあり、またこれらの化合物には危険ものもあります。また、生命には影響を与えなくても不快感や嫌悪感を与えることもあります。
移り香や腐敗による異臭など、所謂臭気クレームは、食品製造から販売、管理といった各段階のうちの何れかの段階で異常があった事を示すシグナルです。このシグナルの意味を正しく読解し、異常工程の洗い出しと修正、更には再発防止手段を講じることが大切であるといえます。 |
|
 |
|
| 永田好男,竹内教文:(財)日本環境衛生センター所報(1990), 17. |
|
|