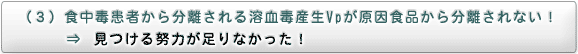 |
|
| 1998年・1999年に三重県で発生したVp食中毒2例において、患者便以外からも初めて溶血毒産生Vpを検出した。保健所で食中毒の調査を担当した者は、かつてVp浄化実験を行った食監、執念で溶血毒産生Vpを分離したのは、三重県保健環境研究所の研究者であった。これらのVp研究会参加メンバーの協働作業がなければおそらく検出できなかったことであろう。詳細はスライドに示すが、「見つけよう、いるはずです、原因食品にTDH(+)Vp!」なのである。発症率の高い食中毒ほど溶血毒産生Vpの検出確率が高くなることも経験したし、溶血毒産生Vpは見え隠れが甚だしいものであることも分かった。 |
|
| ※貝類における汚染・浄化試験や汚染貝類の増殖試験において溶血毒産生Vp(O4:K8)株を用いたが、毒素非産生のVpと異なる性状は見られなかった。また、溶血毒産生Vpの消長とデロビブリオ(Bdellovibrio)の関係についてこれまで何度も関係者から話を聞いたことがある。しかし記述するものを持ち合わせていないのが残念である。 |
|
食中毒の原因調査において、食品残品等からVpが分離されても、数十個のコロニーを拾っていたのでは見つからず、数百から数千個拾えば溶血毒産生Vpは見つけることができるはずだ、これまでは努力が足りなかった、との結論に達したのである。
そして、ビーズ法やPCR法の導入などの試験法が工夫され、自然界からも溶血毒産生Vpを分離することができるようになった。漁港の汚泥や海水からまず富山県衛生研究所が分離に成功し、秋田県、青森県の衛生研究所では、病院の下痢症患者から分離されたVpと河川河口部など自然界から分離された溶血毒産生Vpとの関連についてまで調査研究が進められた。やはりVp食中毒発生件数の多い、また沿岸海水の塩分濃度が低い日本海側の衛生研究所で多くの成果が得られたのである。これらの成果は、血清型O3:K6による食中毒発生と関連して、全国的に溶血毒産生Vpの分離も含めたVpの調査研究の進展をもたらし、また2001年の食品衛生法に基づく成分規格の制定に繋がっていった。
さらに、新潟県保健環境科学研究所においては、上記で述べた新潟・福島豪雨後に多発したVp食中毒の関連として2006年、2007年に、汽水域や沿岸海域の表層水・底泥や岩カキを調査した。詳細は報告書をお読みいただきたいが、「降水量増加後に、汽水域におけるV.pの菌数減少や沿岸海域での菌数増加が確認された。汽水域の底泥V.pが増殖する時期に降水量が増加すると、河川流量の増大にともない同菌が沿岸海域へ大量に流出し、海域汚染の原因になると考えられた。」と研究成果を報告している。
2004年の新潟県・石川県で発生したVp食中毒を一覧にまとめた。新潟県の事例は保健環境科学研究所が大雨との関連を推定している。 |
|
溶血毒産生Vp検出食中毒事例(スライド)
Vp食中毒と豪雨(スライド) |
|
| ※謎が解け、食中毒予防の情報発信に活かされる! |
|
長い間謎とされてきたVp食中毒、三重県において伊勢湾を中心とした調査研究で、汽水域調査、溶血毒産生Vpの分離によって、小生たちは謎は解けたと感じてきた。Vp食中毒について、「本当の犯人である溶血毒産生Vpは河川河口部などの汽水域に生息し、大雨によって汽水域から沿岸海水に流出して増殖・魚介類を汚染させ、汚染された魚介類が調理場等に持ち込まれ食中毒を引き起こした。特にリスクの高い魚介類は、まさに汽水域に生息しVpの生物学的濃縮機構を有する二枚貝、そしてリスクが高くなる時期は大雨の後!」と結論付けた。そして、三重県では2003年度から伊勢湾沿岸の二枚貝をモニタリングし、保健環境研究所で溶血毒産生Vp遺伝子の動向を調査しながら、50mmを超える大雨の際(塩分濃度躍層形成、長期の汽水化)にはVp食中毒警報を発してきた。(H15Vp食中毒予防情報発信事業実施要領)
これらのことが、まさに上記新潟県の調査研究によって明らかとなったし、現在の新潟県における腸炎ビブリオ情報は、汽水域の海水及び底泥(3地点)、水揚げされたマアジ(2地点)をモニタリングし、その結果を腸炎ビブリオ情報として食中毒予防のために発信している。素晴らしい取組に敬意を表したい。 |
|
|
新潟県HP:にいがた食の安全インフォメーション→→→腸炎ビブリオ情報 |
|