| ◆ HOME >「食べて危ないマリントキシン」の概要と今後の課題 |
 |
|
|
|
|
| 海産動物の中には、海の中での生存競争に打ち勝つ(=捕食動物から身を守る、あるいは餌動物を捕食する)ための強力な化学的武器として毒成分を獲得してきたものが数多く知られている。本来の生物学的役割は別として、海洋動物の毒成分(マリントキシン)は研究用試薬や農薬などとしての有効利用の面で、反対に食べて危ないとか刺されて危ないといった健康被害の面で、人間社会と関わってきたものも多い。四方を海に囲まれたわが国は、海産動物を重要なタンパク質源として古くから利用してきたので、「食べて危ないマリントキシン」との関わりがとくに深い。最近10年間(2000〜2009年)の食中毒の発生状況を病因物質別に表1に示すが、マリントキシン(動物性自然毒はすべてマリントキシンである)による食中毒の割合は事件数で2.7%、患者数では0.3%とごくわずかであるにもかかわらず、死者数では40%近くにも達している。本稿では、食品衛生上きわめて重要な位置を占めている「食べて危ないマリントキシン」に焦点をあて、今後の検討課題も含めてその概要を紹介する。 |
|
| なお、2009年6月から2010年3月にかけて、月刊「食品衛生研究」(日本食品衛生協会)に「マリントキシンをめぐる動向」が連載(10回)された。それぞれのマリントキシンの専門家が詳しく執筆しているので、本稿で不足の部分は補っていただきたい。また、2010年4月には、筆者らが行った厚生労働科学研究の成果として厚生労働省のホームページに「自然毒のリスクプロファイル」(http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/poison/index.html)が掲載された。今のところ概要版のみであるが、近いうちに詳細版も掲載する予定である。食品衛生上問題となる自然毒全般を取り上げているので、ぜひアクセスしていただきたい。 |
|
| 表1. 病因物質別食中毒発生状況(2000〜2009年の累計) |
|
| 病因物質 |
事件数 |
患者数 |
死者数 |
|
細菌
|
10,776 |
151,628 |
21 |
| ウイルス |
3,065 |
124,444 |
0 |
| 化学物質 |
123 |
2,497 |
0 |
| 植物性自然毒 |
750 |
2,907 |
17 |
| 動物性自然毒 |
440 |
813 |
23 |
| その他 |
71 |
205 |
0 |
| 不明 |
790 |
15,782 |
0 |
| 計 |
16,015 |
298,277 |
61 |
|
|
|
|
|
| 食べて危ないマリントキシンの横綱は間違いなくフグ毒である。最近10年でも、マリントキシンによる食中毒のうちフグ中毒は事件数の約80%、患者数の約60%を占め、死者もハコフグ類による中毒での1人を除くとすべてフグ中毒が原因である(表2)。“フグは食いたし命は惜しし”と言いつつ古くからフグを食用にしてきたのは日本人だけであり、フグ中毒の件数および中毒死者の多いことが日本の食中毒の大きな特徴となっている。 |
|
| 表2. マリントキシンによる食中毒発生状況(2000〜2009年の累計) |
|
| 原因魚貝類 |
原因毒 |
事件数 |
患者数 |
死者数 |
|
フグ(フグ科)
|
テトロドトキシン |
334 |
485 |
22 |
| エゾバイ科巻貝 |
テトラミン |
43 |
96 |
0 |
| シガテラ毒魚 |
シガテラ毒 |
40 |
161 |
0 |
| ハコフグ類 |
パリトキシン様毒 |
6 |
10 |
1 |
| アオブダイ |
パリトキシン様毒 |
5 |
12 |
0 |
| キンシバイ |
テトロドトキシン |
2 |
2 |
0 |
| イシナギ |
ビタミンA |
1 |
14 |
0 |
| ハタ科魚類 |
パリトキシン様毒 |
1 |
11 |
0 |
| 魚卵 |
ジノグネリン(?) |
1 |
6 |
0 |
| ナガズカ |
ジノグネリン |
1 |
4 |
0 |
| ムラサキイガイ |
麻痺性貝毒 |
1 |
3 |
0 |
| ウミガメ |
不明 |
1 |
1 |
0 |
| 不明 |
不明 |
4 |
8 |
0 |
| 計 |
|
440 |
813 |
23 |
|
|
| フグ毒の本体はテトロドトキシン(TTX、図1)で、ナトリウムチャンネルに作用する強力な神経毒である。すなわち、神経や骨格筋の細胞膜のナトリウムチャンネルに特異的に結合して細胞外から細胞内へのナトリウムイオンの流入を阻止し、結果として細胞膜上の興奮伝達を停止させる。そのためフグ中毒では、麻痺、しびれ、けいれんといった症状が見られ、最悪の場合は呼吸麻痺により死亡する。 |
|
| TTXはフグの専売特許ではなく、両生類のカリフォルニアイモリ、Atelopus 属のカエル、魚類のツムギハゼ、棘皮動物のモミジガイ類、節足動物のオウギガニ類、軟体動物のヒョウモンダコ、巻貝類(ボウシュウボラ、キンシバイなど)、扁形動物のツノヒラムシ類、紐形動物のヒモムシ類、紅藻ヒメモサズキJania sp.など多様な生物に存在が確認されている。このうち、巻貝類ではTTX中毒の例もある(「4.2. 腐肉食性巻貝のテトロドトキシン」参照)。さらにフグの腸内細菌や海洋細菌(Vibrio 属、Psuedomonas 属など)の中にはTTXを産生するものが見いだされており、TTXは細菌から始まる食物連鎖を通してTTX保有動物に蓄積されると考えられている。 |
|
| 図1. テトロドトキシン(TTX)の構造 |
|
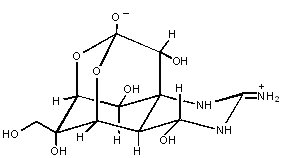 |
|
| フグ毒(およびフグ中毒)は解明し尽くされたかのようであるが、フグはどのようにしてTTXを取り込み蓄積するのか、フグはいったい何のために高濃度にTTXをもっているのか、フグは高濃度にTTXをもっていてなぜ平気なのかなど、古くからの素朴な疑問は依然として残されている。また最近では、フグ毒=TTXという長年の常識すらくつがえりつつある。例えば、フロリダの汽水産フグ(Sphoeroides 属)やフィリピンの海産フグ(Arothron 属)では麻痺性貝毒(サキシトキシン類)が、東南アジアの淡水産フグでは麻痺性貝毒やパリトキシンが主成分である。毒成分が何であるかは中毒対策の根幹に関わる問題であるので、日本沿岸に生息するフグ類の毒成分組成を詳細に明らかにすることは緊急の課題といえる。 |
|
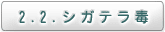 |
|
| 熱帯〜亜熱帯海域、特にサンゴ礁海域に生息する魚類の摂食による致命率の低い食中毒をシガテラと総称している。中毒症状は複雑で、神経系障害、消化器系障害、循環器系障害が絡み合ってみられるが、中でも水に触れるとドライアイスに触れたように冷たく感じる温度感覚異状(ドライアイスセンセーションと呼ばれている)が特徴的である。自然毒による急性食中毒としては世界最大規模で、患者数は毎年2万人以上と推定されている。シガテラ毒魚は数百種に及ぶといわれているが、とくに問題となる魚種はウツボ科のドクウツボ、カマス科のドクカマス(オニカマス)、スズキ科のマダラハタ、バラハタ、フエダイ科のイッテンフエダイ、バラフエダイ、ブダイ科のナンヨウブダイ、ニザダイ科のサザナミハギなどの約20種である。同じ魚種でも個体、漁獲場所、漁獲時期により無毒から強毒まで著しい差があり、中毒発生の予知を困難にしている。 |
|
| シガテラ毒の本体は多くのシガテラ毒魚に含まれる脂溶性のシガトキシン類で、主成分はシガトキシン1B(図2)である。そのほかにサザナミハギからは、水溶性のマイトトキシンが得られている。シガテラ毒は石灰藻などの海藻に付着している有毒渦鞭毛藻Gambierdiscus toxicus が産生し、食物連鎖を通して魚類に蓄積される。 |
|
| 図2. シガトキシン1Bの構造 |
|
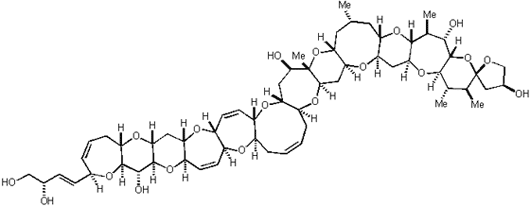 |
|
| わが国におけるシガテラは年数件程度で(表2)、そのほとんどは南西諸島(とくに沖縄県)で発生してきた。しかし、2007年に大阪府で、中毒海域とはいえない和歌山県沖で漁獲されたイシガキダイを原因とするシガテラが起こっている。毒産生者であるG. toxicus が地球温暖化の影響でしだいに分布海域を北に拡大し、南西諸島以外の国内の沿岸に生息している魚においても毒化が進行しているのではと懸念されている。G. toxicus のモニタリング体制を早急に整備するとともに、シガテラ毒の簡易分析法の確立が求められる。 |
|
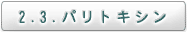 |
|
| わが国では1950年代からアオブダイによる死者を伴った中毒事件が20件以上発生している。主な中毒症状は横紋筋の融解による激しい筋肉痛(横紋筋融解症)で、しばしばミオグロビン尿症(筋肉色素であるミオグロビンが尿中に現れ、尿が黒褐色になる症状)を伴う。原因毒はパリトキシン(PTX、図3)に類似した毒(PTX様毒)と考えられている。最近では、アオブダイだけでなくハタ科魚類やハコフグ類によるPTX様毒中毒も発生している(表2)。 |
|
| PTXあるいはその類縁体を産生するOstreopsis sp.は熱帯〜亜熱帯海域に生息している渦鞭毛藻であるが、九州や四国の沿岸でも確認されており、北上していることは間違いない。アオブダイやハコフグがなぜ特に毒化しやすいのかはよくわかっていないが、Ostreopsis sp.の分布域が拡大すると他の魚も次々に毒化する可能性があるので、日常的なモニタリングが必要である。また、PTX様毒の構造決定と分析法の確立も重要課題であろう。 |
|
| 図3. パリトキシン(PTX)の構造 |
|
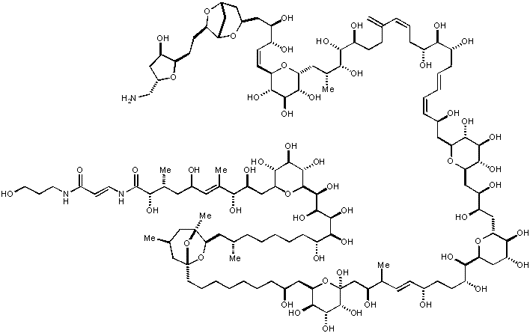 |
|
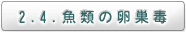 |
|
| 卵巣を食べると嘔吐、下痢、腹痛などの胃腸障害を引き起こす魚が知られている。中毒原因物質が特定されているのは、北海道を主産地とするタウエガジ科のナガズカのみである。北海道では「ナガズカの卵はカラスも食べない」とか「ナガズカの卵はハエもつかない」という古くからの言い伝えがあるため中毒はまれであった。中毒事件は、ナガズカが練り製品原料として出荷されるようになった1960年頃に本州で一時的に続発した。その後の中毒は少なく、最近10年間ではわずか2件である(表2)。原因毒はジノグネリンA〜D(図4)である。 |
|
| 図4. ジノグネリンA〜Dの構造 |
|
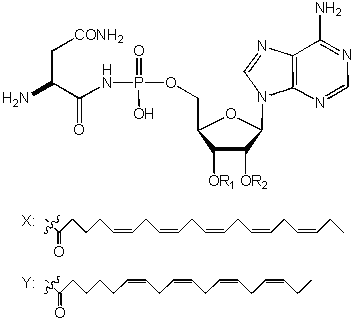 |
|
| A: R1=X, R2=H B: R1=H, R2=X C: R1=Y, R2=H D: R1=H, R2=Y |
|
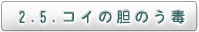 |
|
| コイ科魚類(コイ、ソウギョ、アオウオなど)の胆のうは、眼精疲労、せき、聴力などに効果があるとして中国や東南アジアでは古くから珍重されているが、胆のうの摂取により腎不全や肝不全などを伴った中毒が発生し死者も出ている。中国の統計によると、1970〜75年に82件の中毒が発生し、21人の死者を出している。わが国では死者は出ていないが、1974〜88年に少なくとも17件の中毒症例が報告されている。毒成分は5α-キプリノール硫酸エステル(図5)である。なおわが国では、コイの筋肉(こいこく、あらいまたはみそ煮)による中毒事件が1976〜1978年にかけて一時的に九州で多発した。残念ながら原因毒は未解明であるが、中毒再発防止のためにもコイ筋肉の毒成分に関する知見を得る努力が求められる。 |
|
| 図5. 5α-キプリノール硫酸エステルの構造 |
|
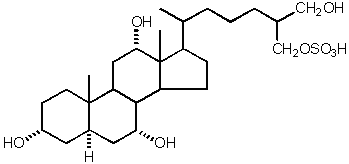 |
|
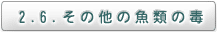 |
|
| 毒とは呼べないかもしれないが、厚生労働省の食中毒統計では動物性自然毒に分類されているビタミンAと脂質を以下に簡単に記しておく。 |
|
| ハタ科のイシナギは肝臓に高濃度のビタミンAを含み、ビタミンA過剰症と呼ばれる中毒の原因となる。食後30分〜12時間で激しい頭痛、発熱、吐き気などが引き起こされ、2日目頃からは顔面や頭部の皮膚の剥離という特異な症状が伴う。イシナギの肝臓は1960年に食用禁止になっている。なお、サメ、マグロ、ブリなどの大型魚、とくに老成魚の肝臓のビタミンA含量も高く、中毒例がある。 |
|
| ギンダラ科のアブラボウズ、クロタチカマス科のバラムツおよびアブラソコムツは、筋肉中の脂質が原因で下痢を起こす魚として知られている。アブラボウズの場合、脂質の主成分は普通の魚と同じくトリグリセリドであるが、脂質含量が50%近くに達することもあるほど異常に高濃度なため下痢が起こる。一方、バラムツとアブラソコムツの場合、脂質含量が約20%と高いばかりでなく、脂質の主成分は下痢を起こすワックスエステル(高級脂肪酸と高級アルコールのエステル)である。バラムツは1970年に、アブラソコムツは1981年に食用禁止になっている。 |
|
|
|
|
| 二枚貝の毒の起源はすべて有毒プランクトンである。二枚貝はプランクトンフィーダーで、有毒プランクトンが大量に繁殖したような場合(例えば赤潮の場合)、摂取したプランクトンから毒成分を取り込み、主として中腸腺に蓄積する。 |
|
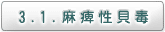 |
|
| 麻痺性貝毒(paralytic shellfish poison、PSP)の成分として最初に単離されたのはサキシトキシンで、その後ゴニオトキシン群、C群など30成分近くの関連毒の存在が確認されている(図6)。PSPはフグ毒テトロドトキシン(TTX)に匹敵する毒性を有し、TTX同様にナトリウムチャンネルを特異的にブロックする神経毒である。したがってPSP中毒の症状はフグ中毒の場合とほぼ同じで、死亡率も高いので欧米ではフグ毒以上に恐れられている。 |
|
| わが国で問題になるPSP産生プランクトンはAlexandrium catenella、A. tamarense およびGymnodium catenatum の3種である。これらプランクトンの調査ならびに二枚貝の毒性検査による監視体制が整備されているので、二枚貝によるPSP中毒の発生は最近10年間ではわずか1件である(表2)。ただし、ホタテガイをはじめとした毒化二枚貝の出荷停止措置(出荷規制値は4 MU/gである。PSPの場合、体重20 gのマウスを15分で殺す毒量が1 MUと定義されている)により受ける経済的損失は甚大である。 |
|
| 図6. 麻痺性貝毒(PSP)の構造 |
|
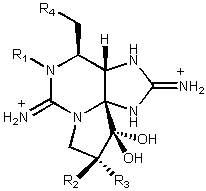 |
|
R1=HまたはOH
R2=HまたはOSO3-
R3=HまたはOSO3-
R4=H、OH、OCONH2、OCONHOHまたはOCONHSO3-
例えばサキシトキシンの場合、R1=H、Rv2=H、R3=H、R4=OCONH2である。 |
|
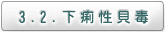 |
|
| 1976年に宮城県と岩手県で、ムラサキイガイの摂食により下痢をはじめとした吐き気、嘔吐、腹痛といった消化器系障害を伴った新しいタイプの食中毒が発生し、この中毒事件を契機に下痢性貝毒(diarrhetic shellfish poison、DSP)が発見された。DSP中毒事件はその後も各種二枚貝により東北地方を中心として続発し、ヨーロッパなどでも主としてムラサキイガイの摂食により起こっている。DSP成分としてはオカダ酸とその同族体であるジノフィシストキシン類(図7)、ペクテノトキシン類、イェソトキシン類が同定されている。このうちオカダ酸とジノフィシストキシン類の下痢原性は非常に強く、中毒症状の主な原因成分である。DSPはDinophysis 属の数種プランクトン(渦鞭毛藻)が産生し、わが国ではD. fortii が主要な毒化原因プランクトンとなっている。PSP同様にDSPの場合も、二枚貝の毒化および有毒プランクトンの発生に対する監視体制が有効に機能しており、最近10年間の中毒例はない。ただし、毒化二枚貝の出荷停止という経済的損失の問題はやはり解決されていない。ちなみに出荷規制値は0.05 MU/g(DSPの場合、体重16〜20gのマウスを24時間で死亡させる毒量が1 MUと定められている)である。 |
|
| 図7. 下痢性貝毒(DSP)の構造 |
|
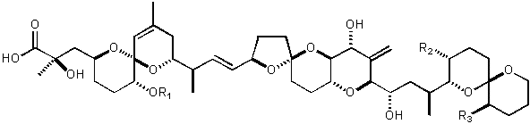 |
|
| |
R1 |
R2 |
R3 |
| オカダ酸 |
H |
CH3 |
H |
| ジノフィシストキシン1 |
H |
CH3 |
CH3 |
| ジノフィシストキシン2 |
H |
H |
CH3 |
| ジノフィシストキシン3 |
acyl |
HまたはCH3 |
HまたはCH3 |
|
|
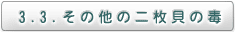 |
|
| これまでにわが国では中毒例はないが、今後の警戒が必要な二枚貝の毒として記憶喪失性貝毒(amnesic shellfish poison、ASP)とアザスピロ酸を取り上げておく。 |
|
| 1987年11〜12月にカナダ大西洋岸のプリンスエドワード島周辺で、ムラサキイガイの摂食により死者3人を含む患者100人以上の集団食中毒が発生した。嘔吐、腹痛、下痢のほかに記憶障害という特異な症状がみられ、原因毒としてアミノ酸の一種ドウモイ酸(図8)が同定されている。ドウモイ酸は中枢神経の興奮性神経伝達物質であるグルタミン酸と構造が類似しているため、グルタミン酸受容体に作用して脳の海馬を選択的に破壊し記憶異常をもたらす。ドウモイ酸の産生者として同定されているPseudo-nitzschia multiseriesなど数種珪藻は日本沿岸にも生息しているし、二枚貝にも低濃度ではあるがドウモイ酸が検出されているので、監視体制の構築が望まれる。 |
|
|
図8. ドウモイ酸の構造
|
|
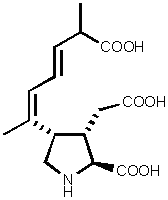 |
|
| 1995年にオランダで、ムラサキイガイの摂食により吐き気、嘔吐、下痢、腹痛などを伴う中毒が発生した。中毒症状はDSP中毒と類似していたが、原因毒はDSPではなくアザスピロ酸-1であることが示された。同様な中毒はその後ヨーロッパ各地で報告され、各種アザスピロ酸(図9)が同定されている。アザスピロ酸の産生者は渦鞭毛藻のProtoperidinium crassipesであると推定されている。 |
|
| 図9. アザスピロ酸類の構造 |
|
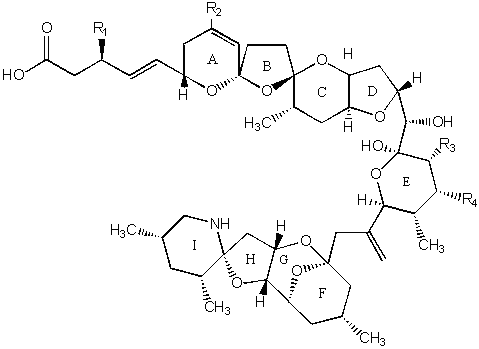 |
|
| |
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
| アザスピロ酸-1 |
H |
H |
CH3 |
H |
| アザスピロ酸-2 |
H |
CH3 |
CH3 |
H |
| アザスピロ酸-3 |
H |
H |
H |
H |
| アザスピロ酸-4 |
OH |
H |
H |
H |
| アザスピロ酸-5 |
H |
H |
H |
OH |
| アザスピロ酸-6 |
H |
CH3 |
H |
H |
| アザスピロ酸-7 |
OH |
H |
CH3 |
H |
| アザスピロ酸-8 |
H |
H |
CH3 |
OH |
| アザスピロ酸-9 |
OH |
CH3 |
H |
OH |
| アザスピロ酸-10 |
H |
CH3 |
H |
OH |
| アザスピロ酸-11 |
OH |
CH3 |
CH3 |
H |
|
|
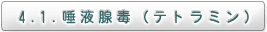 |
|
| エゾバイ科エゾボラ属の肉食性巻貝(ヒメエゾボラ、エゾボラモドキ、ヒメエゾボラモドキなど)はツブとかツブ貝という俗称で流通している。地域によってはエゾボラモドキは赤バイとも呼ばれている。これら巻貝は唾液腺にテトラミン(CH3)4N
+
という毒成分を高濃度に含み(数mg/g)、しばしば食中毒の原因となっている(表2)。食後30分〜1時間で頭痛、めまい、船酔い感、酩酊感、視覚異常などの中毒症状が現れるが、テトラミンの体外排泄が早いため通常数時間で回復する。エゾボラ属の巻貝の大部分は寒海性であるので、テトラミン中毒はこれまでは北海道や東北地方で圧倒的に多かったが、食品流通の広域化のためか中毒の発生が全国的になっているので、特に西日本では注意喚起が望まれる。また、エゾバイ科エゾボラ属巻貝の他に、エゾバイ科エゾバイ属のスルガバイ、フジツガイ科のアヤボラ、テングニシ科のテングニシの唾液腺にも高濃度のテトラミンが検出されている。中毒防止のためには、さらに多くの巻貝についてテトラミンの検索が必要なことはいうまでもない。 |
|
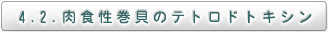 |
|
| 肉食性巻貝によるテトロドトキシン(TTX)中毒としては、1970年に福井県産のバイで1件、1980年前後に静岡県、和歌山県、宮崎県産のボウシュウボラで3件が記録されている。その後わが国では巻貝によるTTX中毒はなかったが、2007年に長崎市、2008年に熊本県天草市で立て続けに、キンシバイを原因とする重篤なTTX中毒が発生した。キンシバイはムシロガイ科に属する殻高2〜3 cmの小型の腐肉食性巻貝で、相模湾以南の潮間帯から水深20 mの砂泥地に生息している。一般的には食用とされていないので市場には流通していない。 |
|
| 長崎県橘湾産および熊本県宮野河内湾産のキンシバイの毒性試験から、内臓だけでなく筋肉も猛毒(1000 MU/g以上)で、これまでに報告のある巻貝類のなかでは最強の毒性であることが判明している。しかも、多くの個体で総毒量は筋肉の方がかなり高く、内臓を除去しても数個体の喫食でヒトの致死量に達する恐れが非常に高い。このようにキンシバイは食品衛生上きわめて危険な種として警戒が必要である。なお、今のところキンシバイ以外の小型腐肉食性巻貝にはTTXは検出されていないが、なぜキンシバイだけに高濃度のTTXが蓄積されるのかは今後の検討課題である。 |
|
| 小型巻貝によるTTX中毒はわが国ではこれまでに例がないが、中国や台湾ではムシロガイ科、タマガイ科およびマクラガイ科の小型巻貝による中毒が頻発しており、多数の死者も出している。2008年7月に厚生労働省は、ムシロガイ科の3属、タマガイ科の2属、マクラガイ科の1属については中国ならびに台湾からの輸入を禁止している。 |
|
|
|
|
| 食べて危ないマリントキシンの概要を述べてきた。ここ数年の間に、ハコフグ類によるパリトキシン様毒中毒、小型腐肉食性巻貝キンシバイによるテトロドトキシン中毒といった新顔の中毒も登場し、新たな対応を迫られている。また、シガテラ毒やパリトキシン様毒を産生する藻類は熱帯〜亜熱帯海域に生息しているが、近年の地球温暖化の影響により北上し、中毒の広域化が懸念されている。マリントキシンに関しては今後の検討課題がまだまだ多いが、ヘルシーな魚貝類を安心して食べることができるように研究が一層進展することを期待したい。 |
|
|
|
|
| 1970年3月に東京大学農学部水産学科を卒業。1975年3月に東京大学大学院農学系研究科水産学専門課程博士課程を修了。日本学術振興会奨励研究員、米国ロードアイランド大学薬学部博士研究員を経て、1977年7月に東京水産大学食品生産化学科に助手として着任し、1989年11月に助教授、1991年4月に教授。その後、大学統合や学科名称の変更により、現在は東京海洋大学食品生産科学科教授。日本食品衛生学会副会長。魚貝類の毒成分、有害元素(ヒ素)およびアレルゲンを研究の3本柱としている。 |
|