|
����܂ŁA�H�̈��S�E���S���x�̊T�v���L���Ă������A�䂪���̋����`�Ԃ̓��������l�������ꍇ�A�����ɂg�`�b�b�o���`�������邱�Ƃ͗e�Ղł͂Ȃ��Ɣ��f����A������K�����玩��Ǘ��̕����ֈڍs���邱�Ƃ��\�z�����B�������A���㎖�̂̔������̔@���ɂ���Ă͖��m�̗v�f���܂ށB���̏ꍇ�A����Ǘ��ƌ����Ă����ȓs���ɂ�鏟��Ȃ����ł͂Ȃ��A(1)�����Ɋ�Â��K���ȊǗ����@�̑I��A(2)���̃}�j���A���������(3)���̎��s�Ɋւ��Ă̋L�^�E�ۑ��A�Ƃ����v�������߂���B
�@�������L�q�����������炵���e���͑傫�����̂����邪�A���Ă̐��H�i�����Ɣ�ׂ�ƁA�g�`�b�b�o��g���[�T�r���e�B�V�X�e���̓����ɂ��A�����i�K�ւ̑k�y��ǐՂɂ������Ƃ��i�i�ɑ��������B�����͂܂��������Ă��Ȃ����A����̂悤�ɊW�҂����i�K���L��ɔg�y���Ă���ꍇ�����A�e�i�K��g�D���u�V���v�̏ؖ����ł���悤�ɂ��Ă������Ƃ��d�v�ł���B
 �������N�̐H�i�̈��S�Ǘ���@�̓������A�t�[�h�`�F�[���S�̂Ō����ꍇ�A���ɔ_�ƕ���ɂ�����f�`�o�̌���ł̐i���͒��ڂɒl����B�u21���I�V�_��2007�v�Ōf�����S��2000�Y�n�ւ̂f�`�o�����͂��ł�1500�����ɋy�Ԃƌ�����B�m���ɂ����ł����f�`�o�̒��g�͈ꗥ�ł͂Ȃ��A���ɂ́u������v�Ƃ������x�����̂����邩���m��Ȃ��B�������Ȃ���A���Ȑ錾�ɂ��f�`�o�̎��{���̂��̂��A�_�ƕ���ɂ����鐶�Y�҈ӎ��̌���ƒ�ւ́u���S�v���^�̓_�ł���߂ĈӖ��������̂ł���A���̐쉺�ɂ��鐻�����H����ɂ�����g�`�b�b�o�蒅�̐L�єY�ݏɑ��ΏƓI�ł�����B
�@���Ȃ킽�A�f�`�o�����̐i�W�́A�t�[�h�`�F�[���S�̂ɂ�������S�Ǘ��̕K�v���������u�H�i���S��{�@�v�̗��O�݂̂Ȃ炸�A�쉺�̏���҂�����҂ł��鏬���i�K����̃j�[�Y�̊ϓ_������A�܂��u���[�r�b�q�̌����v�I�ϓ_������A���ɐ������H����ւ̉e���͏��Ȃ��Ȃ��Ɣ��f�����B
�@����ɁA����܂łg�`�b�b�o�ɔ�r�I���̔����������ʒi�K�ɂ����Ă���O�Ƃ���Ȃ����Ԃ����邱�Ƃ��\�z�����B
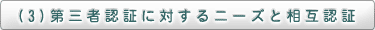 ������ɂ��Ă��A����Ǘ���@�̓������i�W����ƐM�����̓_�ő�O�ҔF�̎���I�擾�����悩��̎擾�v�������܂邱�Ƃ��\�������B
���݁A�f�`�o�ɂ��ẮA�i�f�`�o��f�����������f�`�o�Ƃ��������ԃ��x���ł̔F�ؐ��x�����邪�A�g�`�b�b�o�́A���I�F�Ƃ��Ẵ}�����̑Ώەi�ڂ����肳��Ă��邽�߁A��O�ҔF�Ƃ��Ă͓s���{����Ǝ킲�Ƃ̖��Ԓc�̂̔F�ؐ��x�Ɉˑ�����X�����݂���B
�@���̂����A�s���{���̔F�͂��ꂼ�����قȂ邽�߁A������z�������ʕi�Ɋւ��Ă͍�����������B����A���ꂼ��̑��ݔF�ɂ��Ă̌������K�v�Ƃ���邪�A���Ƃ��Ă̓���I�F�V�X�e���̌��������߂��Ă�����̂Ǝv����B
�@����A�h�r�n22000�́A�g�`�b�b�o��f�`�o���킸�A�t�[�h�`�F�[���S�̑g�D��ΏۂƂ��A�����ۋK�i�Ƃ��Ă̒ʗp��������_�őO�L�̉ۑ�������ł���ʒu�Â��ɂ��邪�A��ƂƂ��Ă͎萔�����̓_�ʼnۑ肪�c��B
�@������ɂ��Ă��A�������i�ނقǁA�ȏ�̂悤�ȏ����݉����A�܂����݉����Ă͂��߂ĊW�҂��݂����ł��悢�Ƃ����d�g�݂ɂ��Đ^���Ȍ����ɓ��邱�Ƃ��o������̂Ǝv����B
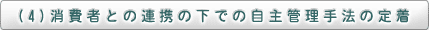 �u�g�`�b�b�o��f�`�o������Ɩׂ��邩�H�v�Ɩ���邱�Ƃ����邪�A���̏ꍇ�ɂ́u�������邱�Ƃɂ��K���ׂ���Ƃ������Ƃ͂Ȃ����A�ׂ����Ă����Ƃł͓������Ă���Ƃ��낪�����B�v�Ɠ����Ă���B���̂��Ƃ́A�K�������������Ȃ����Ƃł͂Ȃ��A�ׂ����Ă����Ƃ́A�f�[�^��͂��\�����{���Ă���Ƃ��낪��������ł���B���Ȃ킿�A�g�`�b�b�o�Ȃǂ̈��S�Ǘ��Ɋւ���f�[�^���A�P�ɖ����ꎞ�����̂��߂ɋL�^�E�ۑ����Ă��邾���ł͂Ȃ��A�i�������ڋq�j�[�Y���̊ϓ_����u��́v�̈�܂ō��߂Ċ��p���Ă��邩��ł���A����������Ƃ͑��̃f�[�^(���i�Ǘ��A�i���Ǘ��A�ڋq���N���[���A�̔����ѓ��X)�ƗL�@�I�ɘA�g�����Ă��邱�Ƃ������ł���B
�@�܂��A�悭�g�`�b�b�o�������Ă��A���烁���b�g���������Ȃ��Ƃ����ӌ��������B�����̓��������b�g�͉����H�P�ɖ�����̎��̔������Ɂu�V���v�̏ؖ������邽�߂́u�ی��v�Ȃ̂��H�Ƃ����{���I�Ȗ₢�ɑ���͎����ɏ��邱�ƂƂ��āA����@����O�ҔF�����Ƃ��Ă��A��{�I�ɂ̓V�X�e���F�ł����Đ��i�F�łȂ��A���������ď���҂�����҂ɁA���̓w�͂��`��炸�ɕ]��������Ȃ��A�Ƃ����������ĔF�����邱�Ƃ͈Ӗ�������B
�@���Ȃ킿�A����������g�݂��Ȃ���Ă��邱�Ƃ����I�ɊO���A���ɏ���ғ��ɒm���Ă��炤�w�͂��L���ł���B
�@���N�x�_�ѐ��Y�Ȃ̎��ƂŁA����Ғc�̂ƘA�g�����g�`�b�b�o��@�������i�Ɋւ����g�݂�����B����́A����҂ɂg�`�b�b�o�Ƃ������̂ƁA���̓�������̎�g�ݓw�͂�m���Ă��炢�]���Ɍq����Ƃ������e�̎��ƂŁA�g�`�b�b�o�Ɋւ��锻��₷������c�u�c�̍쐬�ƌ��n���w�̎��{���s���Ă���B���n�Ɍ������r���łc�u�c�����Ă��炢�A���n���@�ɂ��A��藝����[�߂邱�Ƃɂ��A�u����������Ƃ̐��i�ł���ΐ��������v�Ƃ����]���������Ă���B
�@����������g�݂͍��̎��ƂƂ��Ď��{����Ă��邪�A���ۂɂ͍s���Ɠ����҂ł����Ƃ̎���I�o�q���K�v�ł���A���̌��ʕ]���ɂȂ�����̂Ǝv����B
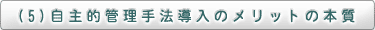 �g�`�b�b�o��f�`�o�͊Ǘ��̂��߂̂����܂ł��c�[���̈�ł���A�����̎g�����͎��i��F�؎擾�̂��߂Ƃ����ړI���ŏ��ɂ���̂ł͂Ȃ��B�����܂ł��A����҂Ɉ��S�E���S�ƃZ�b�g�Ő��i��͂��邽�߁A�Ƃ������_��Y��Ȃ��悤�ɂ��ׂ��ł���B�������≡���т̊Ǘ���@�͌����ă����b�g������ꂸ���S�ɂȂ邾���ł��邱�Ƃ́A����܂�10�N�ȏ�̓������ъ�Ƃ����Ă����炩�ł���B�����Ƃ��Ď�����������ɓ��B���邽�߂ɁA�n���ł��悢�̂ŏ�ɓƎ��̂o�c�b�`�T�C�N�����܂킷���Ƃ��L���ł���B
�@�܂��A��@�݂̂ɒ������Ă��\���̋U���Ȃǂ͉������Ȃ��B�ŋ߂̕\���s�������ɑ���������̂́A�o�c�҂������}���ŒS���҂̌������Ƃ��Ȃ��A���邢�͋t�ɒS���҂��o�c�҂ɏd�v�Ȃ��Ƃ�`���Ă��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł������B�����͉q���E�i���Ǘ��̖��ł͂Ȃ��A�����R�~���j�P�[�V������o�c�҂̐ӔC���q�ϓI�ɓI�m�ɂȂ���Ă��Ȃ��Ƃ���ɖ�肪����B���Ȃ킿�A�H�i���S�Ɋւ���}�l�W�����g�̕s�K���ɋN��������̂ł���B�h�r�n22000�́u�o�c�҂̐ӔC�v�ɂ����āA���̗v���������L���Ă��邪�A����A����҂�����҂́A�w����ɂ��������}�l�W�����g���I�m�ɂȂ���Ă��邱�Ƃ���w���߂Ă���ł��낤���A���̑���u���Ă������Ƃ͖��ʂł͂Ȃ��B����ɁA�����̔��[�����O����̍����ɂ�邱�Ƃ���A����͓��O����̒ʕ����̐��̗L�����M�������Ƃ̎w�W�ɂȂ肤��B
�@�܂��A��Ƀt�[�h�`�F�[���S�̂ł̊e�i�K�̈��S�E���S�m�ۑ��c�����Ă������ƁA�����Ă��̒��ł̎���̈ʒu�Â��m�ɂ��Ă������Ƃ��d�v�ł���i �}�P�j�B
�@����A����҂�����҂ɒm���Ă��炤�w�͂��K�v�ł���A�����{�N�x���炻�̎�g�݂��s�Ȃ��Ă���B�����������̎�g�͕ʂƂ��āA����I��g�̎��ゾ���炱���A��Ƃ�g�D�Ƃ��Ă��A�����E���̂��Ȃ����펞�ɁA�����Ɏ���̐^���Ȋ���������ғ��ɓ`���邱�Ƃ��ł��邩���A�M���m�ۂ̌��ƂȂ�A��Ɗԋ����̍��ɂȂ���ł��낤�B����҂��Ƒ��Ƃ��Ĉӎ����H����邱�Ƃ���ł���B |