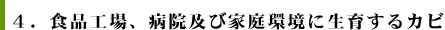 |
|
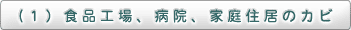 |
|
食品工場、病院、マンション、ホテル、個人住宅、ビル事務所等は密閉性が良好であり、暖房等により室内は冬でも暖かく、乾燥している状態となっている。外気との温度差の大きい冬季においては、室内の壁面、窓ガラスに結露し、壁面の内装材の表面や塗装面にカビが多く発生する。
カビの胞子は空気中に飛散し、室内の空気を汚染する。また、空気中に浮遊している胞子はエアコンの吸入孔から空調装置の内部に入り、繁殖に適したプラスチック部分や塗装面、エアフィルターなどで繁殖する。そしてこれらの部分を通過する空気と共に胞子がダクトを通り室内の空気中に放出される。空気中に浮遊するカビの胞子が多くなると、アレルギー性の気管支炎やぜん息の発作が起こる場合が知られている。そしえ、床とじゅうたんの間や壁にカビが繁殖すると、ダニがカビの匂いによる集まってきてエサとする。ダニや小動物のいるところはカビが必ず発生している。また観葉植物はカビの発生源でもある。繁殖する主なカビはアルテルナリア、クラドスポリウム、トリコデルマ、オーレオバシジウムなどである。
室内のカビの発生を防ぐには、室内のエアコンを掃除してカビのエサになるものを除去しておくことが必要である。室内がカビの発生しやすい条件(60〜70%の湿度、20〜25℃の温度)を避けるように窓を開けて風を通すとよい。
さらに結露の出来やすい壁、窓や畳の下に断熱材(厚手のカーテン、日よけシート)を張るとよい。
湿気の多い日本はカビの多い国である。梅雨時期のみならず冬にも結露が起こり、部屋全体にカビが発生する。結露は急激に室温が下がったり外気温との温度差が大きくなったりすることで、室内の暖められた空気に含まれた水分がガラス窓や壁紙に水滴となって現れる。 |
|
結露が原因となって生じる現象
(1)カビが生える原因となる。
(2)カーテンなどが汚れる。
(3)壁など建材が傷む。
(4)異臭がする。
(5)湿度の変化により体調及び気分が悪くなる。 |
|
結露には、目に見える結露(表面結露)と建物の内部で起こる結露(内部結露)がある。表面結露は冷蔵庫から出したものの表面に水滴が付いたり、朝起きたときに窓ガラスの表面にびっしり水滴がついている現象である。また、冬、締め切った部屋で鍋物をしたりお湯を沸かすと窓に水滴がつくものでこれらは全て、そのものの表面に発生するので表面結露と呼ばれる。
内部結露は押入れの床や壁のクロスからカビが生え、あるいはジトジトと湿気を帯びているとか、畳をめくると、裏面がベタベタしている現象は建物内部から発生してくるもので、内部結露と呼ばれている。また流しの下の結露も多く、排水パイプの表面に結露しやすい。金属は特に結露しやすく、塩化ビニール等のビニール管は結露しにくい。
最近の食品工場、病院、個人住宅は多くの新建材が使用され、塗料を塗り、プラスチックが多く使用されるようになってきた。木材や繊維と異なって塗装膜やプラスチック製のシートは空気が通過しないため、家の内部がむれ、アルミサッシが水分を遮断して室内の湿度が高くなっている。このため室内ではカビが多く増殖して、健康を損ねることがある。 |
|
結露防止対策
(1)換気扇等で換気をする。
(2)除湿機や除湿剤を使って除湿をする。
(3)暖房器具の見直し。石油ストーブやファンヒーターの燃焼系の暖房器具は水蒸気を発生させる。
エアコンやオイルヒーターなどの非燃焼系の暖房器具にすると結露防止になる。
(4)器具や家具の配置を改良する。室内に空気が滞留しないようにする。
(5)観葉植物を置かない。観葉植物からは多くの水分が出ている。
(6)結露防止シートを窓ガラスに張る。
(7)結露防止ヒーターを窓際に設置する。
(8)結露取りワイパーをつける。
(9)結露吸水テープを張る。
(10)結露防止スプレーでスプレーする。 |
|
日本の木造住宅の多くは天井に杉板、土壁や障子、フスマで囲み、床を高くして畳を敷いているので高温多湿の日本の夏に適した住宅である。しかし、日本の木造住宅にも暖房等により床下、窓、壁等に結露が起き易く、木材が湿りがちとなり、カビが繁殖する。
この木材腐朽菌はキノコの一種で白色のものと褐色のものとがある。これらのカビは木材又は生きた樹木について、木材の含水率が25%以上となるとよく繁殖し、セルロースやリグニンを分解して木材を腐らせるので床下等の通気をよくすることが大切である。このため最近の建築会社では木材に薬剤を塗布するか、薬剤液に含浸させて用いている。耐朽性の強い木材としてはヒノキ、クリ、ケヤキ、ヤマサクザラ、ベイヒ、チーク、タイヒ等がある。表2に建築物の腐朽カビを示した。 |
|
| 表2 建築物の腐朽カビの種類 |
|
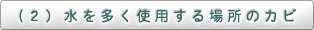 |
|
水を多く使用する部屋は、湿気が多く温度が高いのでカビが生育しやすい。天井、壁、タイルの目地などの黒い斑点が発生する。これはカビの集落でクラドスポリウム(黒、ダークグリーン)、フオーマ(灰色から赤色)、ペニシリウム(青黒色)、アルテナリア(黒)、アースリウム(黒)、オウレオバシヂウム(黒)等である。このほか浴室からは酵母としてロドトルラ(赤黒色)、カンジダが細菌としてはミクロコッカス、スタフィロコッカス、ペディオコッカスなどの球菌が分離されている。浴室の材料(タイルの目地、コンクリート部、シリコン樹脂)の多くがアルカリ性であるので、さらに石鹸やシャンプー等もアルカリ性が多いのでアルカリ耐性のカビが多い。
タワシでよくこすりとり、TBZ(チアベンダゾール)のような殺菌剤や市販のカビとり剤を用いるとよい。 |
|
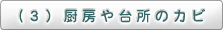 |
|
家庭の中で一番カビの生えやすい場所である。食品の加熱調理により発生する水蒸気は食品あるいは器物に水分を与える、焙焼、油揚げなどによって揮発する有機物は壁、天井などに付着して栄養分を与え、また加熱による室温上昇によりカビが生育する。流し台の周囲の防水シリコンの目地とか、排水孔などには食物の残りかすが付着し、カビが繁殖しやすい。シリコンにはクラドスポリウム、アルタナーリア、オーレオバシディウムなどの黒色のカビが生育しやすい。また調理台の周囲や湯わかし器の上部も湿っていて、カビが発生しやすい。窓のアルミサッシもほこりと油で汚れやすい。特にガラスを保持している塩化ビニール製のシール部分にクロカビが生える。
したがって、台所の換気をよくして、調理台、流し台、湯沸かし器、ガスレンジ、食器だな、床、窓などを掃除することがカビの発生防止対策となる。 |
|
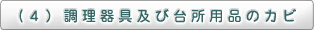 |
|
調理器具の中で特にまな板、包丁、フキンなどはカビに汚染されており、それが食品を変質させたり、食中毒を起こす原因となる場合がある。木製のまな板は適度の水分があり、包丁の傷で食物残渣が残りやすく、汚染源となる。
傷の付きにくい含水性のないプラスチックや合成ゴムのまな板が多くも用いられるようになってきた。
包丁も金属部分の傷や金属と柄の接合部に食品成分が入り込み、カビが繁殖しやすい。またフキンもカビによって汚染されている場合が多いので、フキンをこすりつけることによりカビを付けていることがある。このようにまな板、包丁、フキンはカビが繁殖しやすいので、使用後は洗浄、消毒、乾燥を行なっておくことが大切である。
食器や野菜を洗う台所用洗剤の原液にはカビは生育しないが、原液が皮膚に付くと皮膚が荒れたりするので、予め水で薄めた洗剤をビンに詰めて使用している人が多いが、気温が高くなる夏季においてはこの薄めた洗剤のなかでカビが増殖している場合がある。 |
|