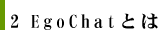 |
|
京都大学の西田教授は、大量の情報が行き交う現在のインターネット社会においても会話型コミュニケーション支援技術が重要であることを指摘し、これに資するツール群の開発をおこなっている 。EgoChatはその中核となるもので、西田グループの一員である久保田研究員が中心になって開発したプレゼンテーションシステムである 。EgoChatはその中核となるもので、西田グループの一員である久保田研究員が中心になって開発したプレゼンテーションシステムである 。EgoChatの特長は次のとおりである。 。EgoChatの特長は次のとおりである。 |
|
 |
|
| EgoChatシステムでは、ウェブ上で本人の代わりに分身エージェントが、訪問者に対応するという体裁をとっている(図2)。分身エージェントは、口を開閉する、お辞儀をするなどの簡単な動作を交え、表示された画像を使って文章を読上げて説明する。学会の口頭発表のようにスライドを使って発表するイメージである。このプレゼンテーション形式によって情報を受け取る人に多様な働きかけができ、飽きさせずに情報提供ができる可能性を高めている。 |
|
| 図2 EgoChat番組の例 |
|
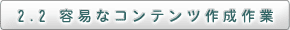 |
|
| EgoChatシステムでは、画像と説明文からなる一連の知識カードを、音声合成技術や動画生成技術を用いて音声と動画からなるコンテンツを自動的に作成し、発信する。コンテンツ作成者は各知識カードを作成し、それを並べて、ストーリーを構成すればよい。あとはEgoChatシステムが実行してくれる。このような構造を採用したため、ストーリーを大きく変更する場合でも、知識カードの並べ方を変えたり、少数の新しい知識カードを加えたりするだけで対応できる。また、各知識カードはさまざまなストーリーでそのまま利用できるし、多少修正して使うこともできる。つまり、過去の努力は蓄積され、将来にわたって簡単に利用できる。 |
|
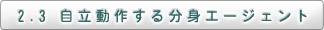 |
|
| EgoChatの分身エージェントは単なるアバター(本人を表す記号)ではない。本人の指示なしに自立的に動作することから現実の秘書、あるいは窓口係に近い。分身エージェントは、すでに答えが用意されている質問に対してはそのまま回答する能力があり、本人を煩わすことはない。しかし、分身エージェントが答えられない質問の場合には、本人に取り次ぎ、本人と質問者の間の高レベルな会話を開始できるようにしてある。窓口係として最低限の仕事をこなす能力を持っているのである。この窓口係は、いつでもどこからでも呼び出すことができ、同時に何人でも対応できるという点だけから見れば、現実の人間以上の存在とも言える。 |
|