| ◆ HOME >カビが産生する毒(マイコトキシン) |
 |
|
![はじめに]](img/01_cap01.gif) |
|
| 今年もまた蒸し暑い梅雨の時期がやってきました。この時期になると、洗面所や風呂場では短期間で黒カビが目に付くようになり、その対応に苦労されることでしょう。生えてしまった黒カビを取り除くのには、次亜塩素酸ナトリウムを含むカビ取り剤の使用が効果的ですが、その使用時における危険性等を考慮しますと、やはり塩素系薬剤の使用は控えたいものです。湿気がこもりやすい場所では風通しを良くする、また、水を使用する場所では水滴をまめにふき取る等の日頃の行いがカビの発生を防ぐ効果的な方法となります。さて、この時期はやはり食品のカビ発生にも注意が必要でしょう。食パン等を冷蔵庫に保管せずうっかり室内に放置し忘れますと数日の内にカビが生えてしまった経験をお持ちの方も多くみえることと思います。このような場合、我々は食中毒を恐れ、食べずに捨ててしまうのが最近では一般的ですが、昔はカビが少々生えた程度のパンならもったいないからとカビが生えている部分を除き食べたものでした。また、お正月用のお餅や鏡餅に青カビが生えてもやはりカビを削りとり少々カビ臭くても食べ、さらにはそのようなお餅を水につけて保存し食べたりもしましたが、気分が悪くなったり下痢したような経験はほとんど無かったと思います。カビは細菌のように人の健康に影響を与えるような毒を産生しないのでしょうか。いいえそうではありません。人類はこれまでにカビが産生する毒(マイコトキシン)により時には死に至る重大な健康被害を受けている歴史があり、また、近年では微量のマイコトキシンを長期に渡って摂取することにより発生する慢性毒性が世界中で問題となっています。そこで、今回はこのカビが産生するマイコトキシンについて簡単にご紹介致します。 |
|
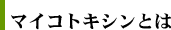 |
|
| マイコトキシンとはカビが産生する第二次代謝産物(自分の体を成長させるため以外の代謝物)の中で、人および動物に対して有害な生理作用を示す化合物の総称です。カビが発生し有害なマイコトキシンが蓄積した農産物を摂取することにより起こる中毒をカビ毒中毒症(真菌中毒症、マイコトキシコーシス)といい、古来ヨーロッパでは真菌中毒症によりたびたび数万人の死者を出し、第二次世界大戦後のソビエト(現ロシア)ではやはりマイコトキシンにより数多くの死者を出しています。我が国においても戦後、赤カビの発生した小麦を使用したうどんやすいとんを食べて急性胃腸炎をたびたび起こしたとの報告があります。最近では、2004年にアフリカのケニアにおいてカビの発生したトウモロコシ(図1)を食べ、患者317名中125名が肝障害により死亡しています。このようなマイコトキシンによる死亡例や急性中毒症状は、何れも食糧難のためカビが生え多量のマイコトキシンを含んでいる農産物でも食べざるを得なかった特別な状況下に発生したもので、現在世界的に見てもその発生頻度は極めて低いものと考えられます。近年世界的に問題となっていることは、マイコトキシンを長期間摂取することによって発生する慢性毒性、すなわちその発ガン性や免疫機能障害等です。これまでに数多くのマイコトキシンが発見されていますが、農産物におけるその汚染頻度や毒性の面から重要視されているものは限られています。表1に現在、世界的に問題となっている主要なマイコトキシンを示しました。 |
|
 |
|
| 図1. カビが発生したトウモロコシ |
|
| 表1 主なマイコトキシン、産生菌、汚染食品および毒性 |
|
| マイコトキシン |
主な産生菌 |
主な汚染食品 |
毒性 |
アフラトキシン
(B1, B2, G1, G2) |
A.flavus
A.parasiticus
A.nomius |
ナッツ類、トウモロコシ、コメ、ムギ類、
ハトムギ、綿実、香辛料
|
肝ガン、肝障害、腎障害 |
| オクラトキシンA |
A.ochraceus
A.carbonarius
P.verrucosum |
トウモロコシ、ムギ類、ナッツ類、マメ類、
コーヒー豆、レーズン、ワイン、ビール、
豚肉製品 |
腎ガン、腎炎、催奇形性 |
トリコテンセン類
デオキシニバレノール
ニバレノール
T-2, HT-2 |
F.graminearum
F.culmorum
F.sporotrichioides |
ムギ類、コメ、トウモロコシ |
消化器系障害、臓器出血、
皮膚炎 |
| ゼアラレノン |
F.graminearum
F.culmorum
|
ムギ類、ハトムギ、トウモロコシ |
女性ホルモン作用 |
| フモニシン (B1, B2, B3) |
F.moniliforme
F.proliferatum |
トウモロコシ |
ウマ白質脳炎、ブタ肺水腫、
発ガン促進 |
| パツリン |
P.expansum |
リンゴ、リンゴ果汁 |
脳・肺浮腫、毛細血管障害 |
|
|
| A : Aspergillus, P : Penicillium, F : Fusarium |
|
この表から分かりますように、主要なマイコトキシンを産生するカビは主としてAspergillus(アスペルギルス、コウジカビの仲間)、Penicillium(ペニシリウム、青カビ)およびFusarium(フザリウム、赤カビ)の3種類の属に分類されます。Fusarium属のカビは圃場菌類と呼ばれ、農作物の栽培中に侵入し増殖する、いわゆる植物病原菌です。日本においては毎年麦類の赤カビ病が発生しており、その発生予防は未だ困難のようです。一方、AspergillusやPenicilliumに属するカビは貯蔵菌類と呼ばれ、収穫後の農産物の貯蔵や運搬期間中に侵入し増殖する非病原菌です。そのため、一般的にこれらのカビの発生を防ぐためには農産物の貯蔵や運搬時における温度や湿度の管理が重要となります。コウジカビは日本でおなじみの日本酒、焼酎や味噌等の発酵食品に用いられる有用なカビですが、日本の発酵食品に用いられるコウジカビはマイコトキシンを産生しないことが判明していますのでご安心下さい。
これらのマイコトキシンはこれまでにその重要性から、FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)や国際ガン研究機関(IARC)によりリスク(健康への悪影響が発生する確率と影響の程度)評価がなされ、また、国際食品規格委員会(Codex)等ではそれらの評価に基づき、基準値設定やリスクマネジメント(リスク管理)の検討が行われてきました。表2にJECFAによって提示されましたマイコトキシンの暫定最大一日耐用摂取量を示しました。「耐用摂取量」という言葉が聞き慣れないかと思いますが、マイコトキシンはカビが産生する自然毒であり、現在の科学ではその存在をゼロあるいは完全にコントロールすることが不可能です。そのため現時点までに動物実験より得られた毒性評価から、ヒトが一生涯摂取しても健康被害は起きないと推定される量が決められ、耐用摂取量とされています。また、今後動物実験より新たな情報が得られれば耐用摂取量も変わってくるためにあくまで暫定値としています。天然物で最強の発ガン物質と言われるアフラトキシンB1がこの表に挙げられていませんが、これはアフラトキシンB1の摂取量とヒトの肝臓ガン発生と相関があることが疫学調査によりすでに判明しており、また、発ガン物質の閾値(毒性が発現しない最小量)はないという考え方から、耐用摂取量の設定は困難だからです(JECFAによりアフラトキシンB1摂取による肝臓ガン発生率の算定式は示されている)。 |
|
| 表2 JECFAによって評価されたマイコトキシンの暫定最大一日耐用摂取量 |
|
| マイコトキシン |
無作用量(NOEL)/最小作用量(LOAEL)
(μg/kg体重/日)
動物種、投与期間、作用 |
暫定最大一日
耐用摂取量
(μg/kg体重/日) |
安全係数 |
年 |
| パツリン |
43 (NOEL) ラット、週3回、2年間投与 |
0.4
|
100 |
1995 |
| オクラトキシンA |
21 (NOEL) ラット、2年間投与、腎腫瘍 |
0.1 (週間) |
1500 |
2001 |
| ゼアラレノン |
40 (NOEL) 若メスブタ、15日間、ホルモン作用 |
0.5 |
100 |
1999 |
| デオキシニバレノール |
100 (NOEL) マウス、2年間投与、体重減少 |
1 |
100 |
2001 |
| T-2/HT-2 |
29 (LOAEL) ブタ、3週間投与、白血球減少等 |
0.06 |
500 |
2001 |
| フモニシンB1, B2, B3 |
200 (NOEL) ラット、728日間、腎毒性 |
2 |
200 |
2001 |
|
|
さて、日本ではこれらのマイコトキシン汚染は大丈夫だろうか、どのように管理されているのだろうかと気になるところです。1971年にアフラトキシンB1の基準値10μg/kg(現在、全食品対象)が設定されて依頼、およそ30年間他のマイコトキシンの規制は行われてきませんでした。しかし、上記の国際的な動向を受け2001年に厚生科学研究の一環として研究班が組織され、市販牛乳中のアフラトキシンM1(アフラトキシンB1の代謝物、家畜の乳等に排泄、発ガン性はB1の約1/10)および小麦玄麦中のデオキシニバレノール汚染調査が行われました。この調査結果を受け、厚生労働省は2002年に小麦玄麦中デオキシニバレノールの暫定基準値1,100μg/kgを通知しました(牛乳中アフラトキシンM1による発ガンリスクは全く無視できることが判明したため基準値設定は見送られた)。また、2004年には農林水産省および東京都健康安全研究センターの調査結果を受け、リンゴジュースおよび原料用リンゴ果汁におけるパツリンの規格基準値50μg/kgが施行されました。その後、厚生労働省においてはマイコトキシン汚染調査班が組織され2004年から2006年までの3年間、日本に流通している食品におけるアフラトキシン(国際基準との整合性を図る目的で)、オクラトキシンAおよびフモニシン(国際的に基準値設定の方向)についての汚染調査が行われました。現在、この調査についての最終的な報告書は出来上がっていませんが、この調査結果を受け、近い将来にはアフラトキシンの規制値変更およびオクラトキシンAの規制値設定がなされることと思います。
上記のようなマイコトキシン汚染調査は今後も厚生労働省および農林水産省において引き続き行う予定であり、何れこれらの結果をご紹介出来る機会があるかと思います。今回誌面の都合上、それぞれのマイコトキシンの毒性、汚染状況等は省かせて頂きました。詳細をお知りになりたい方は、昨年下記の雑誌にてマイコトキシンに関する総説が執筆されました。ぜひご参照下さい。 |
|
食品・食品添加物研究誌 FFIジャーナル(無料配布誌)、Vol. 211、No.12 (2006)
(FFIジャーナル編集委員会、Tel: 06-6333-0521、E-mail: ffij@saneigenffi.co.jp) |
|
| 尚、来る9月6日(木)に神戸市勤労会館において日本マイコトキシン学会第62回学術講演会が開催されます。この学会には大学や公的研究機関における研究者だけでなく、民間の検査機関や食品あるいはビール業界等様々な方々が参加されております。皆様方のご参加をお待ちしております。 |
|
| 連絡先:神戸市環境保健研究所(責任者 田中敏嗣、杉浦義紹、Tel 078-232-1881) |
|
|
|