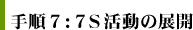 |
|
 |
|
7Sでまず実施するのが、整理です。
整理とは、要る物と要らない物を区別し、要らない物を処分する事です。
製造現場には要らない物が散乱しています。ところが、毎日見慣れている人は要らない物に気付きません。又は、要らない物に対し「勿体無い」とか「情」が入ってしまい処分出来なくなっています。
この要らない物が散乱する状態において、作業場を狭くする、作業動線があまり取れなくなる等の弊害が発生し、作業効率を悪くする、労働安全衛生上も不安定で事故を起こす恐れが出てきます。
そこで、要らない物をはっきりみえる形にする為に「赤札作戦」を実施します。
「赤札作戦」とは、赤い紙に「5.ガイドラインを設定する」において決定したガイドラインを予め書いておき、製造現場内にある、原材料、仕掛品、製品、設備、治具、工具、備品等全ての物に対し、1つずつ確認を行い、不要物に対し「赤札」を貼り付け、要らない物を目に見える形にしていくことです。
従業員一人一人が管理担当するエリアマップにおいて整理を実施します。
不要と判断する物に赤札を貼り付け、不要在庫一覧表に同時に記載していきます。
製造現場に赤札が多く貼り付けられる事により、「何故、ムダな物を購入したのだろう、ムダなスペースを使用していたのだろう」とムダを見える形にする事で、現状を反省して頂きます。
一定期間各作業員が整理活動を行った後、委員会メンバーにより各工場内を巡回確認し、別の目により整理活動を実施していきます。 |
|
 |
|
| 担当者による赤札作戦 |
|
|
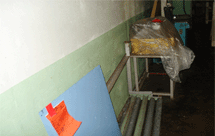 |
|
| 赤札が張付けられた物 |
|
|
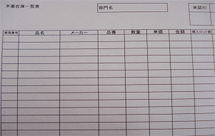 |
|
| 不要在庫一覧表 |
|
|
|
| 次に赤札を貼り付けた物(不要在庫一覧表、不要施設・設備一覧表に記載)に対し、委員会において、廃棄、別の場所で保管等決定します。 |
|
|
|
|
 |
|
整頓とは、「整理」において要る物と判断された物に対し、定位置管理を行い、識別を行うことです。
定位置管理とは、定められた場所に定められた物を定められた数量保管する事です。
識別とは、置き場所に名札を設置し、誰でも置場を認識出来る状態にする事です。すなわち、作業工程から探すムダ、使いにくいムダ、戻しにくいムダを排除する事です。 |
|
 |
|
| 清掃用具放置 |
|
 |
|
| 未整頓の棚 |
|
 |
 |
|
| 吊下げ保管(明示) |
|
 |
|
| 整頓(表示)され先入れ先出しルールの棚 |
|
|
|
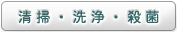 |
|
清掃とは、乾燥状態でゴミや埃が無いように掃除をする事です。
洗浄とは、湿潤状態でゴミや埃が無いように掃除をする事です。
殺菌とは、微生物を殺滅したり、除去したり、増殖させない事です。
しかし、単に掃除をする事ではなく、前段階での「整理」により作業現場から要らない物を処分、「整頓」により要る物に対し置場を決定してから効率よく掃除を行うことです。
清掃は全従業員により出来映えにバラツキがあってはなりません。
そこで、文書化されたマニュアルが必要となります。
マニュアルには、どこを、だれが、いつ、どのようにしたかの項目を含めます。
微生物検査を実施し、マニュアルに従った清掃、洗浄、殺菌の出来映えを確認します。
検査結果が良ければ、マニュアルとして確定します。 |
|
|
|
|
 |
|
食品産業において、7S活動の目的は清潔です。
清潔とは、整理、整頓、清掃、洗浄、殺菌が出来ていて微生物レベルでの綺麗な状況のことを言います。
上記取り組みが確実に実施されて、初めて目標としている清潔にたどり着けることが出来ます。 |
|
 |
|
躾とは、整理、整頓、清掃、洗浄、殺菌、清潔における約束事やルールを守る事です。
いつ何時でも定められたルールに則り行動し、7S活動を維持発展させる要が躾です。
躾の方法として、教育訓練プログラムに準じた定期的な講習会の実施、各現場でルールを掲示し、目で見る躾を実践しています。 |
|
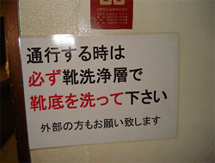 |
|
| 入室時靴洗浄槽注意 |
|
|
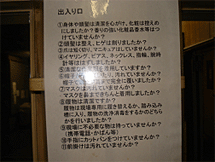 |
|
| 入室時のルール |
|
|
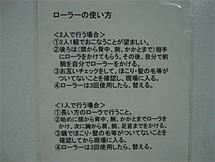 |
|
| 粘着ローラールール |
|
|
|
 |
|
| 業者へ啓蒙 |
|
|
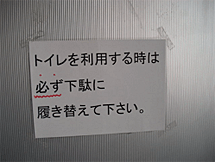 |
|
| トイレルール |
|
|
|